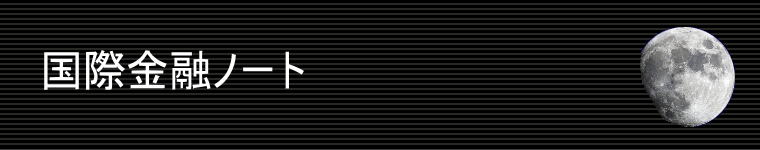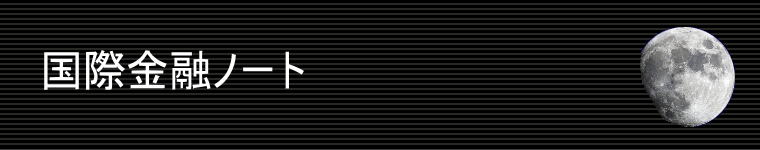VAR概念と『リスク管理』
荒巻 昌宏
Ⅰ.金融機関・一般事業法人にとってのリスク管理とは?
Ⅱ.ALMの概念とリスク管理の変遷(1) 初期のALM
(2) 現状・発展段階のALM
(3) 統合リスクマネジメント
Ⅲ.リスク管理手法
(1) 市場リスク管理
1)『現在価値』の概念導入および『金利感応度』の計測には
2)金利リスク計測のための尺度について
3)VARの導入・・市場リスクを包括的に把握する手段として
ⅰ)VARの計測方法
<1> ヒストリカル分析アプローチ
<2> 分散・共分散アプローチ
<3> モンテカルロ・シュミレーション・アプローチ
ⅱ)VARアプローチの長所・短所
(2) 信用リスク管理
<附則>
Ⅰ.リスク管理(VAR)の役割について
(1) VARモデルやその計算結果が果たす役割
(2) 監督当局による資本規制における役割
(3) 業績評価の点における役割
Ⅱ.VARモデルを導入するための,リスク管理のより広い枠組みについて
Ⅲ.リスク管理の限界
|
Ⅰ.金融機関・一般事業法人にとってのリスク管理とは?
|
最近、新聞・雑誌・マスコミを通して、『リスク』という文字を目にすることが多くなってきました。
記憶に新しいところでは、ベアリング証券、住友商事、ヤクルト、米国のヘッジファンドLTCM等々、マスコミを賑わしリスクを再認識させるような事件が報道されています。『リスク管理』の重要性・必要性が叫ばれるようになった今日このごろです。
しかし、リスク管理の必要性が叫ばれても、巨額の損失事件と絡めて報道・解説されることが多いためか、リスクは損失の温床であって、リスク管理の目的とはリスクを早期に発見し、排除することであるかのような印象がもたれています。
果たしてリスクは金融機関・一般事業法人にとって『排除するべき』ものなのでしょうか。
一般的に、『リスクの大きいものほどリターンが大きい』ことを理解している人々が多いとおもわれます。現実の金融資産や、最近話題になっている投信の商品解説等で知られるように、リスクの大きいものほど期待される利回りは大きいといえます。リスクの大きい分だけ上乗せされる期待収益をリスクプレミアムと言います。ここで、例えばリスクをことごとくヘッジし、リスクを無くしてしてしまえば、リスクプレミアムは皆無となって、収益は低水準で安定することになります。果たしてそれで良いのでしょうか。
バブルの当時、ネコも杓子も不動産・株式等の投資商品に資金をつぎ込み、バブルが弾けて以降、極端な反動からかリスクあるものに投資することに躊躇する風潮が出来上がってしまいました。
本当の反省としては、①会計制度のあり方(時価会計の発想)、②およびその投資商品ごとの本源的リスクを考察することがなかったこと(市場リスクが存在すこと)、③横並び意識からか、自己責任主義の芽生えることなく責任の所在が不明確なまま10年近くが過ぎてしまったことがあげられます。
しかし、2000年を迎える今になって、金融ビックバン・国際会計基準導入に始まるグローバル・スタンダードの大きな波が目の前に押し寄せています。このような時、リスクについては知らないでは済まされません。この大きな波に乗ることが、または乗り越えることが大変重要になってきています。
そこで、発想を転換して、リスクをなくすことを考えるのではなくリスクを知って上手く付き合うことを考えてみてはいかがでしょうか。
|
【 金融機関・法人の金融収支にとってリスクは収益の源泉である。】
JPモルガン ウェザーストーン会長の言葉に、
「The Business of Banking is Risk Management」「銀行業務とはリスクマネジメントそのものである」というのがあります。
|
金融の自由化による利鞘の縮小は、単に資産・負債を膨張させることによって利益を増大させる従来の経営理念を終焉させることになりました。特に、金融機関は量的拡大による収益追求から、適切なリスク・テイクによって収益・リスクプレミアムを獲得する行動を余儀なくされています。
金融自由化の進展の中で、先進的な米国及び欧米の銀行は、1980年代過大な損失をともないながらも、試行錯誤の中リスク管理手法を確立し、BIS規制の考え方を導入しクリアーしてきました。彼らにとっては、体力(資本)に見合ったリスクテイクは当然であって、取ったリスク量(計算された)に対して、いかに収益を極大化するかが命題とされています。
一方、わが国の場合、徐々にではありますが金利自由化が浸透し、あらゆる金融資産について金利感応度が高まっています。顧客ニーズは多様化しデリバティブ内包型商品の取扱いも相当量にのぼっています。また、短期的な収益獲得や対顧客取引としてトレーディング目的でのデリバティブ取引も行われるようになりました。但し、最近のように邦銀の評価機関のレーティングが下がってくると、デリバティブ商品の取り扱いにもジャパンプレミアムがつけられ、金融機関による格差が歴然としてくるようになってきました。このような状況下で拡大的リスクテイクを続けることは困難となっています。一時的に縮小均衡の方向が継続される状況は、日本に対する信用が回復されるまで続くものと考えられます。
従来、ALM(債権・債務の統括管理)の目的は、運用・調達のギャップを縮小し、金利変動によるリスクを抑制することと理解されてきました。現在、『ALM』に求められるのは、金利・為替・株(市場リスク)予測等に基づいた、機動的且つ戦略的なリスクを負担し、収益の増大を図ることと変化してきました。
一方、デリバティブ取引手法の確立は、このようなALMニーズに対して便利な手段を提供した反面、大きなリスクを内包化することになりました。
リスクを共存させながらも、相反する収益を追求していくなかで、リスクの所在、特性、量を正確に把握し、体力に合わせて適確にマネジメントすることが強く求められています。その意味で、リスク管理は「管理」という、さめた冷ややかな語感とは違い、ALMそのものであるともいえます。
このようなリスク管理の体制、管理技術は最近では情報開示の項目の一つとなっており、格付機関による格付や市場での評価を通じて取引レート等に影響を及ぼすことになってきました。
(1)初期のALM
商品勘定、投資勘定、あるいは全体的なバランス・シートといったフィナンシャル・ポートフォリオは、 クレジット・リスク、事務リスク、法律上のリスク、市場変動リスクなど様々なタイプのリスクにさらされています。これらのリスクは常に存在するため、リスクの克服は、資本市場が誕生した時から金融機関
が取り組まなければならない課題でした。金融自由化以前の金融機関にとって、ALMとは、資産と負債の静的なバランスを考慮しつつ主として決算上の期間収益を最大化することだと理解されてきました。したがって、リスク管理の目的も資産・負債の過大なマチュリティーギャップ(期間ミスマッチ)を抑制することが中心と考えられていました。以下に整理しておりますが、帳簿上で把握できる範囲に限られた『預金・貸出・債券』がその対象とされてきました。金利で見た場合には、その持ち高の偏りを把握し、そのリスクを極小化することを目的に利用される程度でした。
|
初期のALM
|
|
ⅰ)金融環境
・・金融自由化以前
ⅱ)金融機関の保有する資産債の状況
・・伝統的金融商品中心金融商品全般的な金利感応度は低い
ⅲ)ALM対象商品
・・預金・貸出・債券
ⅳ)管理項目
・・期間損益(決算)
ⅴ)ALMの目的
・・運用・調達構造を把握し、課題のギャップを抑制すること
ⅵ)リスク管理手法
・・マチュリティー・ラダー法
|
(2)現状・発展段階のALM
金融自由化が進み、金融商品の金利感応度が高まるなかで、ALMの目的も金利予測に基づくより動的な収益追求に変化してきました。従来は抑制することに努めていたはずの期間ミスマッチが収益源として再認識されるようになりました。コントロールする手段として金利スワップをはじめとするデリバティブ取引が拡大したこともその背景にあります。
元々、オプションを始めとするデリバティブ理論は、その市場リスクを統計学の手法を使って把握し、その法則性を見つけ出し科学的に予測の域にまで持って行くことから始まっています。
デリバティブ取引の対象とするリスクは、市場リスクや信用リスクであり、この点伝統的な金融商品と異なるものではありません。
しかし、(1)オフバランス性、(2)レバレッジ効果、(3)仕組みの複雑さ等において、従来の商品にはない重要な特徴をもっています。このような特徴がリスクとして顕在化した事例は、枚挙にいとまないと言えます。
そして今は、リスク管理の対象として、デリバティブ取引がクローズアップされ、オンバランスとオフバランスを総合した、いわゆるオン・オフ一体管理が求められることになりました。
また、将来にわたる期間ミスマッチの効果を把握するため、期間損益のみならず評価損益をも管理項目として取り込む必要が生まれました。代表的な資産・負債である貸出金や預金には元々評価損益という概念がありません。しかし、ヘッジのために使われる金利スワップ等では現在価値(NPV)ベースでの評価損益の把握が一般的になっています。
オン・オフ一体管理が進む過程で、全ての資産・負債を現在価値によって評価しようとすることは当然の流れだったと言えます。
しかし、日本において、オンバランスの取引を現在価値によって時価評価する手法が普及しているとは必ずしも言えません。国際会計基準が標榜され、グローバルスタンダードが普及することになった現在においては、現在価値による評価損益の考え方にも多くの問題がありますが(日本で受け入れられるには)、リスク管理上は無くてはならない基本的な概念として受け入れなければなりません。
|
現状~発展段階のALM
|
|
ⅰ)金融環境
・・金融自由化以降
ⅱ)金融機関の保有する資産・負債の状況
・・金融商品全般的な金利感応度の高まりとデリバティブ取引の比重増大
ⅲ)ALM対象商品
・・預金・貸出・債券+デリバティブ取引
ⅳ)管理項目
・・期間損益(決算)、評価損益
ⅴ)ALMの目的
・・ある程度の金利予測を行い、収益の増大を図る
ⅵ)リスク管理手法
・・ベーシス・ポイント・バリュウ(BPV)、グリッド・ポイント・センシティビティー(GBS)
|
(3)統合リスクマネジメント
金融機関の抱えるリスクが複雑化しデリバティブ取引が飛躍的に拡大するなかで、国際決済銀行(BIS)のバーゼル銀行監督委員会は、信用リスク規制に加え、市場リスクをも規制の対象に加えました。
BIS規制の基本的な考え方は、金融機関のとるリスクを自己資本でサポートするということです。
リスクが顕在化した場合、最終的に損失を担保するのは自己資本以外にありません。つまり、経営体力(自己資本の範囲)に見合ったリスクしかとれないことになります。
それでは、リスクプレミアムによる収益をより多く獲得するには、どのような方法が考えられるでしょうか。この場合の答えは、このリスクプレミアムを把握しながらも、リターンとのバランスを考慮しつつ、資本の最適配分をどのように行えば良いかを考えることになります。このようなキャピタル・アロケーションを行うためには、配分の目安として「どの程度の損失の可能性?リスク」があるかを把握することが必要となります。このリスクを計測するための手法がバリュー・アット・リスク(VAR=潜在的最大損失額)と言えます。
VARは、BIS2次市場リスク規制において、内部モデルとして取り上げられたことから一躍注目を集めたものです。
|
統合リスクマネジメント
|
|
ⅰ)金融環境
・・BISの第2次規制時代
ⅱ)金融機関の保有する資産・負債の状況
・・デリバティブ複合型取引の増大、機動的なリスクテイク
ⅲ)ALM対象商品
・・預金・貸出・債券・デリバティブ取引・為替・株式
ⅳ)管理項目
・・期間損益(決算)・評価損益・自己資本
ⅴ)ALMの目的
・・リスクを統計的に計測し、自己資本の最適配分を行う
ⅵ)リスク管理手法
・・バリュー・アット・リスク(VAR)・レイロック(RAROC)・信用リスクの計量化
|
孫子の兵法に「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」という有名な言葉・格言があります。当然、リスク管理のあり方を考える場合、「敵を知る」以上に「己を正確に知る」ことが重要になります。
一般的にリスクとは、『今もっている資産・負債それぞれに対して、将来は不確実であるため、収益(損失)がどの程度予想されるかの度合』と定義されます。その不確実性の要因として最も重要なのは、市場リスクと信用リスクです。以下、代表的な市場リスクとしての金利リスクと信用リスクについて、その管理手法を概説します。
(1) 市場リスク管理
1)『現在価値』の概念導入および『金利感応度』の計測には
|
ⅰ)
|
資産および負債のポートフォリオを時価で評価(Mark to Market)します。
まず、保有する資産・負債の現在価値はいくらなのかを知ることからはじめます。
損益を認識するための基準点(額)として、現在価値を測定します。金融機関全体のリスクを評価するためには、まず預金・貸出を含めた全ての資産・負債について、統一的な方法で現在価値を測定する必要があります。
|
|
|
|
|
ⅱ)
|
現在価値の変動率(感応度)を計量化
市場において金利(イールドカーブ)が、一定量変化した場合に、現在価値がどのくらい変化するかを、一定の尺度によって計測します。
|
2)金利リスク計測のための尺度について
我々が長さを計る場合につかう尺度の「メートル」は、元来、地球の南北の円周の4千万分の1と定められた。同じように、我々が金利リスクを計るには何らかの定義による尺度が必要である。
|
尺度1 ベーシス・ポイント・バリュー(BPV)
金利が一定の幅、たとえば0.1)%変化した場合に、現在価値がいくら変化するかを示すBPVは、「デルタ」とも言われ金利リスクの代表的尺度。
尺度2 グリッド・ポイント・センシティビティー(GPS)
BPVは金利が全ての期間に亙って同時に、同じ幅だけ変化した場合の尺度。しかし、短期金利と長期金利が都合よく同じ様に変化してくれるとは限らない。イールド・カーブが平行に変化しない場合におけるリスク量を適確に捉えるために、考え出されたのが「期間別デルタ」とも言われるGPSである。
|
3)VARの導入・・市場リスクを包括的に把握する手段として
|
「敵を知り、己を知れば、VARの算出が可能となる!」
|
ここでは、フィナンシャル・ポートフォリオの市場変動リスクの測定及び管理を行うためのVARアプローチと、このアプローチを資本の配分計画、パフォーマンスや金融商品の評価にいかに応用するか、そして、VARモデルを導入するべき対象となるリスクの構造について概説します。
市場変動リスクとは、ポートフォリオの将来価値の下落や上昇といったばらつきを測る物差しです。 リスクは基本的かつ同時発生的な2つの原因、つまり事象発生の不確実性と、そのリスクの基本的な
発生源に対するエクスポージャー、あるいは、そのリスクの影響を受けやすいことから生まれます。基本的な金融理論においては、投資収益は正規分布を描き、分散あるいは標準偏差といった単独の統計量だけでリスクを計測できる世界を前提としています。
しかしオプション市場の発達、特に、バリアー型やバイナリー型のようなエキゾチックな金融派生商品のおかげで、ポートフォリオの投資収益の分布が非対象になり、その結果、分散がポートフォリオの特徴を
示すには不完全なものとなってしまいました。さらにリスクの基本的な発生源が、正規分布や対数正規分布 や平方根確率プロセスといった単純な数学モデルに従わずに、むしろこういったモデルから推測される分布より両端がふくらみ度数分布の幅が広い動きを示すことが、徐々に明らかになってきました。つまり、リスクを最も端的に表しているものは、リスクの基本的な発生源の確率論的な性質を最もよく捉えており、かつ、その性質を、ポートフォリオの実際の特徴を通して投資収益の連続的な分布、あるいは平均
、分散、歪度、尖度などを計算できるヒストグラム(度数分布図)により説明することが可能で、しかも そこから与えられた損失の可能性を特定できるもの、といえます。
これらの要件を満たすのが、VARアプローチなのです。VARは、「特定の投資期間に、あらかじめ設定された目標確率レベルで発生するであろう、ポートフ
ォリオの金額ベースでの最大損失」と定義することができます。例えば、その期間の目標確率を95%に 設定して、ポートフォリオが翌日までに100ドル以上の損失はないと考えられる場合、1日のVARは100ドルとなります。
VARは、ポートフォリオの将来価値や投資収益の確率分布を明白にあるいは暗黙のうちに描くこと で決定します。また、それから、分布の端にある不利な損失が発生する確率を計算することもできます。
この概念は複雑な問題を1つの数字にまとめるため、単純であり、かつ簡単に理解することが可能で、 非常に興味をそそられるものです。
ⅰ)VARの計測方法
ポジションあるいはポートフォリオのVARの測定には、ヒストリカル分析、分散・共分散分析、モンテ・カルロ・シミュレーションという 3通りの方法があります。どの方法も、過去のデータを、将来を推測する手がかりとしており、将来価値の変動モデルを作成するために個々のリスク要因に対する過去の価格変動を利用します。
<1>ヒストリカル分析アプローチ
VARを計算する上で最も直接的な方法がヒストリカル・シミュレーションです。またイングランド銀行の報告書でもこの方法を採用しております。ヒストリック・シミュレーション方式の長所としては、非常に普遍的であるという点があげられます。この方法はどんな金融商品や市場変動リスクのタイプにも応用できますし、特に、ガンマやベガと
いったオプション特有のリスク、また、ベーシスや多変量相関リスク効果などを正確に把握することができます。
ヒストリカル・シミュレーションの場合は個々の金融商品を再評価する際に、ディスカウント・キャッシュ・フロ―・モデル、分析的あるいは数学的なオプション・モデル、モンテ・カルロ・ シミュレーションあるいは直接市場で公示されている相場といった、その金融商品や市場の慣例に応じた、正確かつ市場に認められている価格モデルを利用することもできるのです。
統計上ではヒストリカル・シミュレーションによるVARは、一連のヒストリカルな市場価格データを与えられれば、決められた投資期間内におけるポートフォリオ価値の分布から引き出すことができます。ポートフォリオ価値の分布は、市場価格の時系列データを使ってポートフォリを何度も再評価して計算します。そしてポートフォリオの全投資収益は、1日、10日あるいは1ヶ月といった投資期間として
決められたある日時と次の日時との間に発生した市場価値の変動として計測されます。
いったんNPVの価格変動の時系列を計算してしまえば、損失の確率の決定には、様々な テクニックを使うことができます。
まず、ポートフォリオのNPVの変動の標準偏差を計算します。ここから累積正規分布関数を使ってどのような信頼区間のVARの推定値でも出せます。あるいは正規分布化された結果を利用するかわりに、確率的に考えられる損失を実際の
NPVの日々の変動から得た経験的な分布から直接計算することもできます。これは、ヒストリカル・シミュレーションの計算結果を、推定値の計算のために統計的に等価なものに変換せず、そのままの形で用いる唯一のケースです。この方法はとりわけ、投資収益の分布が正規分布で想定されているような理想的な形となっておらず、市場が示す分布曲線の尖度が高いと考える場合、非常に役立ちます。
<2>分散・共分散アプローチ
分散・共分散アプローチでは間接的なパラメトリック・アプローチを利用して、個々の市場変動リスク要因についての将来価格の 変動の分布とポ―トフォリオ価値の分布を推定します。この手法で最もよく知られているのは、 多分J.P.モルガンのリスクメトリクスでしょう。これは一般に広く利用されておりますが、実は、J.P.モルガン自身が利用している方法はこれとは大きく異なるのです。
分散・共分散アプローチでは、為替の直物相場、短期金利、金利先物価格、スワップ金利、債券価格といった簡単な金融商品についてボラティリティや相関計数を計算します。次に、その結果得られた相関計数行列をポートフォリオと同じ性質をもつ単純化したスポット・レートやゼロ・ク―ポンに当てはめます。この方法は、過去の市場データの中には、5年物ゼロ・クーポンのスワップ・キャッシュ・フローといった個々の主要なリスク要因のボラティリティや分散、並びに個々のリスク要因とその他のリスク要因一つ一つとの間の相関が、目に見えない形で存在しているという基本的な認識に裏打ちされています。
こういった主たる分散並びに共分散の行列が得られれば、行列代数を使って基準となるポジションと等価のものをネットVARの計算結果へと変換するのは容易なことです。
<3>モンテカルロ・シュミュレーション・アプローチ
最後に、モンテ・カルロ・シミュレーション・アプローチがあります。この方法では、一連の現在価値の変動を計算する際に過去の価格を使わずに、ヒストリカルな統計上の価格の分散や共分散を使って、価格間隔を通る標本経路を導出します。これで結果として得られた現在価値の変化を、標準的な統計手法を利用して分析することができるのです。
ⅱ)VARアプローチの長所・短所
以上の 3種類のアプローチについて、「どの方法を使うべきなのか」という基本的な質問は依然として残っています。この質問に答えるためには、それぞれの方法の長所と短所を、とりわけモデル化しようとする
特定のビジネス環境という観点から検討する必要があります。
どの方法を用いるか決定する際には、 1日単位のデータの数と利用する投資期間及び信頼区間を度外視して考えることが必要です。何故ならば、こういったデータはどのモデルにも適用できる変数であり、しかもモデル自体の中核的な特徴ではないからです。
基本的な違いは、分散・共分散アプローチでは、個々の市場変動リスク要因による過去の価格変動が左右対称で釣り鐘型の正規分布に合致すると仮定している点にあります。また分散・共分散アプローチは、過去の価格変動が描く個別の分布の平均値がゼロと仮定する、つまり価値には何のトレンドも存在しないと仮定します。こういった仮定は分散・共分散方式を用いて価格変動の分布を出したり、個々の市場変動リスク要因の分散をポートフォリオの分散に統合する際に絶対に欠かせないものです。
ヒストリカル分析アプローチは、分布の形状についての仮定をいっさい置かず、ポートフォリオ価値の 変動の経験的な分布から直接VARを引き出します。つまり曲線は左右対称で釣り鐘型である必要はなく、
また平均値もゼロである必要はないのです。
モンテ・カルロ・アプローチでも、価格変動が正規分布を描くとは仮定していません。モンテ・カルロ方式の主たる違いは、価格変動経路が前向きかつランダムだということです。モデルの中には、ヒストリカル・
ボラティリティよりもむしろ市場のインプライド・ボラティリティを用いるものもあります。何故ならば、インプライド・ボラティリティは将来の市場参加者の見方を織り込んでいるからです。しかしインプライド・ボラティリティを用いる場合、どのように相関係数を計算するのでしょうか。推定する段階で複雑な誤差が紛れ込むかもしれませんし、ヒストリカルな相関分析を利用した場合、
理論上の欠点が増幅されるかもしれません。
異なるモデルの評価を行う際の基準がたくさんある中で最も知りたいことは、現実を最もよく 表しているモデルはどれかということです。一口でいえば、正規分布を仮定する場合は、すべてのオプションやオプション内蔵商品は除外されます。こういった金融商品の価格変化の分布を描くと、著しく歪んでおり、正規分布の形態をとりません。といいますのも、これらの数値は基礎となる市場変動リスク要因の一次関数ではないからです。そしてその結果、分散・共分散方式では、テーラー展開による近似の第一項であるデルタしか分析できません。セータ、ベガ、ガンマとして幅広く知られているその他の展開パラメーターである第二項は当てはめられないのです。
リスクメトリクスの開発者が、オプション・リスクにモンテ・カルロシミュレーションを用いることでこの問題を多少なりとも解決しようと試みています。しかしながら、その結果、オプションに対するVARとポートフォリオのその他の金融商品に対するVARという2つのVARがでてきてしまった場合、計算結果は
実質的には両者を折衷したものになります。
こういった現象はオプションに影響を与えますが、その一方で、正規分布を仮定することも、一般的に疑わしいということも指摘したいと思います。大方の金融製品の収益分布は正規分布曲線よりも両端が膨らみ真ん中が細いということは、今や広く知られていることです。
ヒストリカル・シミュレーションで重要なのは「定常性」を仮定すること、つまり毎日の価格変動の分布が比較的一定であり、またうまく当てはまらない場合には、データをトレンドに合わせて修正できるということです。ヒストリカル・シミュレーションもいくつかの長所を備えています。
|
・簡単に理解できる。
・利用方法が簡単。
・リスクの分解というよりも詳細な再評価を組み込んでいるため、新しい仕組みを正確に取り込むことができる。
・柔軟性に富む。
|
モンテカルロ・シミュレーションは、分散・共分散分析と同様に、ポートフォリオに含まれる金融商品の相関計数とボラティリティの膨大な行列が必要となります。統計的な精度を保つために、このシミュレーションは膨大な数の経路を作成する必要があります。これがこの方式の一番の欠点で、コンピュータ化による効率向上が必要となります。
つまり、ビジネス上のほとんどのケースでは、簡単に使え、しかもより正確な答を出すことができるのはヒストリック・シミュレーションのようです。つまるところ、各企業・各金融機関の組織に、どの方法が役立つのかということです。VARモデルの評価を行う正式な統計プログラムを導入する必要があります。このようなモデルを使えば、現実の結果を正規分布化することにより、現実のポートフォリオ価値の変動と、予測したVARとを比較することができます。どの様な有意の期間についても、現在価値の変動に対する標準偏差の比率の分布は、正規分布曲線に合致し、標準化させると平均が0で標準偏差が1となります。もし標準偏差が1以上となった場合はリスクを過小評価していることになり、また1以下ならば過大評価していることになります。そして1単位との不一致が精度を測る目安を与えてくれます。不一致が大きくなりすぎると、モデルに含まれる特定の市場変動リスク要因の観点からモデルを再評価したり、他のモデルを使ってみる必要があります。
現実の結果とリスク管理担当者が算定したVARの推定値を比較する際にこのような枠組みを使用すれば、その結果得られた客観的な目安によって、より精度の高いリスク予測が可能となります。
(2)信用リスク管理
信用リスク管理においては、与信先の信用度に応じた倒産確率、回収率等の計測が必要です。
中小一般貸出先の信用力の測定については、データベース整備等の問題もあり、統計的に信頼できるリスク量の計測は困難です。しかし、先進各行では自行データ等から独自のデータベースを構築し、信用リスクの測定を実施しており、統計的に計測されたリスクに見合ったレート決定を行っている。また、有価証券投資については、格付機関が格付に応じたデフォルト率等のデータを公開しており、信用リスクを評価することが可能です。
デリバティブ取引については、あくまで想定上の元本があるのみで、貸出や有価証券投資のように元本リスクがある訳ではありません。したがって、取引相手が倒産した場合に実現されない「取引の勝ち分」である、「現在価値のプラス部分」を信用リスクとして把握します。
統計的に計測された信用リスクは、統計的に使用される必要があります。サイコロを6万回振れば、1の出る回数はほぼ1万回だが、6回振っても必ず1が1回出るとは限りません。したがって、数多くの与信先をポートフォリオ的に集約することによって、統計的なデータを利用した管理が可能となります。
(1) VARモデルやその計算結果が果たす役割
リスク管理には、はっきりとした役割が存在します。
VARの最も基本的な利用法は、市場変動リスクのエクスポージャーを数量的にとらえることと、このようなエクスポージャーの限度を設定することです。VARのテクニックとしての長所は、その組織が保有するリスクの統合的な俯瞰図を検討できる点で、しかも、アセットクラス間やアセットクラス内のすべてのタイプのリスクや相関などを検討できる点です。これは、ベガ・エクスポージャーなどの個々のリスクを理解しない、あるいは検討する時間がない企業の上席役員にとっては、たいへんありがたいことであり、VARの簡単な計算結果だけに注意を向けていればよいのです。
グループ企業、部署、デスク、個別のトレーダー等の階層構造を利用して、VARモデルに基づいた取引限度を設定することも出来ます。取引限度は、伝統的に、実際のエクスポージャー
とは無関係に想定元本等を基準に設定されるか、あるいはボラティリティや相関計数とは無関係に個々の市場変動リスク要因に基づいて決定されてきました。VARの考え方はこういった弱点を一掃する一方で、実際のリスクを抑制させることができます。リスクの過度な集中がおこらないようにするために、通貨ポートフォリオ毎に、デルタ、ベガ、ガンマ等の個別のリスクのガイドラインを設定することができます。
(2)監督当局による資本規制における役割
最近欧州では、法定必要最低資本金額の策定にVARを使うことができます。これはアムステルダム合意によるものですが、まもなくもっと広い範囲で行われるようになりました。国際決済銀行(BIS)は、1993年に、方法論に関する市場の基準について合意を形成するよう勧告を出しました。それ以降、規制当局と実務担当者の双方、特に国際財務協会やISDA/LIBAのプロジェクト・チームが、銀行モデルのための質的・数量的な標準基準作成のために、膨大な作業を行なってきました。
BISによる法定必要最低資本金額の修正版は、草稿の形で既に発表されており、1998年1月の施行に向けて今年 3月までに最終作業を終える予定です。BISでは現在、リスク管理の手段としてVARを強力に推奨しており、またこれは各国規制当局の認可を必要とするものですが、法定必要最低資本金額の算定の手段としても推奨しています。
VARモデルを利用するに際して、各国規制当局はVAR使用の許可の前提として以下の基準を遵守するよう主張しております。
|
・VARを毎日計算すること。
・信頼期間99%で使用すること。
・最低保有期間は10日間とすること。
・ヒストリカルの観察期間は最低でも1年間とすること。
・一連のデータは四半期ごとに更新すること。
・非線形のオプション・リスクも含めること。
・アセットクラス間やアセットクラス内の相関を認めること。
|
残念なことに、規制当局では依然としてVARの基準を、10日間で99%の信頼区間としており、これに 3を掛けて必要な資本金額を求めるよう指導しております。しかしながら、それでもこのような動きは、VARをリスク管理の中心として確立し、また科学としてVARにより多くの人々に関心を持ってもらうためには、たいへん重要な第一歩であろうと思います。
各国規制当局がVARを採用し始めたことのメリットは、潜在的にはたいへん大きなものです。現状、市場変動リスク、企業が直面している潜在的な損失、そのリスクを許容するために必要とされる資本金額との間にほとんど関連がないからです。VAR理論の導入により、ポートフォリオを支えるために必要な資本金額を、ポートフォリオに内在するリスクの量にきちんと見合うレベルにすることができ、またそれによってリスクや資本、投資収益などに関して首尾一貫した見方をとることが出来るようになるでしょう。さらに、VAR理論を使えば、リスク相互間の相関を計算に含めることができるので、相関関係のあるポジションに対する資本金所要額も大幅に減らすことができるでしょう。
(3)業績評価の点における果たすべき役割
報酬が純粋に投資収益に基づいて決定される場合を考えてみましょう。パフォーマンスの測定基準、取引手法、取引動機などすべての要素がVARの中に含まれるため、特定の取引が持つ潜在的な価格上昇の可能性に、ディーラーの関心が集中する傾向が強まり、この価格上昇の可能性と引き替えに取引されているリスクの量には注意が集まらなくなるでしょう。ビジネス・パフォーマンスと各個人のパフォーマンスの測定基準は市場変動リスク、信用リ
スクの双方を反映するように、パフォーマンスの到達に利用された資源の量に合わせて修正を行う必要があります。この方法は一般に、リスク修正パフォーマンス基準
(Risk Adjusted Performance Measurement、RAPM)と呼ばれ、VARに対する収益、シャープ・レシオ、リスク・キャピタルに対する収益なども含みます。さらに、共通の方法や、共通の保有期間・信頼区間等のパラメーターが合意されれば、異なる銀行のパフォーマ
ンスや証券会社のリスクに対する考え方も比較することが出来るでしょう。
要するに、VARはリスク測定やリスク管理に関するすべての問題の答にはならないという ことです。最近の報道された重大な金融破綻の多くは、VAR測定システムでも回避できなかったであろう過失が原因となっています。VARシステムは、信用リスク、事務リスク、流動性リスク、法律上のリスクなどに対する見通しを補足することと、分布の末端におけるストレステスト分析を含むよう拡大することが必要です。しかしながら、これは市場変動リスク、資本配分の適格性、パフォーマンス評価の分析に向けての重要な第一歩であり、リスク管理の将来の発展において重要な役割を果たすことはまちがいありません。
|
Ⅱ.VARモデルを導入するための、リスク管理のより広い枠組みについて
|
企業の役員が効果的にリスクの監督を行うことは、健全なリスク管理プロセスにおいてはたいへん重要なことです。取締役会や上席役員の一人一人がその責任を自覚し、リスクの監督・管理において自らの責務を適切に全うしなければなりません。
取締役会は、企業が負っているリスクの性質や水準を理解する最終的な責任があります。取締役会は、自社が負うリスクを左右する、あるいは影響を与えるような広範な事業戦略や重要な方針について承認を与えなければなりません。またリスクという観点から自社の総合的な目標を検討し、リスクに対するエクスポージャ―の許容水準を明確に規定しなければなりません。
上席役員は、長期・短期どちらの基準でもリスク管理ができるよう、自社が適切な指針と手続を確立するよう監督すると共に、リスクの監督・管理の権限と責任に関して明確な方針を決定しておく責任があります。また経営陣は、以下の機能が確実に維持されるようにしなければなりません。
|
1.
|
ポジション評価のための適切な基準と方針を、定期的に協議・検討することが必要がです。健全なリスク管理は、バランス・シートの評価がオープンな状態で正しく行われてはじめて効果があります。これはオプションの戦略的ディーリングには特にあてはまることです。
|
|
|
|
|
2.
|
リスクを測定する適切なシステムと基準を導入しなければなりません。このためには まず、上席役員と取締役会の両方に直接報告を行う、独立したリスク管理担当部署を設置します。また、この部署は自社のリスク管理システムの設計・実行の責任者とな
ります。
|
|
|
|
|
3.
|
包括的なリスクの報告や経営層が検討するための手続きを、しっかりと確立する必要があります。上席役員に提出されるリスク報告書には、VARモデルの結果を使った
全体的な情報と共に、市況などの重要なリスク変動要因の変化に対する自社のセンシティビティを上席役員が評価するために十分な情報など、総合的な情報を盛り込むことが必要です。このような分析にはとりわけ、ストレステスト分析などの形で、分布曲線の末端に位置したポートフォリオの動きに関する報告が含まれなければなりません。またこういった分析は、最低でも毎日行う必要があります。
|
|
|
|
|
4.
|
日中の取引時間帯におけるリスクに対するエクスポージャーも監視することにより、日中の取引時間帯に発生する可能性がある重大な結果を経営陣が知ることができて、必要に応じて、適当な時期に、適当な手段を講じることができるようにしなければなりません。
|
|
|
|
|
5.
|
適切な限度を設定する仕組みと、許可された商品群を導入する必要があります。限度設定の仕組みは、より詳細なレベルでの大まかな限度とともに、VARモデルに基づいて決定しなければなりません。また資本配分や予算と整合性を持たせる必要があります。これは非常に重要なポイントです。リスクの限度、予算、資本配分はすべて相互に関係があり、ほとんど一つの問題として考えなければなりません。この関係を考える最も良い方法は、予算化された収益目標を設定して、次に、必要最低収益率を設定することによって、資本配分を決定する方法です。これは、年間収益目標を時間の平方根で除して日々のVARに変換することによって完結します。
|
|
|
|
|
6.
|
そして最後に、リスク・モデルがどんなに優れていても、まちがったポジションを モデル化しているか、使うデ―タがまちがっている場合にはリスクモデルがどんなに優れていても内部管理モデルは有効ではなくなります。社内管理システムは、リスク測定 システムの統合性が常に保たれるようにしなければなりません。これは非常に大きなテーマです。しかしながら、有効なシステムであるためには、内部のリスク管理システムは、特に、財務管理部門、事務管理部門、会計監
査部門を含めた組織全体を網羅しなければなりませんし、十分な資源が配分されなけ ればなりませんし、最も上席の役員達の最大限の援助がなければなりません。
|
VARモデルをこういった枠組みの中で運用すれば、経営者はリスクの規模、リスクのボラ ティリティ、リスクが利益と損失に対して潜在的に与える影響について、十分に理解できる立場に立つことができます。VARは、リスク管理における我々のすべての問題の解決にはなりません。しかしながら、VARは大きな前進であり、以前は解決されないままで
あった問題点の多くに解答を与えています。
デリバティブを駆使した金融の革新は、未だ衰えることなく進歩しています。これを追っかけるように、リスク管理手法もさらに高度化されることでしょう。しかし、高度な統計学、数学の理論を応用した手法であっても、結局は『過去のデータの延長線上に将来の変化を捉えようとする自然科学的なアプローチ』であることに変わりはありません。相場にしろ、経済にしろその行く末は『神のみぞ知る』世界だからです。将来を透視できる可能性はあっても、自然科学の追求する『完全性』にはほど遠いものとなります。ましてやその対象が社会現象だったらなおさらです。
市場がいかに理論的になろうとも、最終的に判断を下し行動するのが人間である以上、リスク管理の対象は社会科学の範疇にすぎません。この意味で、最新のリスク管理手法といえども決して万能ではなく、「相場は水物」的な限界がついて回ります。最近のヘッジファンド『LTCM』の破綻に見られるように、高度の金融技術を使いこなしている彼らでさえ、判断を間違えてしまいます。その後の反省として、FRBの指摘もあったように定期的なストレス・シミュレーションや精度検証を常に心がけることが肝心となります。しかし、現代の事業法人・金融機関の持つポートフォリオは、1つの数字で把握できるほど単純ではありません。
結局は、コンピューターによるリスク管理の発達とその応用・導入を考える一方、その限界を知る人間との調和を考えるべきでしょう。あくまでもコンピューターは人に役立つ道具に過ぎないのですから。そして、時代の流れを熟知したリスク感覚を備えた人材をどれほど養成できるかに、事業法人・金融機関の発展と展望がかかっています。
|