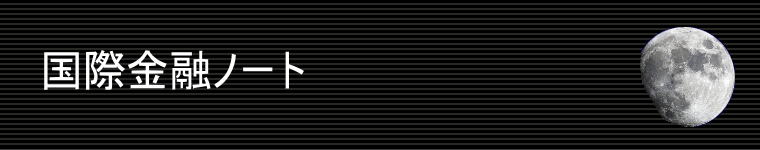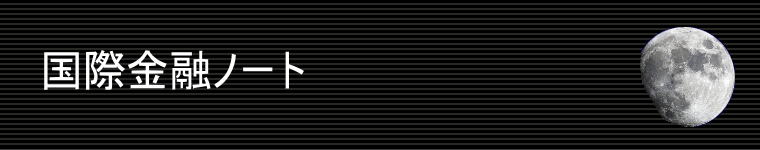国際金利講座
金利相場の基本 第一部 荒巻 昌宏
|
[1] 金利とは
|
|
(1) 概説
|
|
(2) 利子学説
|
|
1) 制欲説・禁欲説
2) 時差説
3) 流動性選好説
4) 利潤説
5) 需給説
|
|
[2] 金利の計算方法
|
|
(1) 日歩と年利
(2) 単利と複利
(3) 片落としと両端入れの計算
(4) 割引率について
|
|
[3] 債券の利回り
|
|
(1) 債券の利回りについて
|
|
(2) 利回りのいろいろ
|
|
1) 直接利回り
2) 最終利回り
|
|
ア) 最終利回りの考え方
イ) 利付債の最終利回り
ウ) 償還まで一年未満までの割引債券の最終利回り
エ) 期間一年以上の割引債券(割引国債)の利回り計算
|
|
3) 所有期間利回り
4)複利利回り(複利)
|
|
[4] 金利の決まりかた(需給説に従って)
|
|
(1) 通貨市場
|
|
1) 通貨の需要
|
|
2) 通貨の供給
|
|
(2) 財市場
|
|
[5] 金利水準
|
|
[6] 金利の種類と分類
|
|
(1) 規制金利と自由金利・・・・・・ 概説と金融商品
|
|
(2) 分類
|
|
(3) 金利体系について
|
|
1) 金利間の格差について
|
|
ア) 資金の流動性
|
|
イ) 確実性(相手のリスク)
|
|
ウ) 資金相互間の関連
|
|
2) 金融システムとの関連
|
|
(4) 金利体系の分類
|
|
1) 公定歩合
2) 市場金利
3) 預金金利
4) 貸出金利
5) LIBORとTIBOR
6) 債券(公社債)金利
|
|
7) デリバティブ商品の金利
|
|
|
|
[7]金利相場のリスク
|
|
(1) リスクとは
|
|
(2) リスクの種類
|
|
1) 市場リスク(マーケット・リスク)
|
|
2) 信用リスク
|
|
3) 流動性リスク
|
|
4) 決済リスク
|
|
5) 法的リスク(リーガル・リスク)
|
|
6) 会計・税務リスク
|
|
7) オペレーション・リスク
|
|
8) システミック・リスク
|
|
9) 人的リスク
|
|
(3) リスクの計量化とコントロール
|
|
|
|
[8]金利相場の変動要因
|
|
(1) 国内景気と金利
|
|
1) 景気上昇局面では
|
|
2) 景気下降局面では
|
|
(2) 日本の金融・財政政策と国内金利
|
|
1) 日本の金融政策と金利
|
|
ア) 金融緩和政策と金利メカニズム
|
|
イ) 金融引き締め政策と金利メカニズム
|
|
2) 日本の財政政策と金利
|
|
ア) 債券市場の需給との関連
|
|
イ) 景気動向からの間接的な影響
|
|
(3) 米国・欧州等主要国の景気と金利
|
|
1) 投資対象としてのアメリカの金利商品との関連性
|
|
2) 外国為替との関連性
|
|
3) 対アメリカ貿易との関連性
|
|
(4) 外国為替と金利
|
|
1) 国内物価との関連性(輸入面)
|
|
2) 国内景気との関連性(輸出面)
|
|
3) 運用・投資資産としての価値との関連性
|
|
(5) 金融商品(特に債券)の需給と金利
|
|
(6) 金融商品間の裁定とリスク管理
|
|
(7) その他の特殊な変動要因
|
|
1) クレジット・クランチ
|
|
2) 海外投資の需要拡大とジャパンプレミアム
|
|
3) 安全資産運用
|
|
4) インカムゲインとキャピタルゲイン
|
|
ア) インカムゲインだけの特性商品
|
|
イ) キャピタルゲインだけの特性商品
|
|
ウ) インカムゲインとキャピタルゲインの両特性商品
|
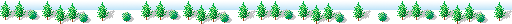
|
(1) 概説
物やお金(通貨)の貸し借り(これを信用といいます)のとき、元本以外に加算される部分を一般に"利子"といいます。この利子をお金で支払い受け取ることが一般です。つまり、お金(通貨)の形で支払い・又は受け取る利子のことを"金利"といいます。
この代表的な例が銀行預金です。銀行(信用できる機関)に預金して、利息を受け取る事です。この利息は銀行に預金した金額(元本)、預金した機関と利率によって決まります。
この利息が利子、利率が金利の事です。
金利は元本又は元金に対する金利の額の比率、つまり利子率又は利率として表現されることが多いため、この利子率・利率を"金利"と表現しています。
資本主義以前の経済社会では、通貨の貸し借りのとき、金利を付けること、そしてそれを取ることを"罪悪"であると考える人々もいました。中世の宗教革命以前のキリスト教会が金利付の取引を禁止することもあったようです。古代ギリシャの哲学者アリストテレスは"通貨は交易の手段(物と物との交換するときの手段)にすぎないのに、通貨が通貨(金利)を生むことは不合理とする"「通貨不妊説」をとなえました。この考え方が中世の教会法の制定に大きな影響を及ぼしたといわれています。
産業資本の蓄積が少なく、蓄積された通貨が少なく通貨の貸し借りが消費の目的に行われ、生産の目的に行われなかった時代と考えると金利を"罪悪"とする考え方は自然だったのかもしれません。
12世紀ごろから、商業資本が発達し、蓄積されるようになりました。商品を生産する過程から利益が生まれ、その利益(利潤)から金利を払うことができるようになっり、金利に対する教会の見方も中世後期には変わってきました。当時の教会法学者や神学者は通貨の使用に対する対価としての金利(利子)「ウズラ」は禁止していました。
債務者が借金の返済に加えて債権者の被った被害は賠償しなければならないとしていました。
*この損害賠償の意味での金利(利子)が、英語の「インタレスト」(金利)の語源「インテレッセ」です。
近代に至って産業資本が形成され、商品の生産過程から利益が生まれ、資本主義的な経済体制が確立されるようになって、通貨の貸借取引に際して金利を支払うことに疑問を持たなくなりました。
今日では、産業の対象が、企業だけでなく、個人、および国、地方公共団体等と広義にわたっています。
人間にとって、現在のことと、将来のことと、どちらが重要と考えるでしょうか。"お金"に限定して考えると、現在お金があれば今必要とする物を買うことができますが、なければ何もできません。必要とする物を手に入れるには、借金するしかありません。
将来のお金は現在使うことはできません。このことは、現在お金を必要とする人は、今お金を必要としない人(貸し手)からお金を借りてくることを意味します。借り手にとって将来より現在の方が大切なことと理解されます。借り手にとっては、現在のお金の価値は将来のお金の価値より高い訳ですから、現在と将来の価値の差額を支払う必要があります。この差額が金利と考えられます。 ……"割引の発想"……・
そこで、借り手は、一定期間、現在のお金を使う権利を貸し手から手に入れることになります。つまり、一定期間お金を使用する権利を、金利を支払うことで手に入れたと考えることができます。一方、貸し手は一定期間、今必要としないお金を使用する権利を放棄する代償として、金利を受け取ることになります。
このように考えると、金利を支払うことで、"将来の時間の価値"を買うことができたと、又"現在から一定期間の将来まで金を使うことのできる権利"を買うことができたと言えます。
この割引の概念は後で説明するデリバティブ商品を考える際の基本となります。
|
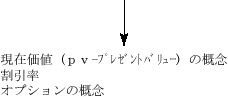
|
(2) 利子学説(金利の本質とは何かを考えた学説)
|
|
|
1)制欲説又は禁欲説
…通貨を保有する者が、その通貨を消費に充てることを抑制したことの対価として、金利が生まれるという考え方です。
通貨を使って物を買う(消費する)ことを"がまん"して通貨を蓄積してその結果、財が増えたと考えるとき、増えた分(金利)は"抑制の対価"の結果であるとする説。
|
|
2)時差説
…固一の財(物)であっても、将来の財は現在の財よりは低く評価されるのは当然で、同じ様に、現在の通貨は将来の通貨よりその価値が高いのが当然とする考え方です。従って、現在と将来の通貨を交換するときには、その差額の分だけ財(物)を補充しなければならない。この差額が金利であるという説。
|
|
3)流動性選好説
…通貨は最も流動的な資産なので、この流動性を満足させてくれる通貨に対する需要は根強いものがあります。この場合、金利はこの流動性を手放す代償として生ずる報酬だと考えるのです。そして、金利水準は、流動性の欲求を満足させるために利用できる通貨量と、流動選好(liquidity-preference)……流動性を欲求する需要の強さ……が均衡するところで決定されるとしています。
したがって、通貨量が増加すれば(流動性選考が弱くなる)金利が低くなり、通貨量が減少すれば(流動性選好が強くなる)金利は高くなるとする説。
|
|
4)産業資本・利潤説(マルクス経済学)
…近代の資本主義的経済体制の下では、金融取引の多くが企業の資本の不足を補うために企業に融資されました。融資された資本をもとに商品の生産過程から生ずる利潤から、その一部を貸し出に支払われたのです。このとき、金利は利潤を生む通貨を利用することができたことに対する代償として理解されます。
間接金融中心の社会機構での考え方といっても良いと思われます。
|
|
5)需給説(近代経済学)
…金利は通貨の借り手が貸し手に対して通貨を一定期間使用させてもらう対価として支払うものとして解釈します。その時、通貨はその使用権を売買する際の手段と考えます。その市場として、
財市場は、一般の物やサービスが売買される場所、通貨市場は通貨の貸借や金融商品の売買を行う場所として考えます。
この二つの市場の全体のバランスが均衡するところが金利水準となるのです。
金利は、物の売れ行きや民間投資、政府の財政支出の大小等、景気を決定する要因に左右されながら全体のバランスによって決められるものとしています。
『[4 ]金利の決まり方』を参照して下さい。
|
|
[2]金利の計算方法
|
|
|
(1)日歩と年利
・・・金利の表現方法による区分です。
|
|
|
<日歩>
日歩というのは、元金100円につき1日何銭何厘何毛というように計算する方法です。これは、欧米では使われることはありません。日本独特のものといえます。この計算方法は短期間の金利計算で便利だったためか、昭和44年に年利建てに改正されるまで長年にわたり、公定歩合はじめコール取引等の短期取引のほとんど全てにおいて使われてきました。現代においては、一部の消費者金融のチラシ広告で見かける程度です。年利で表現するとびっくりするような数字でも具体的な利息金額が表示されるとやや少なく見えるようです。利用する際には十分に注意しましょう。
|
|
<年利>
年利というのは、一年を基準にして金利を計算する方法です。これは元金100円を一年間貸して金利が5円になる取引をした場合に、金利は5%であるというような表現をします。比較的長期間の金利計算に便利であるためか、基本的に世界の基準表現となっています。日本の場合、昭和44年9月に短期金利が全面的に年利建てに変更されるまで、外国からの借入金・外貨預金・郵便貯金の利率・長期国債・地方債・公社債・銀行の定期預金等長期の預金・貸出や債券の利率を表現するのに使われていました。現在では日本の主要金利の全てが年利建てになっています。しかし,国によってまたは金利商品によって、一年の計算基準が360日を使うか365日を使うかで、その金利の数字が違ってきますので注意が必要です。
|
|
(2)単利と複利
・・・お金の増え方の速さの違いによる区分。金利の計算方法の違いによる区分。
|
|
<単利>
単利とは、元金に対してのみ貸借の期間に比例して利息を計算する方法です。この場合、利息の再運用は考慮しません。
|
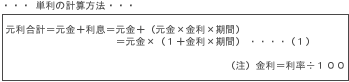 ・・・(1)式
・・・(1)式
<複利>
複利とは、期間の途中で利息を計算し、これを元本に繰り入れて利息を加えた新たな元本として同じ利率で再運用して利息を計算する方法です。
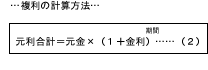 ・・・(2)式
・・・(2)式
*** 短期間では、単利・複利ともあまり違いはありませんが、長期間になりますと両者の差は幾何級数的に大きくなります。
具体的に、元金100万円、利率3%、期間10年として考えます。
単利の場合と複利の場合で、元利合計の殖えかたの違いを見てみましょう。図示すると下図のようになります。
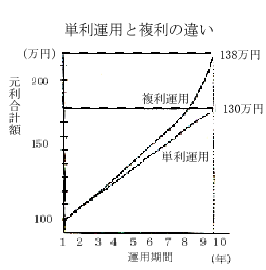
|
この場合10年後の元利合計は、単利の場合130万円、複利の場合、138万4千円です。金利の数字が小さいため大きな差がでませんが、8%で計算すると、単利の場合180万円、複利の場合には、何と約216万円となります。おおきな差が出てきます。現在は、もっと金利が低いですから考え物です。それはさておき、運用期間が長く、金利が高ければ、単利に比べて複利のほうが有利であることは理解できるでしょう。
|
|
①単利の場合……(1)式より
元利合計=元金×(1+金利×期間)
=元金×(1+利率÷100×期間)
=100×(1+3÷100×10)
=100×1.3
=130 (万円)
②複利の場合………(2)式より
|
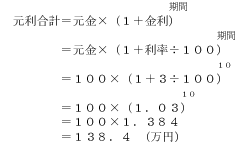
|
金利の計算をする時、運用・調達の期間(日数)の計算に、取引開始日(預入日)と取引最終日(満期日)を入れるか入れないかが問題になります。その期間が長期間となる場合には大きな問題ではなくなりますが、日本の短期金融市場でのコール取引のような、1日・2日の超短期貸借の場合には大きな問題となります。表面上の金利は同じでも実質金利(実効金利とも)に大きな差が生じます。
|
|
① "片落とし"計算とは、
取引開始日と取引最終日のどちらか一方を参入しないで日数計算を行う方法で、"片端入れ"とも言います。例えば、7月1日から7月10日までの取引の場合、片落としでは9日間となります。
この計算方式は、一般的なもので、預金利息の計算・債券利回りの計算・コール取引等の計算に使われます。
② "両端入れ"計算とは、
取引開始日と取引最終日の両日を参入してその期間とするものです。先の例では、10日間となります。この計算方式は、一般の手形割引・新規融資・日本銀行の民間金融機関への貸付および割引取引等の計算に使われます。ただし、日本銀行の取引で、書き換え継続の場合には、片落とし計算の方式で行われます。
|
|
(4)割引率について
金融商品の中には、利率(利回り)として表示するものと、金利ではなく割引率として表示するものがあります。短期の割引金融債・短期国債・割引手形の金利計算表示等がその代表です。ここで、利率(利回り)と割引率とを比較してみましょう。
|
|
① 一般の利率(利回り)は、預入金額を元本として、その元本に対する利息の割合を表現したものです。
例題として、額面100円の割引金融債の購入時の価格が98円40銭とします。そして、90日後に、額面の100円が償還されるという場合を考えます。
この時、90日間の利息額は、
100―98.4=1.6
従って、1円60銭です。
年当たりの利息は、1. 6×365÷90=6.488…
従って、6円48銭となります。
ここで、1年の利率(年利回り)を計算してみましょう。
一般式は次の通りです。
|
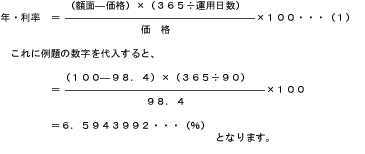
|
② 割引率は、満期償還金額または額面金額を元本として、その元本に対する利息の割合を表現したものです。
同じく、上の例題を使って年・割引率を計算してみましょう。
一般式は次の通りです。
|
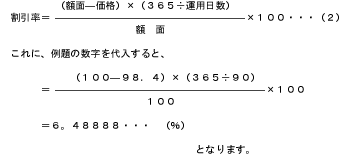
年・利率(年利回り)と年・割引率との違いは、一般式の(1)・(2)を比較 すると分るように、分子の部分は同じですが、分母の部分が(1)では価格・(2)では額面となっています。
ところで、額面と価格とでは、価格(99.6)よりも額面(100)の方が数字が大きくなっています。このことは、一方でパーセンテージで表わされた金利・利率、割引率で、年・利率の方が割引率に比べて大きくなってしまうということです。
したがって、一般の利率と割引率とを単純に比較して判断するのは危険であるといえます。一般的には、割引率を一般の利率(利回り)に変換して表示しているようです。お金の投資・運用の際には、注意が必要です。
|
(1)債券の利回りについて
A)債券投資をする際、毎年一定の利子が支払われ、償還日には間違いなく額面で償還されるということ、すなわち、確定した収入と元金の安全回収の2点が注目ポイントになります。
そこで、債券に投資しようとするとき考えなければならない点は、
* 投資しようとする債券のもたらす利益の計算。
* 他の投資対象との比較。
* より有利かどうかの判断を下すこと。
この判断のバロメーターとなるものが利回りです。
|
|
B) 利回り、利子、利率
債券には似たような言葉がいろいろあります。利回り、利子(利息)、利率もその1つです。
*利率……額面に対して年何%の利子がつくかという割合
*利子(利息)……決められた利率によって支払われる金額
*利回り……投資元本に対して1年当り何%の収益を生みだすか、という率(割合)
通常100円に対して何%、何円と表示します。
|
|
C) 債券の利回りと株式の利回りの違い
株式投資の場合にも利回りという言葉をよく使います。株式の利回りを考える上では、配当が債券の利子に相当します。
ただ、株式は買った時点で配当がいくら支払われるか確定していませんから、株式の利回りには予想的な要素が多分に含まれていることになります。仮に売却時を償還期日、売却価格を償還価格と置きかえて考えても、どのくらいの期間所有し、どのくらいの償還価格になるかは、まったく予想できません。したがって、確定した株式の利回りは投資する時点では計算できないということになります。
これに対し、債券の利回りは、買ってから償還まで何年間にいくらの利子が支払われ、投資元本に対して年当り何%になるかが、あらかじめきちんと計算できます。
このように株式の利回りと債券の利回りでは、予想する利回り(あるいは期待する利回り)と確定できる利回りという大きな相違があるのです。
|
|
D) 利回り決定の3要素
利回りを決定する要素は次の3つです。
|
この3つの要素が互いに変化することによって利回りが変わります。
|
(2)利回りのいろいろ
債券投資による収益には、次の3つがあります。
*利子収入・・・①
*償還時の償還差損益(または途中売却時の売却損益)・・・②
*利子等の再投資による収益
|
|
|
このうち、利子収入のみを考慮したものが直接利回り(直利)です。この利子収入に償還差損益(売却損益)を加味したものが単利の最終利回り(所有期間利回り)です。さらに、①と②に利子等の再投資による収益までも考慮したものが、複利最終利回りあるいは実効利回りです。このように利回りには、いろいろな種類があります。
|
|
1) 直接利回り(直利)
通常は「直利」ともいい、これは利付債のみに用いられる利回りの計算方法です。
|
|
年利子
直接利回り= ―――――――×100
買付価格
|
|
|
直接利回りは、毎年の利子のみを考え、この利子が投資元本に対して何%の率になるかをみるものです。償還差損益が生じる場合でも、これを一切無視して、投資元本(買付価格)に対して毎年何%に相当する収益(利子)が入るかを単純に計算してみようというわけです。
1年に1回とか2回とか決算をして、その期間中の損益を確定する必要のある法人、特に金融機関は直利志向が強いといわれています。
|
|
|
[計算例]
|
銘柄
|
第164回利付国庫債券
|
|
|
償還期日
|
2003年12月22日
|
|
|
利率
|
4.1%
|
|
|
買付価格
|
96円42銭
|
|
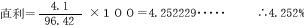
|
2)最終利回り(終利)
最終利回りは単利と複利がありますが、ここでは、日本だけで採用している単利最終利回りについて主に説明します。
ただし、償還まで1年以上の割引債券については、複利の考え方で計算しますので、注意が必要です。4)で説明します。
|
|
ア) 最終利回りの考え方
最終利回りとは、債券を買った日から、最終償還期日まで所有したとき全期間内に入ってくる利子と償還差益(差損)の総合計金額を、1年当たりに換算し投資元本に対して年当り何%になるかをみるものです。
年金信託などのように、比較的長期運用を前提としたセクターは、この最終利回り重視型の投資姿勢が強いといわれています。
|
|
イ) 利付債の最終利回りの計算
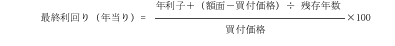
|
前に述べた応募者利回りの計算式のうち、発行価額が買付価格に、年限が残存年数に、それぞれ変わっただけです。
|
[計算例]
|
銘柄
|
第164回利付国庫債券
|
|
|
買付日
|
1994年11月25日
|
|
|
償還期日
|
2003年12月22日
|
|
|
利率
|
4.1%
|
|
|
買付価格
|
96円42銭
|
算式のうち、計算が必要なのは、残存年数です。
残存年数は、買付日から償還期日までの日数、すなわち償還期日まで保有する場合の保有期間のことを意味します。
①買付日の翌日1994年11月26日から1994年12月22日までの実日数を計算し、年換算します。このように、買付日か償還日(あるいは売却日)のどちらかを落とす日数の出し方を片落(カタオチまたはカタオトシ)計算といいます。(前説参照)
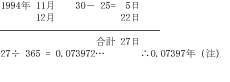
(注)
・小数点以下5位まで算出、6位以下切捨。
・閏年の場合の2月29日は残存1年未満の場合はカウントする。残存1年以上の債券の場合は、考慮に入れない。
②1994年12月23日から2003年12月22日までの年数9年を加え、残存年数は9.07397年となります。
このケースの最終利回りは次のようになります。

[利付債の最終利回りから買い付価格を算出する計算]
実務的には、投資家からの債券の売買注文に対して、価格ではなく最終利回りで答えるのが一般的です。投資家は、それを他の投資物件と比較して売買するに値するかを判断します。
そこで必要となるのが、最終利回りから買付(または売付)価格を計算することです。
買付価格は、下記の計算式により算出されます。
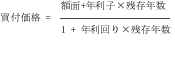
この算式は、既発債券の売買では「最終利回り」の算式よりも多く使われます。というのは、債券の相場は株と異なり、すべての債券が取引所その他で価格、すなわち最終利回りが公示されているわけではないからです。
現在、価格が公示されている銘柄は、上場債・店頭基準気配銘柄を含めても債券全体の1%程度です。
大半の銘柄の利回りは、公示価格銘柄の債券種類、利率、償還期日などを基準に判断されます。
そこで、これに基づいて買付(売付)価格を計算する手順が必要となり、この算式が多く用いられることになるのです。
|
[計算例]
|
銘柄
|
第169回利付国債
|
|
|
受渡日
|
1994年11月25日
|
|
|
償還期日
|
2004年3月22日
|
|
|
利率
|
3.7%
|
|
|
最終利回り
|
4.800%
|
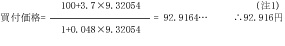
(注1) 普通は少数点以下3位まで表示し、4位以下は切捨てる。
|
ウ) 償還まで1年未満の割引債券の最終利回り
割引債券は、償還金と買付価格の差が利子に相当しますから、計算式は利付債と違います。
また、償還までの期限が1年までのものと、1年以上のものでは計算の方法が違います。
期限1年以下の割引債の最終利回りの計算式は次のとおりです。
|
|
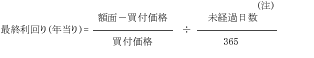
|
(注)未経過日数とは買付日の翌日から償還日までの日数(片落)。
2月29日は日数にカウントする。
|
[既発の割引金融債の最終利回りの計算例]
|
|
銘柄
|
第547号割引商工債券
|
|
買付日
|
1994年12月20日
|
|
償還日
|
1995年11月27日
|
|
買付価格
|
98円17銭
|
未経過日数1995.11.27―1994.12.20=342(片落とし)
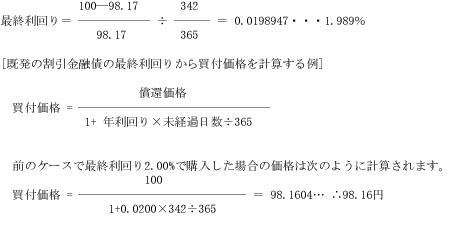
エ) 期間1年以上の割引債券(割引国債)の利回り計算
期限1年以上の割引債券については、毎年の利子が利子を生み、それが積み重なって額面価格(100円)で償還されるのだ、という複利計算の考え方を採り入れています。
この考え方を計算式に表わすと次のとおりです。
償還価格 = 買付価格×(1+ 年当り利回り)年限
例として、以下のような割引国債があるとします。
|
期限
|
5年
|
|
発行価額
|
83円19銭
|
|
応募者利回り
|
3.749%
|
上の計算式に代入すると

|
つまり、83.19円という元本に、年当り3.749%の利子3.118円がつけ加えられて、その合計額86.308円がまた翌年の元本になり、それにまた3.749%の利子3.253円が加えられるということを、最終償還日になるまで毎年くり返し、累積された結果、100円で償還されるということです。割引国債には利払いがありませんが、年1回利払いがあったものとして複利計算したものです。
|

|
[計算例]
|
銘柄
|
第95回割引国債
|
|
|
買付日
|
1994年11月25日
|
|
|
償還期日
|
1999年11月22日
|
|
|
買付価格
|
84円83銭
|
|
|
残存年数
|
1994. 11.25~1999. 11.22= 4.99178年
|
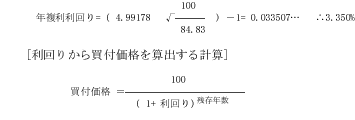
|
3) 所有期間利回り
|
|
|
債券に投資する場合、その債券から得られる収益は2通りあります。インカムゲイン(利子収入)とキャピタルゲイン(売買損益)です。所有期間利回りとは、利子収入と売買損益の合計額(インカムゲインとキャピタルゲイン)が投資元本に対して年率何%になるかをみたものです。
1980年代の前半までは、金融機関等の債券投資は新発債に応募したり既発債を買入れた場合のいずれもインカムゲインを目的とし、たとえ途中で値上りしても売却することはまれで償還まで保有するのが普通でした。しかし、直利面で有利な利率の高い債券はそのまま保有していられますが、低利率の債券は、もし金利が反転したら、金融機関の収益面でマイナスに作用します。また、低利率の債券を取得しなければならないような状況の時は、金融機関にとっては貸出しが伸びないため債券投資が増加することになります。1986年から1988年にかけて極端に低金利の状況となり、金融機関は債券を市場より買入れ値上りを待って償却する、キャピタルゲインを目的とした所有機間売買を盛んに行いました。このことは、1984年6月から銀行などの金融機関が公共債ディーリングを認められ、行うようになったことが背景となっています。この手法を所有期間利回り狙いの短期ディーリングといいます。
所有期間利回りの計算方法には、一般方式と現先方式があります。現先方式については短期金融市場の項(第2部)で説明することにして、ここでは一般方式での計算式のみを示しておきます。
|
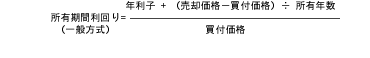
|
4)複利利回り(複利)
複利利回りとは、投資元本を再投資レートr%で満期償還時まで複利運用する場合の将来価格[A]と、償還時までに得られる利子収入、利子を再投資レートr%で運用した場合の孫利息収入、および額面金額の合計額[B]が等しくなるという考え方をとります。この場合のr%が複利利回りとなります。
一般的に考えるために、以下のような債券があるとします。
|
P:債券価格(円)
|
C:利子(%)
|
T:残存期間(年)
|
|
r:再投資レート/100= 複利利回り/100
|
|
|
★投資元本(債券価格)の将来価格と利子の将来価格
投資元本Pを年利rで複利運用すると、1年後は、
P1= P+ Pr= P(1+r)
2年後には、
P2= P1+P1r= P1(1+ r)= P(1+r)2
T年後には、
PT= P(1+r)T
また、1年後の利子Cを年利rで複利運用すると、1年後は、
C1= C
2年後には、
C2= C1+C1r= C1(1+r)= C(1+r)
3年後には、
C3= C2+C2r= C2(1+r)= C(1+r)2
T年後には、
CT= C(1+r)T-1
となります。
すなわち、元本PのT年後の将来価格は
Pt= P(1+r)T、
利子CのT年後の将来価格は
CT= C(1+r)T-1
と表されるわけです。
|
|
|
★ まず、T年後(償還日まで)の元利合計〔B〕を求めます。
|
|
1年目末の受取利息のT年後の将来価格
|
C(1+r)T-1
|
|
2年目末の受取利息のT年後の将来価格
|
C(1+r)T-2
|
|
(T-1)年目末の受取利息のT年後の将来価格
|
C(1+r)1
|
|
T年目末の受取利息のT年後の将来価格
|
C(1+r)0
|
|
T年後の償還金
|
100
|
したがって、T年後の元利合計は次のようになります。
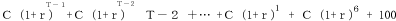
さらに、等比級数の和の公式を使って整理すると、
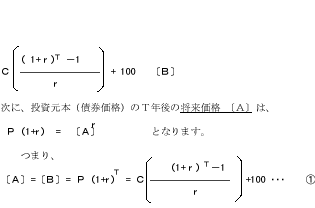
★1年複利利回り(AIBD方式)
ヨーロッパ市場では、1年複利利回りが採用されており、債券価格Pは ①式より、以下のように示されます。
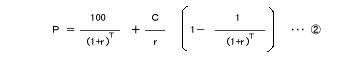
★半年複利利回り(U.S.A方式)
②式を年2回利払いに置きかえると、以下のようになります。
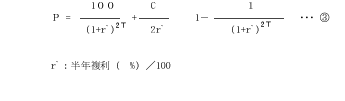
ところで、③式によって算出されたr'(半年複利)を年複利利回りに換算する場合、2通りの方法があります。たとえば、r'= 4(%)と算出されれば、米国では単純に2倍して年利回りを8%と表示ます。
ところが、ヨーロッパ市場では、半年複利法が用いられる場合には以下の式によって求めます。
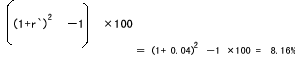
|
[4]金利の決まり方(需給説に従って)
|
|
(1)通貨市場
通貨市場において、通貨の需要の側面と供給の側面に分けて分析します。
1)通貨の需要
……ものを購入するために、その準備として通貨を保有したいという動機による人々、場合によっては借金しても目的の物を購入したい人々にとって、通貨の需要は、ものの売買高である所得(マクロ的)が増えれば増えるほど大きくなります。
一方、万一の出費のために、その準備として、通貨(現金)保有したいという動機の人々、また人によっては、いまある金融資産や土地・家屋等の実物資産などを整理して換金して現金として通貨を保有する人もいるかもしれません。この様な人々にとって、金利が高い時には金融資産等の収益を生む資産へシフトするために、通貨の需要は、小さくなります。逆に、金利が低い時には、その需要は大きくなると考えます。通貨の需要は、ものの購入または非常時の出費の準備という2つの動機の大小によっていると考えます。
しかし、今の現実を見る限り、金利が低いからという単純な理由で資金需要が増えるとは考えられません。経済が安定成長している場合の理論構成といえます。
2)通貨の供給
……通貨の供給は、日本銀行(中央銀行)によるマネーサプライによって最終的に決まるものと考えます。最後の通貨の番人ですから、彼らの金融政策は時間的なずれはあるもののマクロ的にはその範疇に収まるものと考えられます。それも、実体経済に対する正確な把握・判断とその金融政策に対する一般の人々の信頼があってのことです。
人々の所得(収入)が少なく金利が高い時には、通貨に対する需要は小さくなります。反対に、所得が多くなって金利が低い時には、資金需要は大きくなります。
実体経済が安定しており、収入に対する不安がない社会であれば、この理論通りになるものと思われます。そこに金融政策だけでは限界があるものと考えられます。
LM曲線とは
通貨の需要と日本銀行によるマネーサプライがちょうど一致するような金利と所得の組み合わせを描いたものがLM曲線です。
|
(2)財市場
……一般的な有形の物品の売買や一般のサービス産業・金融業・運送業・情報産業等のような無形のサービス・技術・利便性を対価に売買する市場をさします。この財の価格は、その需要と供給が一致するレベルで決まるものと考えます。そのためには、人々の貯蓄と企業の投資が一致することを前提に考えます。
1)貯蓄は、人々の所得と消費との関連があります。それは、所得から消費部分を差し引いた残りの部分と考えられます。所得が増加すれば、基本的な消費部分を差し引いた可処分所得は増加するものと考えられますから、その中から当然貯蓄に回す部分が増加するのは必然です。
しかし、そこで問題となるのが、金利水準です。異常事態ではない健全な経済状況であることが大前提です。人々にとって、貯蓄するにも物を購入するにも適正な金利水準が求められます。しかし、さまざまな要因でそれぞれの金利が決められていますので、どの金利水準が適正かは一概には判断できません。あくまでも、相対的なものと理解されます。
2)投資は、物やサービスと言う財に対する需要が旺盛であることが前提ですが、例えば企業から見て、各企業の生産性の効率に比べてその調達コスト(金利)が低いほど、設備投資等の前向きの資金需要が刺激されますから、その金利が下がれば下がるほど投資は増加します。
IS曲線とは
財市場で人々の貯蓄と一般企業の投資との需給がちょうど一致するような金利と所得の組み合わせを描いたグラフが、IS曲線です。
|
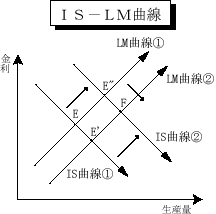
|
図表の解説(条件および仮定)
ここでは、通貨市場における通貨の需要と中央銀行のマネーサプライが一致しており、なお且つ、財市場における人々の貯蓄と企業の投資が一致していることを前提にした経済状況が今あると考えて下さい。
この時、図表の貨幣市場でのLM曲線①と財市場でのIS曲線①の交点Eで、それぞれの金利と所得が均衡しているということができます。
|
*1.
日本銀行が、金融政策の変更のために通貨供給量を増大させる金融緩和政策を行ったと考えてください。
この場合、金利は低下します。したがって、 LM曲線が下にシフト(LM曲線1→LM曲線2)します。そして、IS曲線とLM曲線の交点はEからE’へ移動します。(財市場のIS曲線は動かないものと考えます。)このことは、所得が、増大したということを示しています。つまり、金融緩和へ政策が変更されたために、以前に比べ金利は低下し、その効果として所得が増大するということを説明しているのです。
*2.
次に、例えば、経済状況が過熱気味になり、企業の投資意欲が旺盛になった場合、または、政府が財政支出を増大させる財政政策を採用するという状況を考えてく下さい。
この時、財市場の需給バランスの変化から金利は上昇しますが、所得も増大します。IS曲線は上へシフト(IS曲線1→IS曲線2)しますから、均衡点はEからE’’へ移動します。景気過熱または景気拡大の財政政策が取られたの経済状況では、資金需要が出てくると考えられますから、金利は、上昇気味になります。このIS曲線は上にシフトするものと考えられますから、通貨市場のLM曲線が動かないものと仮定すれば、所得も増大するものといえます。
ところで、この図表をつかって、景気循環の説明をすることが出来ます。
景気循環は、この図ではEからE’、F、E’’、そしてEへと左回りで1回転する経済の均衡点と考えることもできます。
E、E’、Fの動きが好況期を,F、E’’、Eが景気後退期を表しており、とくに景気の過熱期E’→Fでは金利が上がっても生産量が上がること、また、景気の崩壊期F→E’’では金利は下がっているのに生産量も下がっていくという状況が、説明できます。
金利は、所得とともに、通貨市場と財市場の2つの市場における需給バランスによって同時に決定されます。そして、2つの市場の需給バランスは、日本銀行の金融政策(マネーサプライ)、人々の通貨を保有しようという動機、企業による財の供給や投資の判断、政府よる財政政策などさまざまな要因から影響を受けて、変化すると考えられます。
|
[5]金利水準
|
|
|
金利水準を考えるとき、金利には、一般の貸出金利・銀行の預金金利中央銀行の貸出金利(公定歩合)・民間銀行の貸出金利・金融市場の金利…といろいろな種類のものがあります。しかも、金利の高さがそれぞれ違います。
各種の金利は、一つの金利体系を構成しています。金利体系はその国の金融システム・金融政策(金利政策・為替政策)・財政政策等によって違いがあります。従って、金利体系の中心として、中央銀行の公定歩合が上げられますが、この公定歩合を金利水準の比較に利用して、その国の金利水準の全般を把握する方法は、避けねばなりません。従って、金利の国際比較をする場合には、いくつかの主要な金利を比較し、総合的に、判断する必要があります。そのため、インフレ率を勘案して、実質金利で金利水準を把握する方法が一般的となっています。
ところで、金利は金融情勢ないし景気変動によって大きく変動するという点です。政策当局が引き締め政策を取るか緩和政策をとるかによっても、金利は大きく変動します。
たとえば、経済が好況に向かいますと、資金に対する需要が盛んになって、その結果、需給関係から考えれば、当然金利は上昇するものといえます。さらに、中央銀行が経済の行きすぎを防止する目的で、引き締め政策を採用した場合、公定歩合が引き上げられますが、金融機関の金利も同じ動きをするのが一般的です。こうして、景気上昇期には金利水準は大きく上昇します。
反対に景気が後退するときには、資金需給は緩和し、そのうえ中央銀行は公定歩合を引き下げて景気後退を阻止しようとしますから、金利水準は下がるのが一般的です。
また、金利の国際比較をする場合には、各国の景気循環がつねに同じような動きをするわけではありませんから、ある一時点の金利水準のみを比較しても十分ではないということを理解しなければいけません。ここでは参考までに、主要金利の国際比較を表に整理しておきます。
|
|
市中金利動向(2001年8月現在)
|
|
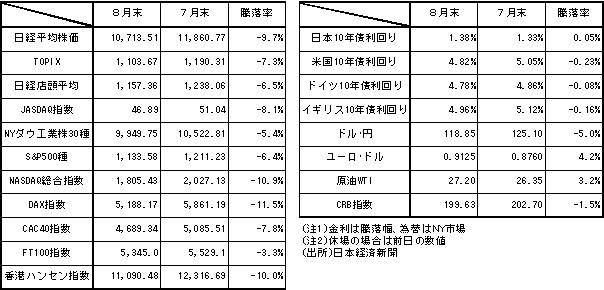
|
|
[6]金利の種類と分類
|
|
(1)規制金利と自由金利
.概説と金融商品
規制金利…金融当局によってその値動きが規制されている金利をさします。代表例として、公定歩合があります。公定歩合は、日本銀行が市中銀行に対して貸し出すときに適用される金利です。日本の経済状況を考慮して、“日銀政策委員会”で決定されます。
自由金利…値動きに制約がなく、自由に決定される金利をさします。その取引形態によって相対型と市場型に分類できます。
|
(A)相対型金利
|
|
…市場を経由せずに当事者間で直接決定される金利をさします。
ex国債の入札金利等
|
|
(B)市場型金利
|
|
…その資金が取引されている市場があり、そこで決定される金利をさします。
ex国債の流通金利等
|
金融商品を規制金利と自由金利に分類すると、
規制金利商品.…公定歩合連動型と長期プライムレート連動型に分けられます。
|
(A)公定歩合連動型
|
|
…普通預金、通常貯金、金銭信託(2年)、貸付信託(2年)、ヒット、ビック(2 年)。
|
|
(B)長期プライム連動型
|
|
…金銭信託(5年)、貸付信託(5年)、ビック(5年)、利付金融債、ワイド、ハイジャンプ、公社債投信。
|
自由金利商品…長期・短期金融市場での実勢金利を直接反映した商品と実勢金利は間接的で金融界特有の調達コストを反映した商品に分けられます。
|
(A)直接に市場実勢金利が反映した型
|
|
…CD(譲渡性預金)、CP(コマーシャル ペーパー)、大口定期預金、スーパ-定期預金、ニュー定期、期日指定定期預金、金貯蓄口座、抵当証券、外貨預金、定額貯金等。
|
|
(B)間接的にしか市場実勢金利が反映しない型
|
|
…貯蓄預貯金、積立預貯金、割引金融債、スーパーヒット、等。
|
|
|
…外貨預金…
自由金利商品のひとつで、銀行に外貨建てで預ける預金です。利回りが今の円預金に比べて高くても、為替レートのうごきによって元利金ともに円貨ベースで見るとかなり変動します。その意味で、元本の保証の無いリスクある商品です。基本的に、為替の変動の割合より、金利部分の変動の割合の方がはるかに小さい商品といえます。この為替のリスクをなくした外貨預金については、『外国為替基礎講座第一部』の“スワップ付外貨預金の項目”を参照して下さい。
単利運用商品と複利運用商品について
利息の殖えかたの違いによる区分『金利の計算方法、単利と複利』を参照して下さい。)
単利運用商品…大口定期、利付金融債、割引金融債、国債、スーパー定期、抵当証券 、公社債投信(一般)等。
複利運用商品…ワイド、ハイジャンプ、期日指定定期、スーパー定期(3年もの)、金銭信託、貸付信託、ビッグ、ヒット、スーパーヒット、ダブル、中国ファド、MMF、スーパーゴールド(継続)、公社債投信(複利コース)、ハイパック、定額貯金等。
|
|
(2)分類
取引される金利の期間により長期金利と短期金利に分けられます。現物とデリバディブをベースにした区分も考えられます。
以下、金利を大まかに分類すると下の図表のようになります。
|
|
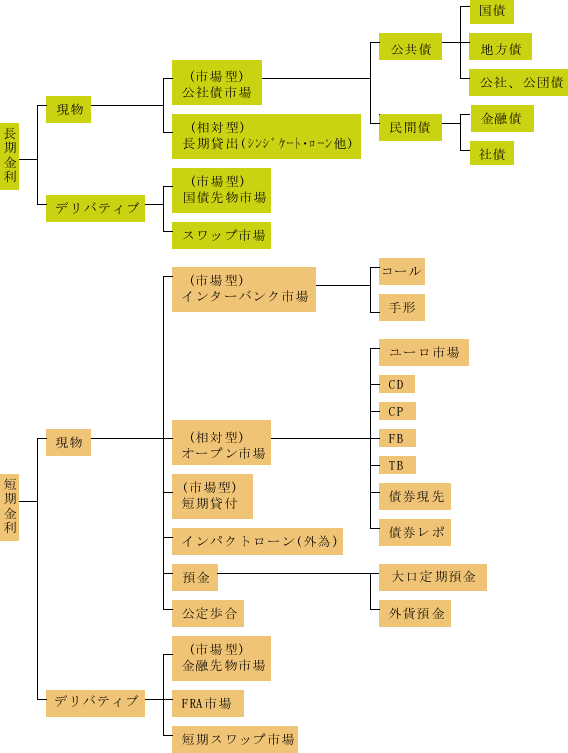
(3)金利体系について
「金利水準」で説明したように、金利にはいろいろな種類があり、それぞれ格差があります。また、各種の金利は、マルチ的に見た経済状況・その国の金融システム・金利および為替等を含む金融政策・財政政策・各金融機関の経営方針および戦略・デリバティブ商品の開発レベル・その残高および影響力……等複雑に絡み合って決められています。しかも、それぞれの金利の間には、相互に密接な関係があり、一つの金利体系を構成していると考えられます。
1)金利間の格差について
その格差がなぜ生じるかは、取引される資金の使いみち・資金の性格の違い・その期間として説明されます。
|
ア)資金の流動性
その資金が現金化し易いものかどうかは、流動性があるか、どの程度かという問題となります。資金の流動性は、基本的に期間の長短を基準に、また市場性のある商品かどうかで判断されます。その資金の回転率がどうかを考えた場合、金利は期間の短いものよりも、長い方が高いと考えられます。例えば、3ヶ月の定期預金は、要求払い預金に比べて資金が3ヶ月間固定されますから運用側から見ると流動性は低いといえます。したがって、定期預金の金利は、要求払いの預金金利よりも高くなるのは当然と考えられます。
|
|
イ)確実性(相手のリスク)
資金の借りての信用が高ければ高いほど、その回収の確実性は高いといえます。資金の回収の確実性は、資金の用途・確実な担保の有無・借り手の信用度・貸出し期間の長短等の諸条件により違ってきます。同じ期間で、その借り手が国・企業・個人によって貸出し金利が違うのは理解されます。
|
|
ウ)資金相互間の関連
銀行は基本的に預金金利をコストの一部として、これに手数料・人件費・その他諸経費を加味して資金の貸出金利を算出します。従って、貸出金利は預金金利より高く設定されるのは当然です。ここで、銀行の資金調達手段であるCD(譲渡制預金)・大口預金金利と企業の短期での調達手段であるCPが一時逆転したことがありました。この時、大口預金金利とCPとの間に金利裁定が働きCPとCDがある一定の水準に落ち着きました。このことは、資金相互間で調整が働いたものとかんがえられます。ところで、手数料を含む諸経費について、今後ビックバンの進展によりかなり見直しを迫られるものと考えます。また、金融市場・資本市場のグローバル化が進む現代において、さまざまな資金の関連性は、さらに緻密なものになるでしょう。
|
2)金融システムとの関連
各種の金利が、どの程度関連性をもっているかは、国によってかなり違います。アメリカ・イギリス等は金利相互間に密接な関係があり、金利体系は整然としたものとなっています。市場金利の動きが、資金の需給にすぐ反映し、その流れや分配をかえる仕組になっています。金融市場に限らず、資本市場の発達が進んでいることに起因するものと考えられます。特に、資本市場の発達は、例えば企業の直接資本の導入を容易にします。間接金融としての金融機関の役割は補完的なものに変わります。すべてのリスクは、公正な情報開示のもとで自己責任により判断されます。英米の金融システムを考えると、資金の流れをどのように作り、安全性・流動性のある金融市場をどのように育成するか、集めた資金・資本をどのように企業・国に分配するか等に力点が置かれているように思われます。また、そのシステムを維持するためには、全面的にカリスマ性が必要です。その意味で中央銀行の果たす役割が重要となってきます。それは、人・組織・国を含めてのものです。資本・金融市場での絶大な“信頼”は欠くことの出来ない条件です。
ところで、銀行券の流通すらまだ国の経済の末端にまで行き渡らない国では、中央銀行の管理の届く金融機関の範囲内では低金利が維持されているのに、末端では数十パーセントという高金利が珍しくないという現象が当たり前です。一昔前の発展途上国によく見られました。一時期のロシアも…。
金融市場・資本市場が発達していれば、金利相互間に密接な関連性が生じます。それは、丁度、“一物一価の法則”が作用しているかのようです。
(4)金利体系の分類
1)公定歩合
・公定歩合とは中央銀行がその取引先に対して貸出を行う場合に適用される金利のことです。我が国の場合、中央銀行は日本銀行をさします。そして、その取引先とは、基本的に、日本銀行に口座を持っている金融機関をさします。
法律上は、「割引ニ付基準ト為ルベキ割引歩合」および「貸付ニ付基準ト為ルベキ貸付利子歩合」という表現が用いられています。これを、「公示スベキ」こととなっています。これが、「公定歩合」と呼ばれる所以です。
日本銀行の公定歩合は、再割引の対象・貸付を行う時の担保の種類によって2種類に分けられていますが、商業手形割引歩合をさしています。しかし、商業手形の流通量が減っているためその適用対象が広げられています。
・金利体系において、公定歩合はその中心となる基準金利ないし中心金利としての存在です。公定歩合の変更は直截的に短期金融市場の変動を促し、金融市場の動きを通じて、間接的には長期金融市場(国債のみならず長期貸付)にも影響力を持っています。日本銀行の金融政策の意図を明確にアナウンスメントする手段の一つと考えられます。
・中央銀行が“Lender of Last Resort”とか、俗に“銀行の駆込み寺”呼ばれることがあります。これは、公定歩合が、中央銀行の政策手段としての効果を最大限に発揮するためには、中央銀行の金利は「懲罰的」であるべきだという考えに基づいています。つまり、公定歩合は民間銀行の金利に比べて割高でなければならないという考え方です。公定歩合を割高にして、安易な中央銀行貸出の発生を防ぐことを目的にしています。
借り手である民間金融機関は金融市場でどうしても資金を調達出来ない ときにのみ、中央銀行へ借りに来るという仕組を作ります。この仕組を前提に、金融を引き締めたいときには、公開市場操作や支払準備制度の運用によって、市場の資金を不足の状態に導き中央銀行からの借入を増やさせます。民間金融機関にとって短期の借入に偏ってしまうため、返済圧力が強く働いて、金融市場はタイトへと導かれその目的を達成しうるのです。
ただし、このような中央銀行貸出本来のあり方は、一時期までイギリスで実施されましたがいまでは行われていません。必ずしも普遍的なものではないようです。最近は、中央銀行の根源的な存在意義が問い直され、方法論的アプローチを問題にすることは少なくなっているように思われます。
・なお、公定歩合は「日銀政策委員会」においてその時々の景気状況・為替動向・物価傾向・海外金利との比較・日本の国際政治経済上の立場等を総合的に判断し決定されます。
2)市場金利
ここでいう市場金利とは、短期金融市場の市況を示す代表的な金利のことをさします。
・民間銀行が、個々の取引先に対して適用する貸出金利とは違い、公開の金融市場での金利であり、金融市場の繁閑を反映して敏感に動くのが特徴です。短期金融市場の金利には次のようなものがあります。
1.コールレート(有担・無担)
2.手形市場レート
3.債券現先レート
4.TBレート・FBレート
5.CDレート(譲渡性預金金利)
6.CPレート(コマーシャル ペーパーの市場流通金利)
・特に、コール市場・手形市場は金融機関の相互間における短期間の資金取引であることが特徴です。各金融機関の支払準備金(手元にある現金準備金・日銀準備金)は、短期的な資金として運用されるため、その流動性が重要視されます。無担の取引を除くと、担保の徴収によって資金の回収が保証されています。
・また、短期金融市場で取引される市況は、その時々の金融の繁閑を忠実に且つ敏感に反映して動いています。その意味では、金融市場の情勢を判断する時の、バロメーターといえます。
・金利体系において、本来的・公定歩合の意味合いを考えた場合(前述の公定歩合の項目参照)、公定歩合は高く、コール・レートや手形レートは公定歩合に比べて低くなります。しかし、我が国の場合、経済成長に伴って必要とした資金を日銀貸出によって供給してきたこともあり(オーバーローン)、公定歩合は民間貸出金利より割安になっています。現代でも、ここでいう市場貸出金利は、直近のオーバーナイトの無担・有担コール金利を除き公定歩合よりも高い水準のままです。
現代でも日本銀行の貸出政策が一般に有効とされるのは、その貸出の多い都市銀行に対して一定の「貸出限度額」を設定して、野放図な信用膨張を防ぐ手段を講じており、金融調節・資金需給の調節がうまく機能しているからであると説明されています。もう一つの歯止め策としての「窓口指導」は現代では行われていません。
別の説明によると、金融市場が発達していることをその理由としています。民間銀行が一時的に資金不足が生じたとき、金融市場が発達していれば、手持ちの第二次支払準備(コールローン・政府短期証券)を処分することで資金不足を埋めることができます。日本銀行に駆込まずともすみます。基本的に、コールローンや政府短期証券は、金融資産としては流動性があり、民間銀行が第二次支払準備として保有するものですから金利は低いものとなります。銀行としても、はじめから高収益を期待してません。したがって、公定歩合に比べて低いのが通常です。
3)預金金利
・我が国における銀行の預金の種類は多く、預金残高は国民総貯蓄額のかなりの割合を占めています。銀行の営業努力の他に、明治以来、政府・金融当局が銀行預金優遇政策をとって来たことの結果とする説明もあります。
・貯蓄を美徳とする考え方が今でも通じるような特殊な風土・慣習を維持する教育が続いてきたことに起因するのではと考えます。しかし、時代の変化はこれを善しとはしないようです。例えば、投資信託の商品の概念は運用をベースにしたものですから、銀行の預金金利の安全性だけの商品は考え直されるものと思われます。
・以前預金金利は「臨時金利調整法」という法律によって預金の種類別に最高限度が定められていました。この上限は、大蔵大臣の発議に基づいて日銀政策委員会が決定します。この日銀政策委員会は金利調整審議会に諮問してその答申に基づいて決定していました。決定された内容は大蔵省告示として一般の人々に公告されます。その後の手続きとして、日本銀行はこの規制の範囲内で期間別の預金金利をガイドラインとして公表しました。そして、各銀行は、このガイドラインに基づいてそれぞれの銀行の預金金利を決定しました。なお、このガイドラインは金融の自由化に沿って平成6年10月に廃止されましたが例外として金利の付かない当座預金については現在も適用されています。
・郵便貯金の金利は郵便貯金法に基づいて政令で別に規定されています。こ のため、銀行預金の金利との整合性がよく話題となります。
・信託銀行の金銭信託については、届出制度によって大蔵省の指導を受けることになっています。この届出を通じて事実上規制されているものと解釈されています。
(預金コスト・資金コストについて)
★預金コスト
各種の預金金利を預金量に応じて加重平均したものが、預金一単位当たりの支払い平均金利です。この金利に、銀行の店舗等の維持・管理コスト(物件費)や人件費そして税金を加えたものが銀行にとっての預金コストです。
★資金コスト
上の預金コストに銀行が市場等から借入れた借入金の支払金利を加えたものが資金コストです。総合的な調達コストといえます。
4)貸出金利
・銀行の貸出には大きく分けて手形割引と貸付金の二つの形式があります。手形割引は手形の表示金額から満期日までの利息分を差し引いて既存の手形を買い取る形式です。主に、商業手形(3ヶ月が一般的)の割引が行われています。特に、優良商業手形(日銀適格手形)について、銀行は、日本銀行の再割引を受けたり、その貸付けの担保に当てることも出来ます。
貸付金は次に説明する手形貸付・証書貸付・当座貸越の三種類にわけ られます。
★手形貸付
資金の借り手が自己を振出人・銀行を受取人とする約束手形を振り出し、銀行はこの手形を割り引く形式で貸付を行う。
★証書貸付
資金の借り手の借用証書を銀行に差し出す形での貸出。
★当座貸し越し
銀行が当座預金の取引先に対して、あらかじめ限度額(極度額)を設定して当座預金残高を超えた振り出された小切手の支払いを認めるという貸付。
・銀行の貸出金利についても預金金利と同様に臨時金利調整法によって上限が規制されています。銀行の自主性が尊重され、各銀行の自主的な判断で貸出金利が決められています。
・貸出金利の中で信用度の高い取引先に対して適用される貸付金利はいっぱんの金利に比べて低いものとなっています。この優遇された金利のことをプライムレートといいます。
プライムレートには短期プライムレートと長期プライムレートがあります。
★短期プライムレート
従来の短期プライムレートは一年未満の貸出金利の基準として公定歩合が使われてきましたが、金利自由化の進展に伴って、金融政策の有効性を確保するという目的で市場実勢を反映させた方式に変更されました。(1988年1月に導入)
各銀行ごとに、規制金利・市場金利それぞれの調達部分の比率によって計算(預金コスト)し、これにさまざまな必要経費(業務維持・管理費、人件費、税金等)を加えて資金の総合的な調達コスト(資金コスト)を出します。これをベースに、貸出の需給環境・市場金利の動向および利益等を総合的に判断して決められます。
ベースレートが0.25%以上変動した場合には0.125%刻みで変更するものとしています。
★長期プライムレート
この長期プライムレートは長期貸出金利の基準として利用されてきました。新発利付金融債のクーポンレートに0.9%を加えて決められます。
新発利付金融債とは長信銀各行および農林中央銀行・東京三菱銀行・商工中金等の債券・発券金融機関の発行する利付金融債です。そのクーポンレートは毎月の発行ごとに、相場動向に左右され変動します。
利付金融債のクーポンレートの改定は、毎月の国債発行の条件交渉の時期に合わせて決められます。毎月20日過ぎに発券銀行による定例会議が開かれ、25日前後にクーポンレートが決められ、28日頃発行されます。この会議で、前月発行された金融債の相場状況・市場実勢や長期国債のクーポンの動向、各行の事情等を踏まえて話し合われます。その変動幅は最低0.2%とされています。
改定されたクーポンレートに0.9%を加えたものが長期プライムレートです。
★新長期プライムレート
これは、前述の短期プライムレートに「期限の利益」相当分のプレミアムを上乗せして決められるものです。従来の固定金利の考え方に変動金利の利便性を加味して考えられたものです。IRS等のデリバティブ商品の開発・普及との関連は無視できません。
1年超から3年以内のレートは短期プライムレートに0.3%を加えた金利、3年超のものは短期プライムレート(短プラ)に0.5%を加えた金利となります。
5)LIBORとTIBOR
★LIBOR
ロンドン時間の午前11時時点のオフショアにおける銀行間の資金取引のうち、出し手サイドの金利をさします。BBA(英国銀行協会)が取りまとめて発表するものです。
LODON INTER BANK OFFERED RATE
の頭文字を取ったものです。360日ベースで計算されます。
このLIBORは、国際的な信用の高い複数の銀行が提示したレートをもとに算出されたものですから、国際金融市場における短期金利の指標として信頼されています。各国の金利市場・債券市場での基準金利としての意義のみならず、貸付市場においても基準金利となっています。デリバティブ商品のIRS・FRAにおいては変動金利として広く一般的に利用されています。
US$・¥を始めとして、世界の主要通貨のほとんどが提示されています。その意味では、ひじょうに便利です。
LIBORはロイター社・テレレート社等の情報会社に掲載されています。この多義性・公示性・客観性の高さが広く利用される理由となっています。
なお、ロイター社では「LIBO」または「LIBOR1」のページに、掲載されています。
★TIBOR
東京時間の午前11時時点の東京マーケットで提示された銀行間取引レートのうち、出し手サイドの金利をさします。日本の全国銀行協会(全銀協)が指定した18銀行の上下それぞれ2レートを差し引き、残りのレートの平均を採用しています。365日ベースで計算されます。
国内の貸出等の基準金利として利用されています。しかし、残念ながら最近のように、邦銀の格付が引き下げられるようになると、LIBORとの比較で理解されるように、貸出し基準の差が歴然となってきました。国際基準から見て、今後さらに差が広がりこのままの状態が続くようなことは、金融機関の弱体化のみならず、一般企業にまでそのコストを押し付けることになり兼ねません。ひいては日本全体の経済力の衰退を助長することになりかねません。現状この金利格差は解消されましたが、金融機関ごとの格付けの格差があり、実際の貸付金利と表向きの金利との間に格差が生じています。
6)債券(公社債)金利
債券市場とは、債券の発行・売買を通じて資金の需給が行われる市場をさします。債券の機能から、発行市場と流通市場に分けられます。発行市場とは、新たに債券が発行される市場をさします。流通市場とは、既発債(既に発行され投資家の手元にある債券)が売買される場所をさし、ここを通じて、市況に応じた妥当な債券価格が形成されています。
公社債とは、「公共債(公債)」と「社債」の総称です。「公共債」は、公的機関、国や地方公共団体および政府機関の発行する債券を、「社債」は民間の株式会社が発行する債券を差します。発行主体別に分類すると、国債・地方債・特殊債(ex政府保証債)・金融債・社債(事業債)・外国債があります。
債券の発行条件は、返済の確実性・流動性の差異によって格差が生じます。一般的には、長期金利が最も低く、社債(事業債)が最も高くなっています。
債券の利回りについては、「前述の金利の計算方法、[3]債券の利回り」を御覧ください。
7)デリバティブ商品の金利
デリバティブ商品については、国際金利講座 第二部 をご覧ください。
[7] 金利相場のリスク
(1)リスクとは
金融商品の取引を行う際にはそのリスクを念頭に置かなければなりません。
リスクとは、辞書的には「危険・冒険・危険な(物・人)・損害の恐れ等」をさします。金融取引に当てはめると、当該取引を行うことで損害を被る可能性が有るということをさします。金融取引での"損害または損失"とは、運用利回りが調達コストを下回ってしまうことや、債券・株・為替・等の購入(買い値)価格が販売(売り値)価格を上回ってしまうために起こる経済的損害を意味します。これとは反対に、運用利回りが調達コストを上回る場合には"利益"、経済的利益を得たことになります。このように、金融取引において、"損失"と"利益"は表裏一体の関係に在るといえます。
常識的に考えて、誰も利益の在るときにはこの"リスク"を問題とはしません。しかし、"損害または損失"が発生したと、また発生するおそれのある時にはこれに対してどのようにすればいいのかを考えます。
金融相場の商品に限らず、すべての商取引には、"損失"と"利益"の可能性が存在します。特に、"損失の恐れ"については、いつ何が起きるかを"予知"することは不可能です。そこで、将来の"損失と利益"が不確実であることを"リスクがある"と認識することになります。この時、リスクの概念は"損失"と"利益"を包括的に把握します。リスク管理でいう"リスク"はこの包括的概念です。従って、リスクに対する認識とそのリスク管理の必要性は同義と考えるべきです。
一般的に"リスク"として、
①「市場リスク」
②[信用リスク」
③「流動性リスク」
④「決済リスク」
⑤「法的リスク」
⑥「会計・税務リスク」
⑦「オペレーションリスク」
⑧「システミックリスク」
⑨「人的リスク」
などが上げられます。
これらのリスクを"不確実性の要因"に分類し、このリスクを管理する際に"計量出来るかどうか"で区分すると以下のようになります。
Ⅰ)計量可能リスク---リスク量を計量したり、指標化することで数字によって管理できるリスク
①市場リスク
②信用リスク
③流動性リスク
④ 決済リスク
Ⅱ)計算不可能なリスク---リスク量の計量化が出来ないリスク。市場環境整備が 不備であるとか、取引の手続きに関する管理に関する事項。
⑤ 法的リスク(リーガル・リスク)
⑥ 会計・税務リスク
⑦オペレーションリスク
Ⅲ)その他のリスク---上記のリスクとは区分すべきリスク。
⑧システム・リスク
⑨人的リスク
各項目について以下説明します。尚、[外国為替基礎講座]では、"外国為替取引のリスク"を簡単に説明してあります。
(2)リスクの種類
1)市場リスク(マーケットリスク)
市場リスク(マーケットリスク)について、「市場の価格、金利等の変動により、保有する金融資産の価格が変動した結果、損益の変化を伴うこと」と定義されます。または、「価格や金利の変化により保有するポジションの価値(現在価値)が変動するリスク」とも考えられます。
市場の変動により、債権では金利上昇で価値が下がり、金利下降で価値が上がります。株価では価格の上昇で価値が上がり、価格の下落で価値が下がります。このように、債券・株式を取引した後で、市場の価格・金利が変動することでその資産価値が上がったり下がったりして変動します。また、外貨建てのローンや外国債券の取引では契約の開始時点と終了時点で外国為替の相場の違いにより為替損益が発生するため、為替リスクを内包した取引となります。又、市場金利が変動することで、固定金利の調達・運用は金利変動リスク(可能性としての)を発生させます。例えば、後で説明する"右肩上がりのイールドカーブ"の状況で、固定金利で長期の運用をしている場合、短期での調達をすることになりますが(ショート・ファンディング)、市場金利が変動して、長期金利のレベルまで短期金利が上昇することもありえます。この様な時、損失が発生します。従って、市場リスクを目に見える形で表現することは、ポジションを管理する上でも、これからリスクあるポジションを持とうとする人のためにも、重要になります。端的に、"市場リスク"を表現するものは"保有するポジションの含み損益"、つまり時価評価です。
ところで、債券取引・デリバティブ取引には取引所の中で取引きされるものと、店頭市場で相対に取引されるものがあります。前者の場合、取引所の中でその時の市況に合った公正な市場価格が形成されているものと考えられます。
保有する様々のポジションを評価することを考えた場合、"取引所取引市場"において価格形成された市場価格は、"一物一価"になると考えられますから、公正な価格形成が十分に期待できます。
一方、"店頭取引市場"における価格形成はどうでしょうか。一物百価になる可能性を含んでおり、「時価」を問題にした時の課題は大きいものがあります。しかし、相対ベースの取引とはいっても、近年はコンピューターの発達により、当該商品の参加者は情報端末の画面を通じて、適正な市場価格を容易に把握することができます。したがって、取引所商品同様、自己の保有するデリバティブ残高に対して常に市場リスクを負い評価されます。
取引所取引であれ店頭取引であれ、確かに市場価格は形成されるが、この価格がどのように導かれたものかを検証できなければ、不正な価格(高値で買わされたり、安値で売らされてりする)形成に対して対応できません。すなわち、市場リスクを取引時において負うことになります。時価評価の必要性が、ここに在ります。現物取引に限らず、デリバティブ取引においても、時価評価を行う能力が"リスク管理"の基礎となります。時価評価をベースにして、10bp-Delta、グリッド・センシティビティ等の管理手法などにも広く使われています。また、VAR(バリュウ・アット・リスク)では、"時価評価"は過去の価格変動性を統計学的手法を使って、算出されます。それは、特定の保有期間に、特定の確率の範囲内において市場が不利に動いた場合に予想される"最大損失額"として表現されます。
ところで、 デリバティブ取引が市場性を有している限り、市場リスクにさらされています。結果として、自己の所有するデリバティブの持ち高(残高)に対して市場リスク(マーケットリスク)が存在します。
デリバティブの市場リスクを考える場合、「レバレッジ作用」の存在が重要となってきます。オプション取引においては、ブラック・ショールズモデルあるいはバイノミアルモデルを用いてプレミアムの価格設定が行われるのがほとんどです。
オプション取引の場合はプレミアムの価格のみならず、オプション取引の対象商品の時価も把握しておく必要があります。したがって、市場リスクを把握するのに必要な概念は後で説明しますが、その他にデルタ、ガンマ、セータ、ベガなどがあります。
|
〈注〉金利変動の影響分析に使用する代表的指標
|
|
デルタ(デューレーション)
|
対象商品価格の変化によるプレミアムの変化率
|
|
ガンマ(コンベクシティ)
|
対象商品価格の変化によりデルタの変動率
|
|
ベガ
|
ボラティリティの変化によるプレミアムの変動率
|
|
セータ
|
時間の変化によるプレミアムの変化率
|
|
ロー
|
オプションの価値に使われる割引率(リスク・フリー・レート)の変化による価格変動リスク
|
|
ベーシス(コリレーション)
|
例えば、CP・CD・短プラ等の金利指標とLIBORとのスプレッドの変化による価格変動リスク。金利スワップのへッジを債券先物・金利先物等の類似商品で行う場合には注意が必要です
|
スワップ取引においても、現在価値を導くための概念として「スポット・レート」「フォワード・レート」などは現場のディーラーにとっては不可欠です。さらに、本来のリスク全体を把握・管理し、いろいろな局面に対処するためには、「再構築コスト」
(次の"信用リスク"参照)の知識は不可欠といえます。これは市場リスクそのものだからです。
このようにオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引には、これまでの金融取引の市場リスクを把握する概念とは異なるデルタ、ガンマ、セータ、ベガあるいは再構築コストなどが入ってきます。これらはデリバティブの特性としてのレバレッジと密接な関係があります。
また、オフバランスの取引であるがためのリスクが存在します。約定(契約)時から受渡日迄の時間的空白時においても、市場リスクにさらされていることに注意しなければなりません。
一方、コンピューターの発達と取引技法の発達によって、相場の変動は、次に説明する"変動要因"以外にデリバティブの影響は無視できません。取引を行う上でこれらの技法及びそのリスクの存在に限らず、リスク管理の必要性から発生する取引があることを理解しなければ思わぬ損失を招きます。特に最近のIRSの取引は、ポジションリスク調整目的が大半ではないかと思われます。
2)信用リスク
今日の社会は双方の合意のもとでの契約をベースにして成り立っています。契約社会では、相手を「信用する」という基本的合意の上で成り立っていると考えられます。従って、その意志を明確にし、確認のための契約書等の諸々の書類が存在します。これらは、全て「信用」という秩序の中で成り立っていると言えます。
これを前提にして、取引を実行し継続するわけですが、環境・状況の変化によってその履行が不完全な状態に陥ることがあります。
その原因とされるものは様々考えられますが、法人間の取引の場合、すぐに思い浮かぶのは取引相手の倒産です。ここで、「信用リスク」について考えてみましょう。たとえば、A銀行とB企業がある金融取引を行っていたとしてかんがえて下さい。①A銀行がB企業に対して貸付けた資金がBの倒産のために回収不能になった場合です。この時、AのBに対する「信用リスクの存在」ということを誰もが考えるでしょう。
②一方、Bという企業がAという銀行に預金したが、Aという銀行の倒産によって預金が返って来ないことがありえます。今後、この現象が多く見られる事でしょう。とくに、預金保険の対象外の場合は特にありえます。これも「信用リスク」です。
「信用リスク」とは、『取引を実行をしても完了するまでの間に環境の変化等によって最終的に履行できない結果、当該取引が、損失を被る可能性にさらされている状態』ということができます。
信用リスクが伴うもとのして、一般の金融取引においては、資金調達・資金運用及び証券売買が考えられます。例えば、借入人が契約満了日に借入金を返済できなくなるリスクが信用リスクです。それは、融資取引の際、貸付金全額が信用リスクにさらされています。これは契約開始後契約満了日までの間、経営環境の変化によって生じる可能性があるからです。反対に、金融機関間の預金預託の場合も同様です。これらは、信用を与える側がこのリスクを負担しています。その見返りとして、そのリスクに見合う分の利益(ローン・スプレッド等)を要求する取引だとも考えられます。この利益を計る基準として各格付機関のレートが参考となります。
取引所取引のデリバティブ取引(短期金利先物・債券先物)の場合には、取引の相手方が証拠金制度によって守られている取引所そのものであるため、債務不履行の可能性は無いと考えられています。デリバティブ取引で『信用リスク』が問題とされるのは店頭取引(金利スワップ・FRA・金利オプション)に限られます。店頭取引の場合には、相手側に対する与信が伴うために一般の金融取引と同様に取引約定から受渡決済日迄の時間が有るために信用リスクにさらされています。
しかし、取引金額(名目元本)が全額『信用リスク』にさらされているというケースはあまり在りません。基本的に元本の受渡しがなされてないからです。
デリバティブ取引においては、相対取引をしている当事者の一方が信用を与えているのではなく、双方が契約に基づく債務を負っています。その意味で双務契約といえます。ここにデリバティブ取引における『信用リスク』の特徴があります。
又、そのリスク額は、前述の市場リスク額に等しいものと言えます。双務契約ですから、取引相手方が被った"損失額"は自らの"利益額"になるはずです。その利益額が相手方の債務不履行によって実現できずに終わるからです。一般的に、市場性のある商品の信用リスクは、市場リスク管理でいう『保有するポジションの時価』に他なりません。しかし、市場リスクでいう時価と区別するために『再構築コスト』と呼ばれています。
たとえば、名目元本100億円の金利スワップ取引きを行った場合、100億円がすべて信用リスクにさらされることはありません。信用リスク額は与信相当額と言われる部分だけに限定されます。
また、オプション取引においても、プレミアム支払いという債務と契約の条件のもとでの特定金額の支払いという債務の交換といえますから、双務契約といえます。オプション取引の『信用リスク』はこの"プレミアム"と"正の再構築コスト"分だけとなります。取引上の名目元本全額が信用リスクにさらされることにはなりません。"正の再構築コスト"とは、時価評価と同じです。同じポジションを市場レートでもう一度作り直すことですから、その時点でポジションを評価したものと同じになります。
多くの人が、デリバティブ取引における"信用リスク"を考える時、名目元本の大きさに目を奪われ、融資取引などと同等の信用リスクが存在するかのように誤解しがちです。取引元本それ自体が全部信用リスクと考えるべきなのかどうかという点について十分留意すべきです。
3)流動性リスク
流動性リスクは、①リクイディティ・リスクと②アベイラビリティ・リスクに分けられます。金融資産を処理する市場の有無と取引する当事者の問題に起因する場合で分けられます。
① リクイディティ・リスク
保有している金融資産を処分したいと思った時にいつでも処分できる市場が存在しているかどうかという問題です。つまり取引所取引であれ店頭取引であれ、取引を実行するのに十分な規模を備えた市場が存在しているかどうかというリスクを指しています。市場の参加者の数・取引量が少ないために、市場環境の急激な変化があったときに保有するポジションを迅速且つ適正な価格で処分する事が出来ないリスクをさします。市場の急変時の際相場が一方向に傾いたり、特殊な取引をしたためにポジションをクローズ(解消)出来ない場合に問題となります。金融政策の変更、へッジファンド等、大玉の処理のため、デリバティブポジションの解消等特殊な要因によって日常的にその幅は小さくとも起きる可能性があります。この内、戦争の勃発・政治経済の大事件等によって市場が麻痺状態になってその機能を失うリスクを"システム・リスク"と呼びます。このリスクについては後述します。
たとえば、東京証券取引所に上場されている株式はどうでしょうか。投資家は値段さえ気にしなければいつでも買いたい会社の株式を購入でき、売りたいときにはいつでも処分できる状態にあります。このような場合に、流動性リスクは存在しません。しかし、未上場の株式の場合は多少事情が違ってきます。未上場株式などの場合は限定された範囲内で株式を持ち合っているケースが多く、売却処分したいと思っても限定された範囲内の株主の中で取得したいと思う者がいなかった場合は売却処分できなくなってしまいます。このような時、流動性リスクが存在するといえます。
流動性の少ない金融商品を対象に投資や投機をすると、そのへッジ取引が有効且つ迅速に行えるかどうかがポイントになります。その時、市場で吸収してくれる業者および取引の存在が、流動性リスクを回避する最大のポイントとも言えます。
市場の規模(取引量)を把握して、自己のポジションとの比較を常にしておくことが、管理方法として必要となります。
② アベイラビリティ・リスク
手元資金が減少して取引の決済が滞る場合とか最近のようにジャパン・プレミアムが広がって市場としては機能していても自己の評価が下がる事で思わぬコストを払わされることも、場合によっては調達が出来ない事もありえます。このようなリスクに対処するためには、自己の正確な評価を知ること(自己管理)及びそのポジションを見直ししてアセットを縮小する等の対応が必要になります。
4)決済リスク
金融取引の決済は、市場での外国為替取引・資金取引における受渡し決済は翌日もしくは翌々日になっています。ただし、オーバーナイトの取引は当日が決済日となります。日本の短期金融市場のコール・手形は基本的に当日が基本です。日本の株式取引においては、4日目に売買代金と売買株券の受渡し決済が行われています。
特に、リスクとして問題となるのは、外国為替取引・通貨スワップ等の元本決済のときです。
例えば、外国為替で米ドル買い円売りの取引においては、受渡日を18日としても円の支払いが先に実行され、米ドルの受取りは米国時間になってしまいます。(東京デリバリーとして一部の米銀が東京タイムで決済する事に御応じています。)このように約定から決済までの間に時間が存在するために、決済時まで契約当事者の一方が決済不可能となる事態が発生する可能性もあります。外国為替については『外国為替基礎講座』を御覧ください。
この様なリスクは、資金決済の金額を、ネッティングなどの方法で少なくする事で防ぐ必要があります。
近年、日本では、日銀ネットシステム、証券振替決済システムなどの導入により、受渡しに伴う事務的な決済リスクの軽減が図られています。
デリバティブ取引における特有の決済リスクの対応として「差金決済」があります。FRAやFXA取引は差金決済などを禁じる刑法との関係で、日本国内での取引がなかなか認知してもらえなかったが、法整備によって1994年10月に取引が認められるようになりました。
5)法的リスク(リーガルリスク)
金融取引で、当初意図していた契約内容が実現出来なくなった時、まず持ち出されるのが契約書です。この契約書の内容について裁判等で争われます。特に、相手方がデフォルト(債務不履行)を起こしたときに取引の清算方法の取り扱いが問題となります。また、契約書の中の裁判管轄権がどこになるかの説明にスペースを費やされています。係争になった場合の事を想定しているためと思われます。しかし、大半の取引は裁判所に持ち込まれる手前で円滑に処理されます。
ここで言う法的リスクとは、対象商品の経済効果や契約書の権利義務関係について法律的な取り扱いが不明確なため、当初期待した経済的・法律的効果が得られない、または損失を被るリスクを指します。しかし契約書が完璧でも、取り扱い商品がほかの法律に抵触するようなケースもあります。契約当事者が、行為能力の範囲を超えて取引を継続的にしていた場合が上げられ、この場合は代理権限の範囲を超えた場合でも民法上の表見代理の拡大解釈によって解決される事が多いようです。
デリバティブ取引において、リーガルリスクを考える時に、一般的に取引所取引のリーガルリスクはほとんど存在しないと考えられます。取引所取引の場合は、取引が定型化されており、法的な面でも事前に取引所と業者の間で取引ルールが確立しているからです。
ところで、デリバティブ取引において、新しい取引形態で元来日本に存在しないために法的な整備が不十分な取引については留意する必要があります。先物取引、オプション取引、あるいはスワップ取引のどれをとっても差金決済的なものが多く、刑法の185条と186条の賭博罪に関係する法の抵触の問題が残ったままです。(FRA、FXAは94年10月にようやく解禁にとなりましたが、日本では、その取引の責任問題を裁判で争ったことがありません。)
ところで、スワップ取引の多くをカバーしているISDA(国際スワップデリバティブズ協会 International Swap Derivatives Association)が作成したマスター契約書の存在があります。この契約書と日本における破産法との関係など取引の実態と法律的な解釈で不明瞭な問題が残っています。
国際スワップ・デリバティブ協会/ISDA, International Swaps and Derivatives Association
6) 会計・税務リスク
デリバティブ取引について、会計・税法に関する指針やルールが確定していないために、契約実行時、意図していた内容を実現出来ないまたは損失を被る可能性があります。この様なリスクを、会計・税務リスクといいます。
例えば、海外と取引をした場合、おたがいの国の税制や金利規制の違いにより源泉税が課されたり適用金利に制限が加えられる可能性があります。また、損益の認識について、時価会計ベースなのか、取得原価方式なのか、またはへッジ会計が制度的に導入されているかどうか等、国による違いを認識する必要があります。
思わぬ損失をしないためにも、我が国の制度とともにその国ごとに調べておく必要があります。上記のリーガル・リスクと同様に、当事者とは異なる利害関係の無い専門家のアドバイスを得る事もその管理のために必要です。
7)オペレーション・リスク
機械と違い、人間の介在するところには何らかのミスが発生します。完全な人間はいません。人間の冒す誤りを少しでもなくすために、機械の導入・事務管理の責任の明確化・その責任体制の明文規程の作成・維持体制の無駄のスリム化・命令指揮系統の簡素化等、こんにちまで色々な工夫がされてきました。それでも、考えられない単純なミスは絶えません。
日本では、基本的に事務管理のセクションに限らず全ての機構が"減点法"によって評価され組織が築かれています。
一方、欧米では、人は間違いを冒すことが当たり前であることを前提に組織を作っています。この間違いの少ない優秀な人材を集めておき(間違いの多い人は採用の対象外)、さまざまなミスを処理出来るひとに対して良い評価をあたえます。ミスを少なくすることは当たり前として、問題の対処能力を評価の対象としています。
この様な人材の組織であれば、命令・指揮系統の責任は明確になります。少ない人数で効果的な組織を作ることが出来ます。日本的な方式が勝っているかどうかは議論の残るところです。
それはさておき、オペレーション・リスクは、事務管理のミス、コンピューター・システムの故障による場合・リスク管理のためのコンピューター・システムのプログラムミスにより『市場リスク』等が把握できなかった場合・単純なコンピューターへの入力ミス等に起因するリスクです。
まず、市場取引は電話で行われる事が多いため、約定締結時点では、約定値段や、売りか買いかの約定ミスが起こりやすい。次に締結価格を提示する際に起こりやすいのがプライシングミスと呼ばれるものです。そして、締結条件をコンピューターに入力するときミスの起こり安い。こうしたミスが取引金額の間違い、顧客コードの間違いによる取引相手先の取り違えなどを誘発することになります。
さらに、ディーラーのオペレーションミスの中で最も怖いのが、ヘッジ取引のつもりがヘッジ取引ではなく反対にポジションの倍増を招くこともあります。
あるいは市場リスクの把握の際、ヘッジ比率の計算ミスによるリスクの増大ということもありえます。
このように、取引を完結するまで、オペレーション・ミスは様々のところで発生します。
最近、この様なリスクの集中管理のために、独立した『ミドル・オフィス』及び『コンプライアンス・オフィサー』の必要性が叫ばれています。欧米は別として、日本でも一部の企業で"日本的"に導入されています。
8)システミック・リスク
戦争の勃発・政治経済上の重大な出来事(政変等)・主要金融機関の倒産等、異常事態が発生した結果、その金融市場全体だけでなく社会体制にまでも影響が及び、金融システム全体の安全性が損なわれてしまうようなリスクをシステミックリスクと呼んでいます。このシステミック・リスクは金融取引における究極的なリスクといえます。それは、『金融システム』全体に及ぶ問題というよりも、今日の『社会システム』そのものに及ぶ問題といっても間違いがありません。これまで触れてきたリスクは、金融システムのごく一部で発生し、それは何らかの形で吸収されてしまう程度のものとすれば、システミック・リスクは"社会"そのものの問題となる可能性を秘めたものだからです。
金融取引に携わる人々にとって、種々のリスクをあるときは回避し、ある時は積極的に組み込み、上手にマネジメントしていく"責任"があります。この様なリスクに対処するために、「ストレス・シュミレーション」による分析が活発になされています。これは、ある意味で、過去の歴史に学んでいるといえます。『温故知新』の必要性が認識され再検討されるべきる時代を象徴しているのかもしれません。
9)人的リスク
人的リスクに言及する時、まず、200年の老舗ベアリング社を消滅させたMr.ローソンや住友商事・大和銀行等の事件等が思い出されます。このとき、特定の個人に対して経営陣の理解度、関与度が問題にされました。一般的には、経営陣を含めた管理者(マネージメント)の管理体制の在り方、管理者の人材としてみたときの質、責任の取り方を含めた偉大なる"常識"が問われます。しかし、ここでは、むしろ、ディーラーなり、ミドル・オフィス、バック・オフィスで仕事している人々の『人的リスク』を取上げます。オペレーション・リスクを伴うこともありますが、ある金融取引に携わる人々が、チームごと他社に移ってしまうようなリスクです。この結果これまで蓄積してきたノウハウはすべて中断を余儀なくされ、金融取引体制を再度構築するためには、それまで以上のコストと時間がかかることになります。雇用体系、給与体系等人の処遇問題の改善と対応が必要となります。
(3)リスクの計量化とコントロール
この第一部では、リスクの存在を理解して頂ければ十分です。リスク管理の為の計量化、管理手法、については、別の機会にしたいと思います。
[8] 金利相場の変動要因
市場性のある相場の今後の動きを分析・予想するための方法として、ファンダメンタルズ分析(実体要因分析)とテクニカル分析の二つの方法があります。
ファンダメンタルズ分析とは、日本・米国・欧州・アジア・北米・南米等の国際経済を取り巻く経済状況及びその経済実態等を調べ、これを受けた各国の経済政策の動向を調査・研究することにより、今後の相場動向を考える上で、どのような影響が及ぼされてくるかを分析するものです。
国際経済を見ると、経済ブロック(経済圏)は大きくⅠ.北米ブロックⅡ.欧州ブロックⅢ.アジアブロックの三つに分けられます。経済政策で共通点があり、地理的にも接近しており、企業等の経済活動に相互依存の関係が認められる国々を整理した区分です。その他南米諸国・中東・ロシアの諸国は基本的に、石油・鉱石・コーヒー・等第一次産品の輸出国で、過去の政治的・軍事的な背景を基に経済規模の大きさを勘案すると、北米ないしは欧州ブロックに吸収して把握することで十分であると考えます。ただし、ロシア等旧ソビエト諸国については、経済力の大きさとしてよりも、軍事的色彩が強くその影響力の大きさの方が問題となります。地理的にも、企業活動の範囲としてはやはり欧州ブロックの一部として、捉えるべきでしょう。中国・インドについては、経済力・政治力を考えねばなりませんが、現状であまった資金の運用等中東諸国・ロシアほど戦略的に運用するというよりも、欧米諸国の規範の範疇に入っていると考えてよいと思われます。中東諸国・ロシアにつきましては、政府系ファンドとして問題となっていますが、数十年先を見た戦略で動いていることを警戒する必要があります。歴史的な背景を無視するわけにいきません。とはいっても、金融市場の整備ができているかどうかがその鍵となります。金融ハブとして・・・。
|
Ⅰ.北米ブロック:
|
アメリカ・カナダ・メキシコを中心にした地域。
|
|
Ⅱ.欧州ブロック:
|
イギリスを含む・ドイツ・フランス等のヨーロッパ諸国を中心にした地域。
|
|
Ⅲ.アジアブロック:
|
日本・中国・韓国・東南アジア諸国・オセアニア諸国を中心にした地域。
|
これらの地域の中で、経済の依存度・経済規模を考慮すると、日本・アメリカ・イギリス・ドイツ等の主要な経済大国の経済分析を利用する事で、とりあえずは相場を判断するには十分と思われます。
一昔前に比べて、経済活動のグローバル化・規制の及ばない金融のグローバル化が進み、国際経済は複雑に絡みあってきており、単純に一元的に捉える事は得策ではありません。経験的に、トレーディングする際には、その時々のマスメディアのニュース・取り扱う金融商品のマーケットでのトピックを参考にしながらも、客観的に分析されたファンダメンタル分析の結果(政府系・民間の各経済研究機関および研究所から様々のものが公表されている)を利用して、複眼的にストラテジーを組む事が大切です。
しかし、さまざまな経済分析の中で注目される"銘柄"がその時々で違ってきます。米国のFRB議長・グリーンスパーンの様な主要人物の発言に注目し、彼らの関心の強い経済指標・個別の国を中心に活用する必要があります。
テクニカル分析とは、過去の相場の動きをチャート等によって目にみえる形(グラフ)で表現して、その形状によって今後の相場の動きを把握・予想しようとするものです。過去のその時々の経済状況は全て捨象されたものとして取り扱います。そして、過去のデータから予想されうる様々のテクニカル分析手法の中からその金融商品に適した手法を選択する事で利用されています。
人類の歴史を長い目で見ると、時代背景は違っても"歴史は繰り返される "事実は明白です。この様な歴史を繰り返さないために国際的な機構が作られては解散することの繰り返しが歴史です。
それはさておき、コンピューター技術の発展とシステム取引の開発及びデリバティブ商品の普及により、テクニカル分析の手法はその仕組に組み込まれる段階まで進んでいます。ジョウジ・ソロスに代表されるへッジ・ファンドはこの様な最新の技術を取引に導入しています。大口の取引をするためには、欠くべからざるものとなっています。従って、システムリスクで説明したような特殊な出来事が無い限り、チャート分析に従った相場の動きになる傾向があります。
このテクニカル分析につきましては、『テクニカル分析』を参考にしてください。
ここでは、ファンダメンタルズ分析に主眼を置き、『長期金利の相場』を念頭におきながら変動要因について説明していくことにします。
現在の金利相場に大きく影響を与える変動要因として、次の項目を挙げることができます。順次、以下の項目について考えて行きましょう。
|
(1)国内景気と金利
(2)日本の金融・財政政策と国内金利
(3)米国・欧州等主要国の景気と金利
(4)外国為替と金利
(5)金融商品(特に債券)の需給と金利
(6)金融商品間の裁定とリスク管理
(7)その他の特殊な変動要因
|
ただし、どれかひとつの要因が単独で影響を与えることはまれです。その時どきの相場状況によっていくつかの要因が絡み合って、複合的に相場が形成されていくと考えた方が良いようです。
(1)国内景気と金利
国内景気と金利との間には、景気の上昇局面と下降局面に分けて考えると、次のような関連が見られます。
1)景気上昇局面では、
景気が上昇局面にあると誰もが考えてはじめたときには、企業の収益が好調に伸び、個人の所得は増える事が予想されます。この時、一般的にはマクロ的に"消費・企業の投資"の増加、すなわち有効需要の増大がもたらされるものと予想されます。
それは企業の設備投資ニーズ等の増加をよび、ひいては資金需要の増大に結びつくことになります。そして、その時の状況からさらに資金需給の切迫が予想されると各金融商品の金利は上昇することになります。
また、それは、資金需要の増大がマネーサプライの増加をよび、これが物価上昇懸念を呼び、市場金利の上昇につながると考えることもできます。
2)景気下降局面では、
景気下降局面にあると誰もが考えはじめたときには、景気上昇局面とは反対に、企業の収益が伸び悩みとなり、個人の所得は頭打ちになるだろうと予想されます。この時、"消費・企業の投資"の減少、すなわち有効需要の縮小がもたらされるものと予想されます。
それは、企業の設備投資マインドを冷やし、ひいては資金需要の縮小に結び付くことにになります。そして、その時の状況からさらに後ろ向きの資金需要しか求められなくなると、各金融商品の金利は低下することになります。
また、それは、資金需要の縮小がマネーサプライの減少を呼び、これが物価下落を連想をすることになり、市場金利の低下につながっていくものと考えることもできます。
(2)日本の金融・財政政策と国内金利
日本の金融政策及び財政政策は、国内の短期・長期の金利に影響を与える重要な要因の一つです。
1)日本の金融政策と金利
日本の金融政策については、前述の"金利体系"等の項目で説明しますが、短期・長期金利に及ぼす影響としては、次のような関連が考えられます。ア)金融緩和時 、イ)金融引き締め時に区分して説明します。
ア) 金融緩和政策と金利のメカニズム
金融緩和政策は、国際経済、特に国内の経済状況が弱く、景気状況がますます悪くなるのではと予想される時に、金融当局により発動されるものです。
まず、金融当局つまり日本銀行による"公定歩合"の引き下げが考えられます。日本銀行は公定歩合を引き下げるか、引き下げた時と同じ効果のある"準備預金率の引き下げ"または"金利の低め誘導"―――(公定歩合の水準以下に市中金利を誘導するため、コール金利・手形・国債・CD・CP等を買い上げ『買いオペレーション』をして市中に資金を放出することで市場金利を低めにもって行く金融政策)―――を行います。
これは、経済の潤滑油としての円資金を金利を低くして供給することを目的にしています。このようにマネーサプライが増大すると、日本銀行の潤沢な資金供給を背景に市中銀行間の貸出競争が激化する可能性が出てくることが期待されます。経済状況が底入れから脱するまで、資金需要は資金供給よりもまだ小さいものと考えられますからさらに金利は低下することになる。経済状況が、底入れを脱してテイクオフ(脱出)したと考えられるまで続けられます。景気浮揚策の一手段ですから…。
|
公定歩合引き下げ→マネーサプライ増大→銀行間貸出競争激化→金利低下
|
イ) 金融引締め政策と金利のメカニズム
金融引き締め政策は、経済状況がやや過熱気味になっており、景気が好転からバブルぎみになって、物価が上昇しはじめ、今後さらにその悪化が予想される時に、発動されます。金融当局(日本銀行)は、この様な過熱気味の経済状況が今後長く続くと判断した時には、金融政策として"引き締め気味に"舵取りを始めます。
まず、金融当局(日本銀行)による公定歩合引き上げが考えられます。日本銀行は、公定歩合を引き上げるか、引き上げた時と同じ効果のある"準備預金率の引上げ"または"金利の高め誘導"―――(公定歩合の水準以上に市中金利を誘導するために、コール金利・手形・国債・CD・CP等を売り『売りオペ』をして市中から資金を吸収することで、市場金利を高めに持っていく金融政策)―――を状況を総合的に考慮して実施します。このように資金が吸い上げられ、マネーサプライが減少すれば、インターバンク(金融の卸売り市場)において資金供給がタイトとなってきます。経済状況が過熱気味の状況からやや落ち着くまでの間、資金の需要と供給のバランスが崩れ、資金需要が、資金供給よりも大きくなるものと考えられますから金利はさらに上昇することになります。金融引締めは、景気抑制策の一手段ですから…。
|
公定歩合引き上げ→マネーサプライ減少→資金供給タイト→金利上昇
|
2) 日本の財政政策
日本に限らず、財政政策が発動される動機として、基本的には景気を刺激し拡大させるという目的が上げられます。景気刺激・拡大のために、その投資目標及び目的が具体的に策定(計画)されます。これに基づいて、公共事業が執行され道路・公園を始めとするさまざまな"社会資本"が築かれていきます。
また、欧米では既に経験済みですが、最近のように、大義名分は何であれ、『金融システム』の崩壊を防ぐ目的・経済の血液の循環である"金"の流れを止めないために、金融機関を対象として"実質的な公共投資"が行われることもあります。グローバル・スタンダードの観点からは、公明・正大・責任の所在のはっきりした"明朗会計"が望まれます。
この様な財政政策が実行されるためには、政府・地方公共団体は資金を調達する必要があります。この時発行されるのが債券(公共債・国債・地方債)です。税金収入の問題が何であれ、建設国債等名称が赤字国債となろうとも、本来の目的は景気拡大・維持にあります。
それはさておき、財政政策が、短期・長期金利に及ぼす影響として、次のような関連性が考えられます。ア)債券市場の需給との関連とイ)景気動向からの間接的な影響の二つが考えられます。
ア) 債券市場の需給との関連
国及び地方公共団体が財政政策を発動し実施するためには、財政資金が必要となります。この財政資金を調達する手段として、国債・地方債等の債券の増発が考えられます。しかし、この増発が債券市場にとって、その市場環境によっては、需給悪化につながる可能性があます。また一時好景気の時にいわれたように、大型の借換え国債発行によって市場から資金吸収が行われ民間企業に資金が回らない現象(クラウディングアウト)が、起こる可能性があると考えられて、長期金利が上昇することもあります。しかし、この時には、国内の債券の運用残高が少なく相対的な市場規模に問題がありました。やや、"後付けの理由"と言えなくはありません。
|
財政政策発動 → 新規債券の増発 → 債券需給の悪化 → 長期金利上昇
|
イ) 景気動向からの間接的な影響
国または地方公共団体の財政政策の発動による公共投資の効果・目的として、国内の雇用創設と民間企業の業績の回復があります。景気の回復が最終目標ですから。
しかし、その景気回復が急な場合、後で説明しますが、"イールドカーブ"がスティーブな時、外国為替などの外部要因が無ければ、一般的に労働者の需給関係が逼迫してきて、労働賃金が上昇してきます。一方、民間企業にとっては、国内の景気が回復すると、一般の消費が増え引いては民間企業の収益の増加に結び付きます。また、企業サイドから見て、今後、その事業収益の継続及びその事業拡大の見込みがあり増収が見込めると判断される時には、全般的に、新たなる設備投資の意欲が増してきます。持続的に、且つ急速にこの様な内需拡大の可能性があると判断される時、経済の拡大再生産(景気上昇)は、必然的に短期の資金需要に限らず、長期の金利は上昇することになります。
|
財政政策発動 → 内需拡大 → 景気上昇 →短期・長期金利上昇
|
(3)米国・欧州等主要国の景気と金利
金利の変動要因として米国・欧州等の主要国の経済状況が上げられます。
基本的に、『金』に色はありません。金利の高い、つまり収益性を求めて、そのリスクを考えながら動く資金運用ファンドもあります。又、安全性・流動性をベースに、"確実な運用"を目指す日本の大半の金融機関が運用するファンドもあります。運用(ファンド)を考えた場合、資金の『安全性・流動性・収益性』のどの部分に比重を置くかによってリスクとリターンが違ってきます。その目指す目標によってファンドが組まれているわけです。
それはさておき、世界中に存在する投資家は、リスクの所在(リスク管理の必要性)を認識しながらも『安全性・流動性・収益性』を考慮して最大の"収益性"を追求しています。彼らは、それぞれのファンドの性格を認識した上で、投資の対象を決めて行きます。特に、『グローバル運用』の場合には、各国の経済・政治・軍事状況を分析の上、今後どのような変化(リスク)が生じるかを予想しながら判断していきます。ここで言う、『投資家』にはヘッジファンドの様な"錬金術"のプロフェショナルに限らず、一般企業の行動も含まれます。時にはそれが国家であることもあります。企業の海外投資・海外撤退は投資の対象及びその期間が違うだけで結果(金の移動)・効果は同じと考えられます。
彼らが、収益を確定させる時、新たにリスクが予想されて今運用している投資をクローズ(手仕舞う)する時、または新たな投資を考えた時など、国境を超えて資金が大きく移動します。その時、金融市場は変動します。その参加者は、自分の国と投資対象国の個々の分析と比較を通じて資金の流れ(どの国に資金が集まるか等)を読み、決断していきます。しかし、判断の材料は複雑です。
ここでは、主要国特にアメリカの経済状況が我が国の金利に及ぼす影響として取上げます。アメリカと日本との関係は、欧州諸国と違って、経済的・軍事的・政治的にもその貿易取引の割合、軍事基地の問題等から理解されるように相互依存の関係にあります。今後、資本の分散化が進みその"グローバル化"が進むものと考えられますが、現状では、アメリカを中心に考えれば、取りあえず十分と考えます。そこで、次のように、大きく三つの関連性が考えられます。1)アメリカの金利商品(投資対象としての)との関連性、2)通貨の交換比率といえる外国為替との」関連性、
3)対アメリカ貿易との関連性、です。
1) 投資対象としてのアメリカの金利商品との関連性
前述の『国内景気と金利』で説明したように、アメリカの景気が上昇局面にある時、アメリカ国内では資金需要の増大化が起こり、米国金利の上昇につながると考えられます。この時、金利のレベルがどうかが問題となりますが、投資対象として金利商品を考えることが出来ます。為替の問題を別とすれば、ドル資産への投資としての魅力が増すとともに、ドル資産への投資が活発化することになります。日本からのドル資産への投資が活発になるということは、国内サイドから見ると、円資金がドル資金へ移動することを意味します。当然国内の資金が消えているわけですから、国内はタイトな資金需給になります。対米ドル資産への相対的な資本流出防止という観点から日本の長期金利もこれに引きずられる形で上昇することが考えられます。これは空くまでも、対米投資が続く事が前提です。
反対に、アメリカ国内の景気が後退・下降局面になれば、ドル金利は下がることになります。そのことは、ドル資産への投資の観点からすると、魅力が減少し、投資の回収の時期にあるのではと考えるようになります。実際に、回収が始まるとドルを円に変えて運用することを考えるようになります。海外から円資金が戻ってくるわけですから、国内的には、資金のだぶつきから円の金利は下がることになります。ここでは、為替の影響が無いことを前提に考えています。
|
アメリカ景気→アメリカ国内資金需要→アメリカの金利上昇・下降→資本流出・流入→円の資金不足→短期・長期金利上昇・下降
|
2) 外国為替との関連性
外国為替の変動要因については『外国為替基礎講座』でも説明してますが、実際の市場では、色々な要因が絡み合って取引が行われています。ここでは、アメリカの景気と為替との関連だけに限定して考えます。通貨の交換比率といえる外国為替はアメリカと日本の景気状況が両天秤に掛けられて、これが均衡する水準で決まるものと考えられます。アメリカの景気が上昇する時、その時の日本の景気動向に変化が無いものと考えると、相対的にはアメリカ景気の力の方が強く感じられます。したがって、為替面では円に比べてアメリカ・ドルの方が強くなります。つまりドル高(円安)となります。これが、日本の短期・長期金利にとっては、マイナス要因(金利の上昇要因)として働きます。反対に、アメリカの景気が弱くなると、為替面では、相対的にドル安(円高)となります。この場合には、金利はプラス要因(金利の低下)として働きます。この点については、次の(D)外国為替と金利で説明します。
|
アメリカの景気→為替(円高、円安)→短期・長期金利上昇・低下
|
3) 対アメリカ貿易との関連性
アメリカは世界の工業国といわれてますが、一方で最大の消費国です。アメリカの景気が上昇するということは、アメリカ国内の消費が拡大することとつながってきます。一方、日本にとって最大の貿易相手国はアメリカです。対米輸出が増加することになれば、日本の景気上昇につながってきます。ひいては、日本の短期・長期の金利上昇に及んでくる可能性があります。反対に、アメリカの景気が下降局面にある時は、日本の景気にとってマイナスに働きますから、金利は下がることになります。
|
アメリカの景気→アメリカ国内の消費拡大・縮小→対米輸出増加・減少→日本景気上昇・下降→短期・長期金利上昇・下降
|
(4)外国為替と金利
外国為替の変動要因については、『外国為替基礎講座』にも説明してますが、大きくその変動要因を捉えると、外国為替と金利と景気と物価の四つの要素が考えられます。そして、それそれが相互に関連性を持っており影響し合っている構図が考えられます。又、外国為替は、この講座で取上げている債券等の金利相場以外にも株式相場・商品相場との間にもその関連性が見られます。
ここでは、日本を中心にして外国為替と金利との関連性を考えます。
その外国為替が金利に及ぼす影響として、次のような三つの関連性が考えられます。1)国内物価との関連性、2)国内景気との関連性、3)運用・投資資産としての価値との関連性、です。
1) 国内物価との関連性(輸入面)
外国為替相場で各種通貨を相対的に見て、円高となっている時を想定してみます。円高となっている時、海外から輸入する品物の価格は、円高になる前に比べて、安くなります。円から支払いのための対象通貨を手に入れる費用が円高のおかげで少なくて済むからです。特に原油・鉄鉱石等の原材料、小麦・トウモロコシ・大豆等の食料原材料の価格は安くなります。原材料に限らず完成品の輸入価格も安くなります。この効果が国内経済全般に及ぶようになると国内の卸売物価・消費者物価が下げの方向に向かいます。特に外国製品の輸入価格が低下し、国産商品との競合関係が成り立つようになると価格抑制効果が働くようになります。長い目で見ると、それはインフレ懸念の後退へと繋がります。そして、これが国内物価の低下、ひいては金利の低下に結び付くと考えることが出来ます。
反対に、円安のときには、原材料の高騰、外国製品価格の上昇を招き、価格抑制効果は働きませんから国内の製品価格は高くなります。円安が続くと、インフレ懸念の再燃が生じ、国内物価の上昇、ひいては金利の上昇へと結び付いていきます。
|
(輸入サイド)
円高 → 輸入価格の低下 → 国内物価の低下 → 金利の低下
円安 → 輸入価格の上昇 → 国内物価の上昇 → 金利の上昇
|
2)国内景気との関連性(輸出面)
まず、上述と同じように、相対的な円高を想定します。
円高となっている時、輸出サイドから見てみます。日本は資源が乏しく加工貿易を中心に経済が成り立っている状況は昔も今も変わりありません。輸出産業にとって円高は、最終の受取り通貨である円が少なくなることを意味しています。円の受取りを以前と同じにするためには、その製品の販売価格を上げるしかありません。しかし、競合する外国製品を抑えて価格競争をすることは難しくなります。そこで、企業は、コスト削減の努力をすることになりますが、日本の場合中小企業にそのつけを払わせることが恒例になっています。企業の70%が中小企業である実体は変わりませんから、その影響は国内景気に及んできます。輸出の販売数量は減少し、次第に国内景気を減退へと引きずり込むことになります。この時、国内景気を刺激・回復させるために財政・金融政策として金利が低くなることが予想されます。
数年前に『円高不況』が叫ばれたことを記憶している方々も多いことでしょう。この時の経験から、当時生き残った企業は、中小企業も含め国内から生産拠点を東南アジアを中心に移してきました。人件費、設備投資を含めコスト削減の目的で雪崩現象のように技術移転が進みました。国内産業の空洞化が叫ばれたのもこの時期です。しかし、残念ながら、1997年7月を境に東南アジアの通貨危機が叫ばれ、今に至っています。原因として、さまざまに議論されていますが、為替を中心に考えてみると、この円高とは反対の"円安"がこの時期から始まっています。そして、日本企業の資本回収が始まったのもこの時期です。そして、工場閉鎖移転が加速度的に行われてきました。アジア危機が問題となるのも納得出来ます。同一方向の行動が無ければこの様な危機には至らなかったものと考えられます。この影響が本体の日本経済まで及んでいることは、恐ろしいことです。バブル崩壊後の対処が遅れたことをその原因とするにはあまりに時間が経ち過ぎています。実は、この現象と同じことが、1980年代のアメリカとメキシコとの間ですでに起きています。"メキシコ危機"当時のアメリカの対処法は示唆に富むものと思われます。
それはさておき、円高とは反対の円安の場合を想定します。
円安のときには、輸出産業にとっては、円の受取りが多くなります。外国製品との価格競争の面でも優位に立ちますから、企業の生産意欲は増してきます。国内景気にとってはプラスに働きます。設備投資意欲がますます旺盛になりますから、その資金需要が出てきて、加速するようになると金利は引き上げられることになります。
最近の経済状況を考えると、バブル当時、国内・海外ともにその生産設備投資が過剰に行われたために、製品の供給過剰の状況が続き今に至っています。神の『見えざる手』ではないですが、世界全体の需要以上に物が生産された結果といえます。このような状況のとき、たとえ為替が円安に傾いてもその効果は日本経済に及ぶことはありません。したがって、金利にその影響が及ぶことはないと言えます。構造転換が叫ばれるのも、一方、生産設備の廃棄、ダウン・サイジングが議論されるのも納得が出来ます。問題は、その方法といえます。
|
(輸出サイド)
円高 → 価格競争力の低下 → 輸出低迷 → 国内景気の減退 → 金利低下
円安 → 価格競争力の上昇 → 輸出増加 → 国内景気の上昇 → 金利上昇
|
3) 運用・投資資産としての価値との関連性
運用・投資の対象として"円とUS$"の資産を見る時を考えます。ここでも、円高の場合を想定します。外国為替が円高に動いた時、『ドル資産の保有者』からすれば、基本的に円での受取りが多いいかどうかを判断の中心に据えますから、円ベースで見た時の資産の目減りが明らかになります。金利等のインカムゲイン以上に最終的な受取りが目減りして、元本割れとなることも考えられます。
この様な時には、損害を最小限に食い止めるために、為替のタイミングを見ながらロスカット(資産の処分)するか、為替先物予約の仕組を利用して為替の変動リスクをヘッジするか、または通貨先物・通貨オプションを利用するか、会計処理した上でも余裕があればその資産を塩漬けにするか等の判断が必要になります。あまり勧められる方法ではありませんが、"勇気をふるって"同じ資産に同額以上の投資を継続する方法もあります。特に、この投資方法を"ナンピン法"といいますが、相場について自信があるか、確かな情報を持っている時以外、基本的には"感"に頼った手法に過ぎませんから止めた方が良いと思われます。
ところで、見方を変えれば、この様に円高になることは、円資産の『相対的実質価値』が増えると考えることも出来ます。資金の運用・投資は基本的に、実質的な価値が大きい物に対して行う行為です。従ってこの場合、ドル等の海外資産から円資産へと資金のシフトが起こる可能性があります。この様な資金シフトが起こると円資産として最も流動性のある債券に対して需要がでてきます。債券の相場にとってその運用が増えることになりますから、金利は下がることが予想されます。
反対に、円安の場合には、相対的にドルの価値が上がり、一方円の価値が下がります。円資産に対する魅力がなくなりますからその資産の処分に走ることになります。ひいては、金利は上昇することが予想されます。
|
円高 → ドル資産の価値低下 → 円資産の相対的価値上昇→ 円資産への投資 → 金利低下
円安 → ドル資産の価値向上 → 円資産の相対的価値低下 → 円資産の処分 → 金利上昇
|
(5)金融商品(特に債券)の需給と金利
ここでは、債券を中心に説明します。債券の需給関係は、国債の供給と需要に分けて考えられます。
(供給面)
ここでは、国債に対する需要が一定であると仮定します。この時 国債発行量が減少すると、一定の需要に対して国債の供給が少なくなりますから、需要と供給のバランスが崩れ、需給関係は好転します。相対的に、需要が強くなりますから、例えば新規国債の発行は容易に御成なります。したがって、金利を若干下げてもマーケットで消化することができます。つまり、債券(国債)の利回りは、下がります。
一方、国債発行量が増加すると、国債の供給がその需要に比べて多くなりますから、需給関係は悪化します。従って、国債の新規発行条件をよくしないとマーケットでは、消化できなくなることになります。つまり、その利回りは、上がることになります。
|
国債発行量の減少 → 需給関係好転 → マーケットでの消化良好 → 金利低下
国債発行量の増加 → 需給関係悪化 → マーケットでの消化不良 → 金利上昇
|
(需要面)
ここでは、国債に対しての需要が増える場合として 、国債償還量が増加する場合と、国内に限らず海外からの国債への投資ば増える場合を考えます。
国債の償還量が増えるとき、すでに債券に投資している投資家が、彼のポートフォリオを変更する必要がないと判断したとき、償還分と同じ量の債券購入の必要性が生じます。この時債券の需給関係は好転しますから、相対的に金利は低下することになります。
また、国内に限らず海外の投資家が"利回り"意外に"安全性" "債券の流動性"の追求から日本の債券(円への回帰)への投資を考えるときがしばしば見られます。日本株への投資の待機資金としての一時的な投資も考えられます。このような理由による債券投資の需要がある時、その投資量が増加することになれば債券の需給関係は好転することになります。この時も相対的に金利は下がることになります。反対に、日本から資金が逃避するとき、債券以外の株式への投資が盛んになるとき、全体の資金量は変化ありませんから、債券を処分して他の金融資産へ資金が移動することになります。このような時、相対的に金利は上昇することになります。
|
国債償還量の増加 → 新たな債券購入の必要性が増加 → 債券の購入 → 金利低下
投資家の債券投資に対する需要の増加 → 債券の購入 → 金利低下
投資家による債権の処分の判断 → 債権処分(売却) → 金利上昇
|
(6)金融商品間の裁定とリスク管理
裁定取引(アービットラージ)とは、市場間または商品間の価格・金利に生じた一時的な歪みを利用して、取引を行うことでより少ないリスクで利益を得る取引です。
異なる市場間(現物市場と先物市場・東京市場とロンドン市場とアメリカの市場間)で生じる一時的な価格・金利のひずみを利用してリスク無しに利益を得る取引(狭義の裁定取引)、過去の経験と正確なデーターをもとに、先物の限月間及び現物と先物間の格差が一時的に乖離した場合や、将来その乖離が縮小または拡大するとの予想がかなりの確率である場合等、リスクはあっても乖離幅を利用して利益を得る取引(広義の裁定取引)があります。
一年以内の短期資金取引の場合、国内の短期金融市場の各金融商品間(たとえば手形とコールとの裁定取引、CDとCP、…)以外に、短期市場レートと外貨建ての預金金利またはインパクトローン金利との裁定が考えられます。この取引は、最近では、広く一般化しています。この取引の概要については『外国為替基礎講座第一部』「外貨預金」・「インパクトローン」に説明しています。参照してください。
ところで、基本的に、当該取引が短期であろうと長期であろうと相場である以上一定の水準に収まるものと考えられます。それは、さまざまな条件に変化がないと仮定した場合です。相場に限らず、ある事柄について"百家争鳴"のように複数の人々が集まると、それぞれ意見が違い論争が繰り返されます。しかし、時間が経ち内容・論点が整理されてくるとその意見は一つないし相対立する二つに集約されてきます。これに似ています。
しかし、実際にはそれぞれの条件に変化が生じて相場は変わってきます。このような相場の変化による"リスク"を避ける目的で各種金融先物を含むデリバティブ商品が開発されマーケットで取引されるようになりました。現代ではこのデリバティブ商品がリスクヘッジの目的以外に投機の対象として育つまでになっており、場合によっては現物のマーケットに大きな影響を与えることもしばしばあります。
これらの商品は、特にマーケット・リスクの計量化の目的で研究・開発されたものです。リスクの存在を計測し、そのリスクを軽減するためのマーケットの必要性から取引が始まっています。しかし、リスク軽減の効果以上に現物取引に比べて少ない資金量でより大きな利益を生む可能性があり、また取引慣行(ISDA)に従えば比較的簡単に取引できる利点があり、その取引量は増える傾向にあります。想定された元本は見た目よりも大きくなりますが、そのリスクはさほど大きくはありません。但し、取引した相手が"倒産しない"ということが当然の大前提として、その仕組みが出来上がっています。この点は、"経済の大変革のとき"忘れないようにしなければなりません。
また、当然、取引するためには、そのリスク管理のためのシステムおよびその知識が必要になります。最近、『リスク管理』の必要性が叫ばれるのは現物以上にその取引量が多く、コンピューターとそのシステムの精度に頼る部分も多く、また以前と比べてデリバティブのポジションによって各金融商品の相場が左右されることが多くなったことに起因しています。実際、世界の大手銀行・証券の想定元本の大きさはその国の国家予算の数倍という規模になっています。先ほども申し上げたように、そのリスクはそれほど大きくはありません。取引全体のポジションのリスクも想像されるほどではなく、また、基本的にこのデリバティブの取引に対して、他の金融商品でのリスクヘッジが、『裁定取引』と同様の手法を使ってほぼ同時に行われているのが実際です。『V・A・R』(バリュウ・アト・リスク)等の時価会計によるリスク管理の手法が研究・開発され、すでに1995年前後までには欧米の金融機関で実用化され、経営サイドに直結した管理部門に導入されています。日本では、BISの2次規制の対象として最近その対応が問題となりましたが……。
このリスク管理の強化は、ポジションの持ち方に限らず、そのトレーディングの手法・ヘッジの手法およびそのストラテジーの組方も以前とは異なるものにならざるを得ません。この点は別の機会にでも説明したいと思います。
ここで、いえることは、デリバティブの取引がリスク・ヘッジの手段として発生し、その規模がおおきくなった今ではその影響力を無視できなくなったと言うことです。リスク管理の理解とデリバティブの商品知識は、今後の相場展開を予想する上で大変重要になってきます。
(7)その他の特殊な変動要因
以上の変動要因以外に、次のようなものが考えられます。
1) クレジット・クランチ
基本的に、各金融商品に投資される全金融商品に対する割合は、そのポートフォリオによって決められています。特殊な要因、たとえば戦争・政変がなければその割合は変更されないものと考えて間違いありません。このような時、経済の立て直しのために、または地震・台風等の被災復興のために国債等の公共債が発行されることがあります。経済が良好なときには、この公社債が発行されるために、民間の資金需要が圧迫されると予想されることがあります。このような時、"クレジット・クランチ"の可能性が叫ばれます。債券の流通市場から見れば、一定の流通量以上に債券が発行されれば、その需給関係は悪化します。したがって、金利上昇のきっかけとなります。その上に、資金需要が好転することになれば、債券の購入サイドの銀行・生保は、ポートフォリオの変更を迫られ、新規の貸し出しのために債券の購入を手控え、場合によっては手持ちの債券を処分することになります。
しかし、金融当局は、一時的な金利上昇を押さえるためにマネーサプライを増加させる金融政策をとることが多く、最終的にはある一定の水準に収まります。全般的な金利水準が上がるときには、短期の金利、およびその資金供給量を窺つめに調整してきます。これが、サインです。
2)海外投資の需要拡大とジャパン・プレミアム
外貨を調達するには、外貨の直接借入と為替のスワップ取引・及び通貨スワップ(IRS)を利用した調達の方法が考えられます。外貨の直接借入には、直接金融市場から債券・株式を外貨建てで発行する方法と間接金融としての銀行から"インパクト・ローン"の形式等で借入れる方法が考えられます。しかし、ここでは日本サイドから見た手段として『円』の金利を考えるわけですから、その説明は別の項目に譲ります。
もう一つの方法として、外国為替のスワップ取引を利用した調達方法があります。これは、円資産を外国為替の手法で外貨資産に換える手段です。単純に外貨預金の手法の応用です。この場合、金利の利息部分の処理、または元本の為替の変動リスクの対応が問題となります。これに比べて、通貨スワップの手法はこれに見合う債券がある場合には、契約に基づいた相対する相手がいるためこのようなリスクはありません。『外国礎講座為替第二部』の『スワップ取引概念の見直し』を参照してください。
さておき、ここでは外貨の調達に外国為替・通貨スワップを利用した場合を考えます。日本の投資家から見ると、海外の資産への投資魅力が出てきたとき、つまり海外直接投資の需要が増加すること、または海外債券・株式投資の需要が増加するということは手持ちの円資金から外貨資金への交換が増えることを意味します。この時、円を売って外貨を買うこと(円投する)で外貨を手に入れることになります。銀行から見ると、それは『円』の預金口座の残高がマイナスになることを意味します。つまり、為替の決済のために円資産がなくなりますから、この銀行は短期金融市場から円資金を借入れるか、保有している債券を処分することになります。
金融市場からの借入のためには、特に日銀のオペに参加してより低い資金を手に入れるためには、国債などの担保が必要になります。この担保を入手するために債券市場から購入することになります。短期的には、債券現先市場の利用によって、債券を借入れる方法もあります。しかし、この時、長期的に預金等の新たな資金が入手できない場合には、自己のポートフォリオ上の貸付債権の回収か、運用資産の債券を処分することになります。自転車操業に過ぎませんから。
ところで、最近のように金融機関の不祥事が続きその財務内容・財務管理の不明確さが取りざたされ、格付け機関からそのレーティングが下げられ、その国際的評価が下がるようになると、関係した金融機関のみならず日本の金融機関全体が、世界の金融市場から締め出しを受けるようになります。
時価会計導入の遅れ・大蔵省を頂点にした護送船団方式の崩壊・財務に限らず人事管理および日本の経営体質、手法に対する不信・日本の常識は世界の非常識の露見・金満国日本の凋落…・・等々さまざまに表現されています。
金融市場から締め出しを受けるということは、特に資金取引の場合、取引がほとんどできない状態になる場合や取引ができても取引の際にそれ相当分のプレミアムが要求されます。この時、日本の銀行全体に対して、プレミアムが求められる状態を総称してジャパンプレミアムといいます。銀行の格付けによってそのプレミアム幅が違っています。したがって、銀行によってその調達コストはまちまちとなります。しかし、この金融市場で外貨が調達できない場合やそのコストが高い場合などのときには、外貨を手に入れる手段として外国為替の手段を使うしかありません。この方法では、常に為替のリスクが伴います。安定的な手段とはいえません。
そして、このプレミアムのつけは、当然のように、顧客に跳ね返ります。最終的に、誰が損をするかは明白となります。長期的には、これらの金融機関は、外貨建ての債権から利益を生むことができなくなりますから、その債権を放棄または処分することになります。それまでの間、前述の外貨の資金需要が増えるときと同様に国内の円資金に対する需要が、後ろ向きの需要が生じますから、金利にとって一時的に上昇要因・下降要因の相反する変動要因となります。
このように相反する可能性が考えられますが、全体の動きを注意深く見守る以外にはありません。
3) 安全資産運用
上述のように、さまざまな状況が不安定になると、日本の大半の投資家はその資金運用を考えるとき"リスクの少ない、利回りの安定した資産"の運用を考えるようになります。
『安全性・流動性・収益性』と投資対象のリスクとの比較をしながら、投資することが基本ですが、信頼の置ける判断基準が明確でないときには、安全性が投資の際その基準となります。『自己責任主義』が常識とされる欧米では、各個人および各企業は、正確な知識と公正な評価基準でそのリスクと収益性を評価する機関の資料を基にしてある程度のリスクを取りながら資産運用をしています。資産を増やすのも増やさないのもそれぞれの判断で成されることですから。残念ながら、日本にはこのような評価機関がまだ少ないのが実際です。
大半の投資家が安全性のみを求めるようになると、収益率は度返しにして流動性のある国債に投資の対象が集中してしまいます。最近の国債の状況がその一例といえます。ただし、次に説明するキャピタルゲインの追求の目的で取引をする投資家が多いことも事実ですが…。
4)インカムゲインとキャピタルゲイン
金融商品、実物資産によって得られる収益には、大きく分けて、インカムゲインとキャピタルゲインと呼ばれるものがあります。
インカムゲインとして、預貯金の利息・株の配当金・債券の配当収入などが考えられます。これらの例から分るようにある投資商品を所有している間に得られる投資収益です。
これに対して、株・金・不動産の値上り益のようにその投資商品を処分(売って)して初めて実現する投資収益のことをキャピタルゲインといいます。
いろいろな金融商品・実物資産はそも収益の特性によって、ア)インカムゲインだけの商品 イ)キャピタルゲインだけの商品 ウ)インカムゲイン・キャピタルゲインの両方の特性を持つ商品に分けることができます。
ア) インカムゲインだけの特性商品
固定金利型:預け入れた時点で、年率で見た収益が固定されているもの。
…銀行・郵便局の預貯金等。
変動金利型:預けられた時点ではその収益が確定しておらず、景気・金融政策等の要因で金利が変化するもの。
…貸付信託・金銭信託・投資信託等。
保険・年金の金融商品について:
一般的に、保険商品については値上り益を期待することはできません。契約の段階で決められた保険料に対して死亡・事故の場合に保険金が支払われたり配当金が支払われます。
また、年金商品については、同様に一定の年齢に達した段階で、一定額が終身及び契約の期間支払いがなされます。
保険・年金の配当・受取額はその引受会社の運用成績により逓増したり反対に逓減することもあります。しかし、このときこれらの商品自体が、値上りまたは値下がりするようなことはありません。したがって、インカムゲインの仲間とかんがえられます。
イ) キャピタルゲインだけの特性商品
キャピタルゲインだけの商品は、売買される特別の市場があり、値上りによってのみ収益が得られますが、反対に値下がりによる損失の可能性もあり、リスクが大きく投機性の強い商品といえます。
実物資産として、金・銀・銅・プラチナ等の貴金属がその代表です。ワラント・先物商品のような金融商品も考えられます。また、コモディティの商品相場の商品も考えられます。
絵画・骨董・不動産等を考えると、これらの商品には、独自に貸し付けによる運用があります。したがって、一般的には、つぎのインカムゲイン・キャピタルゲインの中に含めて考えるようです。
ウ)インカムゲインとキャピタルゲインの両特性商品
株・債券・為替・不動産・絵画・骨董がその代表です。
債券(国債・社債)の場合、インカムゲインはクーポン収入、キャピタルゲインはその価格の売買益といえます。株式の場合、インカムゲインは配当収入・株式分割等の収益です。不動産・絵画の場合は、動産・土地などの不動産の賃貸による賃貸収入をさします。
その商品の変動率によって、投資の対象としてインカムゲイン・キャピタルゲインのどちらに比重を置くかは違ってきます。
最近のように、あらゆる商品が上下に変動するようになると、インカムゲインを追求するよりもキャピタルゲインを求めたほうが有利なものが多くなりました。
株・債券は先物取引等のデリバティブ取引が発達し、信用取引を含む取引手法が開発され、売り買いともキャピタルゲインを得る機会が増えてきました。その分、そのリスクは大きいともいえます。
国際金利講座目次
金利相場の基本 第二部 荒巻 昌宏
|
[1] デリバティブ商品の金利概念の基本
|
|
(1) 概説
|
|
(2) デリバティブ取引の前提条件
|
|
(3)キャッシュ・フローの概念とIRR(内部収益率)
|
|
1) 単利・複利
|
|
2)金融取引の評価
|
|
ア)単利による価値評価
|
|
イ)複利による価値評価
|
|
3) キャッシュ・フローの価値
|
|
ア) 将来価値(FV: future value)
|
|
イ)現在価値(PV:present value)
|
|
4)NPV 正味現在価値(Net Present Value)
|
|
ア)NPVとは
|
|
イ)NPVの一般式
|
|
5)キャッシュ・フローの元利展開
|
|
(4)割引率について
|
|
~割引率の導出
|
|
1)パー・レート(スワップ・レート)
|
|
2)ゼロ・クーポン・レート(スポット・レート)
|
|
3)ディスカウント・ファクター(割引係数:Discount Factor)
|
|
4)フォワード・レート
|
|
|
|
[2] デリバティブ商品の金利
|
|
1) デリバティブとは
2) 短期金利先物
3) 債券先物
4) 金利スワップ(IRS)と通貨スワップ
5) FRA
|
|
6) 金利オプション
|
|
(a)金利の期間構造(イールド・カーブ)
|
|
(b)キャップとフロア
|
|
(c)プレミアム(オプションの価値)
|
|
(d)ボラティリティ
|
|
(e)スワップション
|
|
|
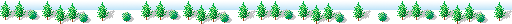
|
[1] デリバティブ商品の金利概念の基本
(1) 概説
通常一般の人々が考える金融取引は、自己の持つポートフォリオ(資産・負債)が今後どのくらいの割合で増えるか、またはその負担が増えるか減るかをベースに考えられています。そこでは、その資産・負債が現在の時点でどのような評価が与えられるか、今それを処分すべきかどうかは考慮されていません。同一の基準、同一の尺度で、これらが今どのような状況にあるかを知ることが資産・負債の今後の処分・処理の重要な判断基準となります。そこで、資産・負債の現在価値を図る方法として"割引率の概念"を導入する必要があります。
デリバティブ取引は、自己のポートフォリオ(資産・負債)の持つマイナスの側面、つまりリスクを把握する手段として研究・開発され市場性を持って取り引きされるようになったものです。ここで、導入される概念が"割引率の概念"です。現在価値を計る重要な概念といえます。この時、通常の概念では説明できない部分が生じてきます。そこで、ここでは金利概念を別の切り口から説明することが良いのではと考えます。
(2) デリバティブ取引の前提条件
ところで、デリバティブ取引は、その現在価値をベースに取引条件が決められ、ポジションとして把握されます。毎日、さまざまな要因でレートは変動しています。そこで、ディーラーは、その現在価値の変化をみながら、ポジション管理を行ないます。
デリバティブ取引を価格計算する時には、金融取引の内容をキャッシュ・フローとして把握し、それぞれのキャッシュ・フローを各期間に応じた割引率で割り引いて現在価値を求め、将来のキャッシュ・フローの現在価値と等しい値(等価)を求めます。この取引で現在時点の現在価値と将来のポジションの現在価値が等しい時 「等価である」といいます。そして、将来の不確実なキャッシュ・フローについては、数学の確率・統計の手法を使ってその期待値を求めます。この時、この期待値の現在価値を、当該取引の現在価値とみなします。デリバティブ取引の概念については次の項目で説明します。
このような計算手順の背景には、理論の構成といくつかの前提条件があり、その上にデリバティブの取引が成されています。
その前提条件として、経済活動をする上で、規制・制約の無い自由な資本移動が可能となる社会がここにあることを大前提にしています。近代経済学の理論構成の前提条件と同じです。理論と実際の違いを説明・解明し将来の姿を予想することがその学問の学問たる所以です。同様に、現実にお金の移動・利益・損失の発生するトレーディングの世界でもその根拠となるそれなりの理論構成が必要になります。チャート分析・ファンダメンタル分析の必要性が求められるのそのためです。デリバティブ取引の場合もその他と同様に、現実と理論の違いを穴埋めするために、確率・統計学の手法を借りて、これを"リスク"と把握することでさまざまな工夫がされてきました。現代は、実験の段階から実践の段階に移った時期と考えていいと思われます。以下に、理論の前提について整理しておきます。
=====理論の前提として=====
①資本主義社会の根本である、人・法人は利益主体として利益・利潤の最大化のために合理的な行動をする。
②情報については、時間的な差異はあっても平等に共通の情報が入手できる。
③取引に際しては、信用リスクは考慮されない。
この点については、信用リスクを考える前に、デリバティブの場合、その参加者についての開示された情報に基づいた判断が、取引前に成されておりそのリスクはないと考え取引されています。実際には、当事者同士でリスクに見合う分の担保やネッティングの契約が成されており、想像されるほどのリスクは無いと考えられます。しかし、デリバティブ取引の前提は、あくまでその当事者が倒産しないことのみを考え対処していますので、全体のポジション上の影響は一時的には過小に見られています。最悪の場合、つまり恐慌のような長期的・連鎖的な波及効果は予想・想定していませんからやや問題が残ります。
④現資産とそのデリバティブ商品について、金利体系の完璧な・確かなマーケットが存在する。この点については、マーケット・メーカーの役割が重要となります。
⑤デリバティブ取引の参加者は無リスク資産の利子率で自由に資金の調達・運用ができる。
計算上で使われる基準金利LIBOR金利での調達・運用が完全に可能であることを前提に取引が成されています。しかし、最近のように、ジャパン・プレミアムが恒常化してくるようになると、当然のことながら、LIBORでの資金調達は不可能となります。実際の金利計算から考えた場合、採算コストとのずれが生じています。
⑥マーケットで取引されるレートの理論価格は、過去のデーターに従い、一定の確率で規則に従って変動する。オプション理論の"ブラック・ショールズ・モデル"では、相場変動は対数正規分布に従うとされています。金利商品への適用に問題があるため最近では、これを改良した、"ハル・ホワイト・モデル"を利用することが一般的です。
⑦理論価格と実際の価格との間に開きがあるということは、信用リスクの格差・会計制度の違い等理論の前提条件とは異なる条件が存在するためと考えられます。そこに、理論の限界が見られます。そこで、デリバティブに限らずそれぞれのマーケットでは、この理論の限界を補完しながら価格の形成が成されています。理論に対する知識・理解は常識として、その限界を認識しその補完の方法を知ることが、マーケットの参加者にとってもリスク・マネージメントのためにも今後必要になります。
|
(3)キャッシュ・フローの概念とIRR(内部収益率)
キャッシュ・フローとはデリバティブ取引(特に、スワップ取引やオプション取引)において、その取引内容を示したもので、ある一定期間に発生する「資金の受け・払い」を縦軸に「時間」の要素を、横軸に取引としての資金の受払期日と金額を一覧表にして整理し表現したものです。デリバティブ取引の教科書の解説の方法として、また実際のビジネスの上で大変有効かつ便利なものといえます。
1) 単利・複利
単利・複利については、第一部『 [1] 金利とは 』の「 [2] 金利の計算方法 」で説明しています。ここでも、前述と同様に、元本100万円、利率3%、期間10年として考えます。計算式は、省略します。前項を参照してください。
|
単利(simple interest)
単利とは、元本に対して期中発生する利息のみを計算した金利をさします。この時、利息の再運用は考慮しません。
複利 (compound interest)
複利とは、運用期間中に発生する利息の再運用を含めて計算した金利をさします。
|
ここで、単利と複利の違いをキャッシュ・フローの概念を用いて、単利運用(A),複利運用(B)について考えてみましょう。以下に、この一覧表を示します。
|
|
単利運用の場合
|
複利運用の場合
|
|
|
元本の動き
|
運用額
|
受取金額
|
キャッシュ・フロー
|
元本の動き
|
運用額
|
受取金額
|
キャッシュ・フロー
|
|
0年目
|
-100
|
100
|
-
|
-100
|
-100
|
100
|
-
|
-100
|
|
1年目
|
-
|
100
|
+5.00
|
+5.00
|
-
|
105
|
+5.00
|
-
|
|
2年目
|
-
|
100
|
+5.00
|
+5.00
|
-
|
110.25
|
+5.25
|
-
|
|
3年目
|
+100
|
-
|
+5.00
|
+105
|
+100
|
-
|
+5.51
|
+115.76
|
|
合計
|
+15.00
|
+15.76
|
キャッシュフローの一覧表を見ると、次のことが理解されます。
単利運用の考え方には「時間の要素」が含まれていません。つまり、受取利息の「再運用」が考慮されていないことが分かります。
一方、複利運用(B)の場合は、100万円の初期投資から毎年3万円の金利収入が発生し、この利息を「再運用」することでさらに利息を生むことが分かります。
2)金融取引の評価
ア)単利による価値評価
単利による価値評価は、期中の収入(受入利息及びキャピタル・ゲイン)を足し合わせ、「収益総額」を出し、これを当初の元本および期間で割ります。このようにして、"各期平均の収益率"を表わすことができます。日本では、国債の利回りのように単利の概念で議論されることが多いようです。
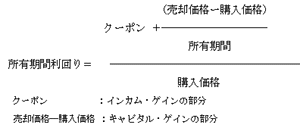
イ)複利による価値評価
複利による価値評価は、IRR (Internal Rate of Return:内部収益率または投資収益率)が用いられる場合が多い。
IRRとは、当初の投資元本とその投資元本から将来発生する一連の収益の現在価値総額一致するような一定の収益率(割引率)"のことをさします。
つまり、次のような式に表現できます。
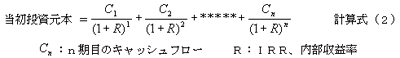
これを、Σ記号を用いると、次のように整理できます。

ここで、同じキャッシュ・フローを単利ベースとIRRベースで計算した場合を例にして比較してみます。
|
0年目 -100 …当初の投資元本(当初のキャッシュ・フロー)
1年目 + 9
2年目 + 9 …将来の収益 (将来のキャッシュ・フロー)
3年目 + 10
4年目 +110
|
単利ベースで計算すると次のようになります。
|
(8+9+10+110―100)÷4(投資期間)
|
|
|
|
= 9.25%
|
|
100
|
|
複利ベースで計算してみましょう。前節のように計算式(2)に代入すると、
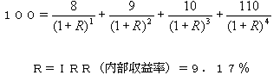
|
となります。
<注意>
複利による運用の場合、『再運用』を考える時、金利の期間構造を考慮していないため、各キャッシュ・フローの再運用金利が一定であると仮定しています。つまり、市場金利のイールド・カーブ(後述)が完全にフラットになっていることを前提にしています。
|
3) キャッシュ・フローの価値
金融取引、特にスワップ取引は、将来の一定期間にわたるキャッシュ・フローの交換を現時点で約束する取引です。「現在価値」は、この当該取引の内容・条件を考える時の尺度・物差しとして利用されます。
そこで、取引の受取・支払の相反する形態のキャッシュ・フロー(固定金利・変動金利)を現在価値へ引き直し、これらが等価であるかどうかを比較します。この現在価値への引き直しの際に、利用される金利が「スポット・レート」・「ディスカウント・ファクター」・「フォワード・レート」(『イールド・カーブ分析の基礎』の項目で説明します。)です。
ここで、現在の100と1年後の100のような時系列で異なるキャッシュ・フローを比較することにします。
ア) 将来価値(FV: future value)
いま、100の元本を持っていて、その元本を現在の金利水準で運用することを考えます。運用金利を5%とすると現在の100は1年後に元利合計で105になります。
ここで、元本も何も無い人々から見た場合はどうでしょうか。"[1]金利とは"の概説で説明したように、現在のことと、将来のことを比較した場合、現在(いま)を重要視する考え方が主流になっています。このような人々にとって、現在の100のほうが1年後(将来)の100より価値があることがわかる。
この時、このような人々にとって、運用金利が5%の場合、「現在の100」と「1年後の105」が等価であることが理解されます。この1年後の105を、現在の100に対する1年後の将来価値といいます。
|
|
1年間
|
|
|
100.00
|

|
105.00(将来価値)
|
|
|
5%運用
|
|
イ)現在価値(PV:present value)
ここでは、1年後(将来)の100を現在の価値に置き換えた場合を考えます。
ここでも、1年の金利を5%とします。
この時、元利合計で100になるような投資額を Xとすると
X × (1+5%)=100 、X=100÷(1+5%)
ここで求められた95.24を将来の価値に対する現在価値、5%を割引率(discount rate)といいます。
|
|
1年間
|
|
|
95.24
|

|
100.00
|
|
現在価値
|
5%割引
|
将来価値
|
5%を割引率とすると、「現在の95.24」と「1年後の100.00」が等価であることが理解できます。
====現在価値(PV)と将来価値(FV)====
これを、整理すると、次のようになります。
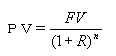
|
PV :現在価値 (Present Value)
FV :将来価値 (Future Value)
R :割引率 (Discount Rate)
n :現在から将来までの期間
|
4)NPV 正味現在価値(Net Present Value)
ア)NPVとは
すべてのキャッシュ・フローを現在の価値に置き直して考えると、すべての支出(キャッシュ・アウトフロー)の現在価値と収入(キャッシュ・インフロー)の現在価値を直接比較することができるようになります。
資金の調達(借入れ)や運用(投資)などの取引を行うと、資金のイン・フロー (収入)と アウト・フロー(支出)が必ず発生します。
例えば、余裕資金があり、1年間5%の金利で運用するという場合を考えてみます。現時点で100の資金のアウト・フロー(マイナスのキャッシュ・フロー)と1年後に105の資金のイン・フロー(プラスのキャッシュ・フロー)が発生します。この時、資金の「収入」・「支出」をすべて「現在価値」に引き直して、その合計を出せば、プラスとマイナスがネットされ、その残った額が、現在価値ベースの収益ということになります。そのネット額を指してNPV(正味現在価値:net present value)といいます。
NPV= [キャッシュ・インフローの現在価値] + [キャッシュ・アウトフローの現在価値]
このNPVは、また投資の評価数値として投資判断の際に重要視されます。複数のキャッシュ・フローから構成される投資案件を、初期投資、金利、資本回収など想定されるイン・フロー、アウト・フローすべてのキャッシュ・フローを「現在価値」に引き直し、これを合計して比較検討します。そして、その投資案件の可・不可を判断するすることになります。
イ)NPVの一般式
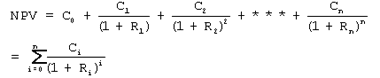
Ci :i期のキャッシュ・フロー Ri:i期の評価に適用される割引率
上の式から理解されるように、期間[i]が0からnになっています。これは、初期投資額も計算に含めことで、そのネット額を算出しやすいように工夫したためです。
現実的にNPV(正味現在価値)を利用するためには、インターバンクで取引されている期間の異なる金利を使用して、実際に近い評価基準となるように工夫しなければなりません。
ここで,NPVの式とIRRの式を比較してみることにします。それぞれの一般式は非常に似ています。
<NPVの式>
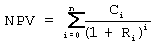
Ci :i期のキャッシュ・フロー
Ri :i期の評価に適用される割引率
<IRRの式>
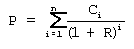
P=当初投資元本
C n : n期目のキャッシュ・フロー
R :IRR (内部収益率)
NPVの式とIRRの式を比較するために、IRRの式を少し変形すると当初投資元本を支払・受取りを考慮のうえ、C0としたとき、つまりn=0のとき、
C0=ー〔投資元本〕となります。

となります。
両者の相違点は、IRR(内部収益率)で使用されるR(割引率)が「一定の金利」であるのに対して、NPV(正味現在価値)のRⅰは期間に対応する「基準となる金利」で、期間ごとに異なる点であるといえます。特に、IRRの場合、再運用金利(収益率)を同一のものとして考えており、評価するキャッシュ・フローが再運用あるいは再調達の市場金利の変化に対応した判断基準ではないことを考慮しなければなりません。
5)キャッシュ・フローの元利展開
元利展開とは、キャッシュ・フローの成分を元本と金利の部分に区分し、その性質を理解しようとするものである。たとえば、元利均等分解弁済型のローン(住宅ローン等)の毎期支払額を元本弁済部分と金利支払部分とに分けたり、スワップ取引において、いわゆるクーポン・スワップのキャッシュ・フローを、経理上の理由から、元本と金利部分に分けたりするときに用いる手法です。また、それはデリバティブ金利商品の開発を考えるときに、有効な手段となります。
ここで、キャッシュ・フローの例として次の条件を考えてみましょう。
まず、キャッシュ・フローは、100の借入れをして毎年24.5を支払うと、5年目の24.5の支払をもって、借入れた元本及び利息をすべて返済したことになるような例を取ります。
はじめに、このキャッシュ・フローのIRR(内部収益率)を『エクセル』によって求めると、IRRは、7.17%と計算できます。このIRRを各支払期間の期初の元本残高に掛けて、その期の利払額を求めます。その利払額と支払額(毎年の24.5)の差が元本弁済額になります。
このようにして元本展開した結果を一覧表にすると以下のようになります。
|
キャッシュフロー分析
|
|
年
|
キャッシュ・フロー
|
元本残高
|
元本返済
|
利払い
|
|
0
|
100
|
100
|
-
|
7.170%
|
|
1
|
-24.5
|
82.67
|
-17.33
|
-7.17
|
|
2
|
-24.5
|
64.10
|
-18.57
|
-5.93
|
|
3
|
-24.5
|
44.19
|
-19.90
|
-4.60
|
|
4
|
-24.5
|
22.86
|
-21.33
|
-3.17
|
|
5
|
-24.5
|
0.00
|
-22.86
|
-1.64
|
|
IRR
|
7.170%
|
3.138
|
-
|
-
|
〈解説〉
1年目の利払額は、100 × 7.17%=7.17となります。そして、この利払額を 支払額廼24.5から差し引いた残りの17.33が元本弁済額となります。このときの元本残高は、82.67(=100-17.33)です。
2回目は、82.67を元本として計算されますから、5.93となります。2回目の支払額24.5のうち5.93が利払い分となりますから、残りの18.57は元本弁済額となります。同じ作業を繰り返すと、5年目の支払によって、元本は無くなり、元本展開が完了します。
なお、この借入は、 5年で分割弁済されますが、借入の平均年限は3.138年となります。
平均年限(Average Life)とは、元本残高の合計を当初の元本で割ったものです。
|
|
|
Σ(各期の元本残高)
|
|
平均年限
|
=
|
―――――――――――
|
|
|
|
当初の元本
|

(4)割引率について
デリバティブの金利商品(スワップ、オプション等)については、「将来のキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて評価する」という考え方が基本になっています。
①スワップ(金利スワップ・通貨スワップ)
現在価値が等価なキャッシュ・フローの交換
②オプション
将来のキャッシュ・フローの期待値としての現在価値をプレミアムとして受払い
割引率(Discount Rate)とは、将来の特定のキャッシュ・フロー(将来価値)を現在価値に割り引き、評価するときに用いられるものです。
この割引率として、一般的にゼロ・クーポン・レート(Zero Coupon Rate)が使われています。
割引率に関連して、①パー・レート(スワップ・レート)、②ゼロ・クーポン・レート(スポット・レート)、③ディスカウント・ファクター、④フォワード・レートの金利概念・意義を理解する必要があります。これらのデータとその分析が時価評価・リスク管理を進めていく上でその基本となります。当然、金利デリバティブの取引の基本です。ここでは、これらの概念を説明し、次の『イールド・カーブ分析の基礎』でその計算方法を説明します。
|
1)パー・レート(スワップ・レート)
|
|
価格が額面で取引されている利付き債券、IRS(金利スワップ)で取引されているマーケット・レートのように、定期的に金利の支払いが行われる債券・スワップ・レートをさします。スワップ・レートは一定期間での金利を複利で計算した商品で、一定の満期をもつパーの利付き債券利回りの代用として利用することができます。基本的に、債券を原資産とするデリバティブ商品ですから。
|
|
2)ゼロ・クーポン・レート(スポット・レート)
|
|
ゼロ・クーポン・レートとは、投資時点と回収時点のみキャッシュ・フローが発生する金利のことをさします。解説書によってはスポット・レートともいいます。
現在価値を算出するには、将来価値を単一の金利で直接割り引くため、純粋に2時点のキャッシュ・フローに依存する金利が必要になります。したがって、ゼロ・クーポン・レート(割引率)は割引債の金利と同じものと考えて良いのです。
つまり、ある特定の残存期間に対応する割引債の最終利回りであるともいえます。一般的に、一連の市場金利をベースに、逆算して導き出すことで、ゼロ・クーポン・レート(スポット・レート)を求めます。この計算方法については、次の『イールドカーブ分析の基本』で説明します。
割引債の場合、満期の元本償還時点までキャッシュ・フローが発生しないため、最終利回りが含まれた形となっています。一方、債券・金利スワップのキャッシュフローを考えてみると、特定の期間に対応したキャッシュ・フロー、つまり割引債の集合体として捉えることもできます。
|
|
1年目のクーポン=残存1年の割引債=期間1年のゼロクーポン・レート
2年目のクーポン=残存2年の割引債=期間2年のゼロクーポン・レート
3年目のクーポン=残存3年の割引債=期間3年のゼロクーポン・レート
|
|
ゼロクーポン・レートは、ある特定の期間に対して一義的に決められるため、同一の満期に同額のキャッシュ・フローが存在する場合、計算上必ず同じ現在価値が求められます。また、期間の違うデリバティブ金利の商品の現在価値は、現在時点でのマーケット理論価格を共通の尺度に置き換えて算出されたものと考えられます。ポートフォリオを時価評価する際には、その内容を考慮する必要もなく同一の基準で一様に評価できます。このような評価に限らず、リスクの計量化やポジションの状況を的確に把握し、そのリスク・コントロールにも役立ちます。
ここで取り上げられた割引債は、信用リスクにさらされない主要国の国債、米国財務省証券、又はこれを分解したストリップ債のような"リスク・フリー債券"をベースにしています。
|
|
3)ディスカウント・ファクター(割引係数:Discount Factor)
|
|
|
『キャッシュ・フローの価値』の項目で説明したように、将来価値(FV)と現在価値(PV)の関係は、次の関係式に表現できます。
|
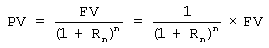
|
PV:現在価値
FV:将来価値
R :割引率
n :現在から将来までの期間
|
このような関係は、割引債の場合にも当てはまります。この時、将来価値と現在価値の比率をディスカウント・ファクターと呼びます。
|
|
|
現在価値(PV)
|
|
ディスカウント・ファクター(DF)
|
=
|
―――――――
|
|
|
|
将来価値(FV)
|
上の関係式から理解されるように、ディスカウント・ファクター(DF)は、n年物複利利回りRnとして、
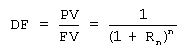
と表現できます。
また、同じように正味現在価値(NPV)の一般式との比較から考えてみましょう。
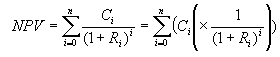
|
Ci:i期のキャッシュ・フロー
Ri:i期の評価に適用される割引率
|
NPVの式を変形すると上のようになります。「将来価値」を「現在価値」に割引く時には、必ず
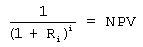
を計算しなければなりません。この式がディスカウント・ファクター(割引係数)です。
|
4)フォワード・レート
|
|
フォワード・レートとは、将来の一時点において、あらかじめ定めた期間の資金運用あるいは資金調達を行った時に受け取ることのできる運用レート、あるいは支払わなければならない調達レートのことをさします。
以前説明したように、スワップ取引とは、現在価値(経済価値)が等価なキャッシュ・フローの交換取引のことをさします。固定金利支払、変動金利受取りの円金利スワップの場合、将来の固定金利支払キャッシュ・フローの現在価値が等しいということになります。
後に説明しますが、固定金利サイド の現在価値は、各利払日の利息額にその期間に対応する割引係数(ディスカウント・ファクター)を掛けることによって求めることができます。
一方、変動金利の現在価値はどのようにしたら求めることができるのでしょうか。ここで、"フォワード・レート"という概念の導入が必要になります。このフォワード・レートとは、現時点の市場金利(割引率/ゼロ・クーポン・レート)を前提にした場合の、将来の特定期間に対応する利子率のことで、いわば変動金利の将来価値の期待値とも解釈できます。つまり、現在から見て、6ヶ月先からスタートする6ヶ月物の適用金利(LIBOR)の金利水準を、現時点のマーケット・レートから理論的に計算し導き出されたものといえます。
ここで、具体的に円6ヶ月LIBORの6ヶ月後から始まる半年間の金利(フォワード・レート)を考えてみます。もしマーケット・レート間に十分裁定が働いているなら、6ヶ月LIBORで半年間運用した元利金を、さらに半年間その時の6ヶ月物LIBOR・RATEで複利運用した場合の元利合計は、一年物のLIBOR(年一回払い)で一年間運用した元利合計とは等しいと考えられます。固定金利の現在価値と変動金利の現在価値(経済価値)は等しいものと考えるのが基本ですから。この時、フォワード・レートは、このような考え方(純粋期待理論)に基づいて求めた先日付の金利と言うことができます。
(1)割引率を使って、投資額をA、半年の金利を2.35%、1年の金利を2.500%として、6ヶ月後スタートの6ヶ月ものLIBOR(フォワード・レート)Xとして考えてみます。
|
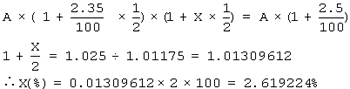
この時のフォワード・レートは2.619224%となります。
以上の関係を図示すると、
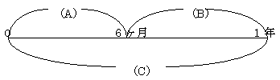
|
(A)6ヶ月の実勢レート(スポット・レート):2.35%
(B)求めるX(フォワード・レート):2.619224%
(C)1年物の実勢金利レート(スポット・レート):2.5%
|
次に、1年後半年間の金利をもとめてみよう。市場実勢金利と割引率の表をみると、1年の金利(割引率)は2.5321%、2年の金利(割引率)は3.0713%である。しかし1年半の金利(割引率)は出ていない。そこで、ここでは一年半の金利は1年物と2年物を算出する。
(2.5321%+3.0713%)x1/2=2.8017%・・・・・1.5年の金利(割引率)
1年後半年間のフォワード・レートをYとすると、
(1+0.025321)X(1+Y+1/2)=(1+0.028017)1.5
1+Y/2=1.0423185/1.025321=1.0165777
Y=0.0165777X2=0.033155→3.3155%
以下、同様に1年半後半年間、2年後半年間ということで市場実勢に応じた、将来の6ヶ月ごとの変動金利の理論値ともいえるインプライド・フォワードレートが求められる。スワップの変動金利サイドも、このインプライド・フォ
ワード・レートを求めることにより、確定したキャッシュ・フローとして把握できるので、あとは各期間に対応する割引率で割り引く(又は割引係数を掛ける)ことにより変動金利の現在価値が求められる。
現実の金利スワップのレートから導き出されるイールド・カーブは、参加者それぞれが考える金利予想に基づいて形成されたものと言えますから、マーケットの金利相場観が反映されていると考えることができます。マーケットの見方が変化すれば、イールド・カーブの形状もそれに応じて変化してきます。
このように考えてくると、円金利のスワップ・レート(LIBORと交換できる固定金利)は変動金利のインプライド・フォワード・レートにより決まることがわかると思う。もし現在の市場金利から算出される(市場が想定している将来の変動金利の推移(インプライド・フォワード・レートの推移)が自分の確信する金利見通しと異なるなら、これを投資機会ととられ、スワップディーリングをすることが可能である。今後3年間の短期金利見通しがインプライド・フォワード・レートほど上昇しないと確信できれば、固定金利を受取り変動金利を支払うスワップを行えばよい。
自分の予想どうり金利が上昇しなければ、実際に支払う変動金の現在価値は受け取る固定金利の現在価値より小さくなるだろう。また市場が将来の金利上昇見通しを修正しだすと、スワップ・レートも低下していくので、そこで逆取引のスワップをしてポジションをクローズすれば収益がとれることになる。
[2]デリバティブ商品の金利
(1)デリバティブとは
デリバティブ(derivative)とは、辞書的には『「本源・源泉」から…を得る』ことから発生した「派生物」です。金融商品で使われる場合には、「もとになる原金融資産(預金・為替・債券・株式等一般的に取引されている商品)から、その経済効果の一部を取り出した商品」といえます。
デリバティブ商品を定義・取引方法・取引形態を基準に分類することが出来ます。ここでは、分類の羅列は止めにして、基本となる原資産別の分類をあげておきます。
|
対象
|
原資産
|
デリバティブ商品
|
|
短期金利
|
預金
|
短期金利先物・金利先渡取引等
|
|
長期金利
|
債券
|
債券先物・金利スワップ取引等
|
|
通貨
|
直物為替
|
通貨先物・通貨スワップ取引等
|
|
株式
|
現物指数
|
株式指数先物・株式指数オプション等
|
|
商品
|
現物商品
|
商品先物・コモディティ・スワップ等
|
ここでは、金利に絡むデリバティブ商品についてに絞ります。取引所を通した取引かどうかで区分すると、取引所取引(LISTED)である短期金利先物・債券先物と店頭取引(OTC)である金利スワップ・FRA(金利先渡取引)に分けられます。
金利先物は、「決まった取引所を通して、現時点で、将来のある時点に、標準化された商品を、購入または売却することを約束する取引です。
金利先物市場では、現物市場と異なり、商品の単位・期間・値刻みがあらかじめ定められており、市場へは一定の証拠金を積み、その残高を一定水準以上に維持することで参加することが出来ます。取引の決済は、基本的に反対取引(購入に対しては売却、売却に対しては購入)をすることで行われます。現物による受渡し決済はまれです。取引を取組む際、元本の受渡しがないためリスクは限定的なものと考えられます。
預金(exユーロ¥預金)を原資産とする、短期金利先物取引と債券を現資産とする債券先物取引があります。
2)短期金利先物
短期金融市場等では、CD・CP・ユーロ預金・TB等の商品が取引されています。今 自ら保有する金融資産や負債、及び将来保有する予定の資産や負債を、現段階で将来の予期せぬ金利変動リスクから回避する目的で創設されたのが、短期金利先物市場です。原資産のリスクを軽減し、投資の目的にも利用されています。先行きの金利変動を予測しへッジする行動は、その相場の動きを激しいものにしています。その意味で、代表的な指標として注目すべきものの一つです。
短期金利先物は、1976年1月に米国シカゴのCME(シカゴ商業取引所)の一部門としてのIMM(International Monetary market,シカゴ国際金融先物市場)に、T-BILL(90日物)が上場されスタートとしました。CP(30日物、90日物)、CD(90日物)、ユーロ$(3ヶ月物)と新商品が次々と開発され上場されてきました。我が国も、リスクのへッジの必要性から、東京金融先物取引所において、1989年6月にユーロ¥(3ヶ月物)、ユーロ$(3ヶ月物)の金利先物取引が開始されました。日本に先立ってユーロ¥(3ヶ月物)が、1984年11月にはSIMEX(シンガポール)に上場されました。今では米国IMMにも上場されていますので24時間取引が行われているといえます。
現在では、先物金利のレートを利用して、次に説明する金利スワップ・FRA等の理論値、またはそのプライシングに使用されるのが一般化しています。
3)債券先物
債券先物市場が1980年代に入って、各国で相次いで創設されました。“日本機関車論”に見られるように、国際・国内経済の状況から、各国は財政規模を拡大させる政策、それに伴う国債の大量発行の必要がありました。大量に発行される国債を円滑に消化するためには、現物市場の整備するだけでは不十分です。国債の流通を円滑にするための流動性確保のためのシステムを作る必要があります。先物取引の持っている「へッジ機能」及び「現物と先物の裁定機能」を通じた国債市場全体の流動性確保の為の仕組を導入する必要がありました。それが、先物市場です。各国のお家の事情から発生したものとも考えられます。
債券先物取引は、アメリカのCBT(Chicago Board of Trade 、シカゴ商品取引所)において、1975年10月、GNMA証券(アメリカ政府抵当金庫証券)が上場されたのが始まりといわれています。その後、米国長期財務省証券(T-Bond)1977年8月、米国中期財務省証券(T-Note)1979年6月・・・と、おのおのCBTにおいて上場されました。その後、イギリスのLIFFE(London International Financial Futures Exchange、ロンドン国際金融先物取引所)において、英国長期国債が1982年11月に、T-Bondが1984年6月、日本国債 が1987年7月にそれぞれ上場されました。シンガポールでは、SIMEX(Singapore International Mercantile Exchange、シンガポール国際金融先物取引所)のおいて、T-Bond先物が1986年10月に上場されました。日本の場合は1985年10月に、東京証券取引所に日本国債の先物が上場されました。このように、世界の主要金融市場 で債券先物取引が行われています。
4)金利スワップ(IRS)と通貨スワップ
①スワップとは、“交換”のことをさします。ここでは、相対する当事者間でお互いに“等価”と思われるものを交換する取引です。
堅苦しく言えば、スワップ取引とは「将来の一定期間に起こる経済価値が等価であると考えられる二つのキャッシュ・フロー(金融取引から発生する現在及び将来の現金の受け払いのこと)を相対する当事者間で合意した条件のもとで支払い・受け取りをお互いに行う取引である。」と定義されます。また、店頭取引の一つと考えられます。
経済価値・キャッシュフロー等については後述の「デリバティブの金利概念の基礎」で説明します。
②スワップ取引は、大きく金利スワップと通貨スワップに分けられます。
金利スワップとは、同一通貨間の異なる種類の金利の将来のキャッシュ・フローを交換する取引です。この取引は、元本の交換はなく金利計算の際に名目上の元本(想定元本、Notional Principal Amount)が契約されます。
一方、通貨スワップとは、異種通貨間の異なる種類の金利の将来のキャッシュ・フローを交換する取引です。この取引の場合、元本の交換があり、金利計算の際実質の元本(この場合も想定元本と呼んでいます)が契約されます。
これらの取引は、基本的にその想定元本が変化しないスワップが一般的です。しかし、最近、一定期間毎に元本を返済するローン等を対象にする取引ニーズが増えてきており、その形態に変化が見られます。このため、想定元本の変化するスワップも取引されています。
③公表されたスワップ取引で、最も古いとされるものは、1981年のIBMと 世界銀行との間で取引された通貨スワップとされています。
IBMのUS$調達ニーズと世界銀行のスイスフラン調達ニーズが存在し、お互いのスイス市場・アメリカの市場における比較優位性(当時の市場間の不合理性・制約によって生じたもの)を利用することで、各々が直接起債するよりも有利な条件で調達が可能となった例です。
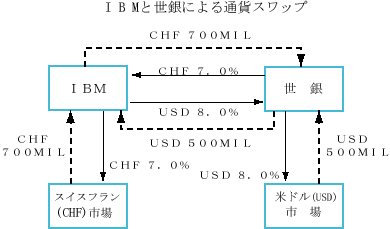
その後、金利スワップも含め1983年頃より欧米で普及し、80年代後半日本でも導入され拡大しています。
金利スワップ・通貨スワップ等のスワップ取引については、第二部で説明します。
5)FRA
①FRAとは、Forward Rate Agreement(または、Futures Rate Agreement)の略で、金利先渡契約とも呼ばれます。この商品は、我がトラディション・グループが“Futures Rate Agreement”と命名し外国為替取引・外貨資金取引市場で世界で初めて商品化し、規格化したものです。しかし、“Forward Rate Agreement”の名称が一般的となっています。名称は別として、最近ではこのプライスの形成にあたって金利先物(FUTURE)をベースにすることが常識とされる関係からホームページ上では解説には“Futures Rate Agreement”と呼んでいます。なを、ホームページには、マーケットレートに近い理論値を掲載してあります。今後の金利の予想をする上で、便利なものと思われます。参考にして下さい。
②FRAは短期金利先物取引と比べて取引所取引ではなく、取引内容に対する 所与の条件設定がなく全て相対取引(店頭取引)とされています。また、この取引は双方が将来の期間の金利水準を前もって約定するもので元金の移動を伴わず、その約定金利とFixing Rateとの差額だけを決済する差金取引です。
このFixing Rateは、基本的には前述のLIBOR or TIBORのレートを使います。
③FRAの決済金額の算出については、相対取引であるため、個々の契約によってその計算式を決めることができますが、ユーロ市場においては、1984年にイギリス銀行協会(British Bankers Association)が取引慣行を整備するためにイングランド銀行(英国中央銀行)をオブザーバーとして作業部会を設置して“FRABBA”フラバ(“Forward Rate Agreement、British Bankers Association”Terms)と称する推奨ルールを作成し、1985年9月2日付けで施行されました。この推奨ルールの計算式については、第二部で説明します。
④FRAの特徴と取引メリット
以下に、FRAの特徴とメリットについて箇条書きしておきます。
★資産・負債の増加を伴わないオフバランス取引です。従って、バランスシートの膨張を抑えることが出来ます。一方、BISによって要求されている自己資本比率との関係は極めて小さいものとなります。
★将来の金利変動をへッジすることによってそのリスクを回避することができます。
★相対取引ですから、金額・期間・取引開始日等の条件を自由自在に決められます。従って、個別のニーズにあった約定が出来ます。
★差金決済ですから、後で説明する“信用リスク”が小さくて済みます。
★基本的に割引方式で計算されます。従って、約定期間のスタート日に前払い決済となりますから、そのスタート日に損益の確定が出来ます。
⑤日本において、その取引形態から“刑法上の賭博罪に抵触する恐れがある”として大蔵省が事実上禁止してきましたが、1994年から、国際金融市場の発展の流れに遅れないために解禁されました。しかし、残念ながら市場においてはあまり取引されておりません。
|
6)金利オプション
|
|
|
①オプション(Option)とは、対象となる商品(原資産)を一定の価格で、一定量、一定期間 (その期間内)に「買い付ける権利 または買う権利」(コール・オプション、Call Option)、または「売り付ける権利または売る権利」(プット・オプション、Put Option)のことをさします。オプション取引とはこれらの権利を売買することをさします。そして、オプションの契約レートを「行使価格」(ストライク・プライス、Strike Price)と呼びます。
②先物取引と比べると、先物取引では、売り手・買い手ともに対象となる商品の売り・買いを履行する義務を負います。一方、オプション取引では、オプションの売り手だけが対象となる商品の売り・買いを履行する義務を負います。オプションの買い手は、売り手に対して売り・買いの履行を請求する権利を持ちますが、義務は負いません。しかし、オプションの買い手は有利な分だけ売手に対してオプション料(プレミアム)を払わなければなりません。
③金利オプションとは、金利に関するオプションのことです。その取引とは、将来のある一定の金利で取引を行う権利を売買する取引をさします。通貨オプションの場合と同様に、オプション締結時にプレミアムの受け払いをするのが普通ですが、対象となる商品が金利であるためにプレミアム分を金利に織り込んで受け払いする商品も出ています。
④以下、金利オプションを理解するのに必要とされる概念を取上げることにします。
(a)金利の期間構造(イールド・カーブ)
金利の今後を予測するためにも金利の期間構造を理解することが必要です。特に、金利オプションの場合、将来時点の金利を取り扱うことが多いため、期間構造(イールド・カーブ)の形状を把握することが重要になります。この項目については、後述の[イールドカーブ分析の基本]に譲ります。
|
(b)キャップとフロア
指標となる短期金利を対象とする金利オプションのことです。対象となる金利として、LIBOR・TIBORが一般的です。その他、短期プライムレート・スワップレート・CP(コマーシャル・ペーパー)をその対象とする商品も出ています。
キャップとは、これらの対象となる金利が将来のある時点で一定水準(上限金利、行使価格、ストライク・プライス)を超えたときに、超過した金利相当分の金額を、キャップの売手が買い手に対して支払う取引をさします。この時、プレミアムは保険料に相当するものと考えられます。
例えば、LIBORベースで調達している場合、キャップを購入すれば、LIBORが上昇すれば支払金利が増加しますが、その契約の上限金利であるストライク・プライス以上の増加分はキャップによって補填することが出来ます。
[取引例として]
|
想定元本 :
|
5億円
|
|
期間 :
|
3年
|
|
指標となる金利 :
|
¥3ヶ月LIBOR(3ヶ月ごとの見直し)
|
|
上限金利 :
|
¥1.5%
|
|
プレミアム :
|
15百万円(想定元本の3%、一括前払い)
|
[プレミアム・金利の流れ]
<約定時点>
|
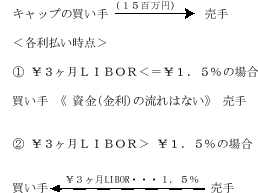
|
このように、金利上昇に対する保険として利用できます。特に事業法人の場合には、変動金利での借入が多く、金利上昇のリスクへッジ手段の一つとしてスワップ取引とならんでキャップを購入(買い手となる)することが多くなっています。
|
|
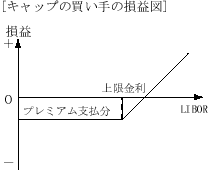
|
フロアとは、キャップの場合とは逆に、対象となる金利が将来の ある時点で一定水準(下限金利)を下回った時に、下回った金利相当分の金額をフロアの売手が買い手に対して支払う取引をさします。
キャップ・フロアは先スタートの金利(将来のある時点の金利)を対象にしたオプションですから、金利先物オプション(第二部で説明します)の店頭取引版ともかんがえられます。従って、呼び名は別としてフロアは金利先物のコールオプション、キャップは、金利先物のプットオプションに類似したものと考えられます。
|
(c)プレミアム(オプションの価値)
プレミアムとは、オプションの買い手が売り手に対して支払う金額のことをさします。キャップの場合には、“キャップ料”とよぶことがあります。保険としての意味合いが強いものと考えられます。プレミアムはオプションの価値と同義といえます。
オプションの価値は“本源的価値”と“時間的価値”に分けられます。
①本源的価値(Intrinsic Value)
本源的価値は、目的のオプションを今すぐにでも行使したときの価値をいいます。つまり、現在の市場金利から算出されたときの価値です。ただし、この価値がマイナスのときは、ゼロと評価します。
キャップ取引の場合、その本源的価値は、市場金利から算出されるフォワードLIBOR(後述、イールドカーブの項目で説明)と契約の上限金利との差として表現されます。
例えば、各利払い日のフォワードLIBORが次のように算出された場合、
上限金利 :3%
期間 :3年のキャップ取引
フォワードLIBOR
|
<A>スタート時:
|
1.5%
|
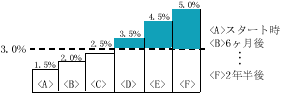
|
|
<B>半年後 :
|
2.0%
|
|
<C>1年後 :
|
2.5%
|
|
<D>1年半後 :
|
3.5%
|
|
<E>2年後 :
|
4.5%
|
|
<F>2年半後 :
|
5.0%
|
この場合の本源的価値は上図の斜線部分といえます。<C>の段階までの価値はゼロとかんがえます。
②時間的価値(Time Value)
時間的価値は、「そのオプションが満期日に価値を生じる確率が生む価値」をさし、確率統計の考え方を利用して評価されます。また、別の説明として、時間的価値は、LIBOR決定までの時間とボラティリティ《予想変動率、次の(4)ボラティリティ参照》によって決められます。
本源的価値の例をここでも使います。2)の段階のように6ヶ月後のフォワードLIBORが2.0%のとき、上限金利3.0%キャップの本源的価値はゼロですが、そこから6ヶ月後にそのLIBORが3.0%に上がる可能性はゼロではありません。理論上の数字に限らず市場のレートはもろもろの予想の上で決まるものですから、可能性があるといえます。この可能性または期待が“時間的価値”といわれるものです。この“時間的価値”は金利の変動性(ボラティリティ)が上がるとき、例えば、金利が大きく動くと市場の期待が高まった時、その“時間的価値”は上がることになります。
(d)ボラティリティ
①ボラティリティとは
前述のようにプレミアムは本源的価値と時間的価値で構成されています。ボラティリティは、時間的価値の構成要素であり、将来の金利の変動性を示す指標です。一般的に、ある確率分布を対数正規分布として扱い計算し、ボラティリティはこの標準偏差を年率で表現したものです。
金利オプションの場合、将来のある時点における金利をフォワードレートを中心(統計学でいう平均値)とした確率分布であると考えます。
②一般的傾向として
金利オプションのボラティリティ・フォワードレートとキャッププレミアムの関係を概念的に整理すると、
ボラティリティが大きくなると、キャッププレミアムは高くなり、ボラティリティが小さくなると、キャッププレミアムは安くなります。一方、フォワードレートが高くなると、キャッププレミアムは高くなり、フォワードレートが低くなるとキャッププレミアムは低くなります。
③金利のボラティリティの特性
株・為替のオプションと違い金利オプションの場合そのボラティリティは期間が長くなるほど小さくなります。一般的に、その理由として、金利は上下の変動があっても中長期的にみると、平均的な値に近づく性質(平均回帰性という)が認められることをあげています。
④ボラティリティの計測方法
その計測方法として、次の2つが上げられます。
インプライド・ボラティリティ
現在、金利オプションの市場で取引されているプライス(プレミアム)から逆算して出されたボラティリティ
ヒストリカル・ボラティリティ
過去の金利から計算されるもの。ポジションをもって今後の動きを予想する際に有益ですが、マーケットでは直近の動きが重要と考える傾向があり、参考値として捉える人が多い。
(e)スワップション
スワップションとは、指標となる金利として長期金利 特にスワップ・レートをその対象とする金利オプションです。それはスワップ・レートを将来のある時点で開始する権利の売買です。
スワップションのの買い手は、売り手に対してプレミアムを払い、それによって契約のスワップ取引を開始する権利を得ることになります。
スワップションには、次の様なものがあります。
①コール・スワップション(レシーバーズ・スワップション)
……固定金利を受け取るスワップの開始権の売買
②プット・スワップション(ペイヤーズ・スワップション)
……固定金利を支払うスワップの開始権の売買
[取引例として]
(対象となるスワップ条件)
|
想定元本 :
|
5億円
|
|
期間 :
|
1年先スタート4年
|
|
A社支払い金利 :
|
¥2%(固定金利)
|
|
A社受取り金利 :
|
¥6ヶ月LIBOR(変動金利)
|
(オプションの条件)
|
スワップションの買い手 :
|
A社
|
|
スワップションの売り手 :
|
B銀行
|
|
想定元本 :
|
5億円
|
スワップションのプレミアム
支払人:A社
金額 :2.5百万円(想定元本の0.5%、一括前払)
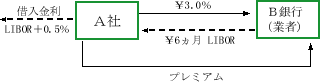
1年先の時点で、4年物スワップレートが2.0%以上(例えば3.0%)になっている場合、A社にとって、新たにスワップを組み直すよりもスワップションの権利を行使した方が有利ですから、A社はこの契約の権利を行使することになります。
反対に、4年物スワップレートが、2.0%未満であれば、このスワップションの権利を放棄して、新たにスワップを組んだ方が有利になります。
スワツプを新たに取組んだ方が有利かどうかが、権利行使の有無の判断基準になりますが、実際には細かくこれらのコストを計算した上で、じっさいの経済状況等をも加味して判断されるものです。